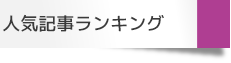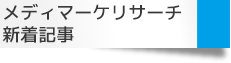■行政トピックス
1. 厚生科学審議会感染症部会 10月9日 インフル・新型コロナ同時流行備えサーベイランス強化へ
■記者会見
1. 毎年薬価改定で「投資優先順位は下がる」-PhRMA:ジョバンニ・カフォリオ会長-
■セミナー便り
1. アルコール依存症に対する適切な理解が必要-国立病院機構久里浜医療センター:樋口進院長-
2. BS「促進施策や阻害要因改善に取り組む時期」-日本バイオシミラー協議会:南部静洋会長-
3. 33%の保護者が予防接種を延期-すがやこどもクリニック:菅谷明則院長-
■行政トピックス
1. 厚生科学審議会感染症部会 10月9日
インフル・新型コロナ同時流行備えサーベイランス強化へ
厚労省は今冬のインフルエンザと新型コロナウイルス感染症の同時流行に備え、サーベイランスを強化する方針を、10月9日の厚生科学審議会感染症部会に提示した。症状のみによる鑑別診断は難しく、地域における流行状況を把握しておきたいという医療現場の要請に応えるもの。現在、厚生労働科学研究班で実施している三重県における取り組みを全国に広げたい考えで、「この取り組み自体は既に9月末から始まっており、早めに他の都道府県に紹介したい」(同省)とした。
現行のサーベイランスは、インフルエンザの場合、全国約5000カ所の定点医療機関から(1)突然の発症、高熱、上気道炎症状、全身倦怠感等の全身症状の全てを満たす(2)迅速診断キットによる病原体の抗原の検出-を基準に患者数が報告される仕組み。ただし、実際は(2)により報告される場合が多くを占める。
一方、新型コロナウイルス感染症の場合、全国全ての医療機関からPCR等の検査で診断された患者数が報告されている。
今冬に重複感染を含め同時流行するリスクがあり、検査診断が必要不可欠だが、医療機関によっては、鼻咽頭拭いの場合の飛沫曝露リスクなど十分な安全対策ができておらず、既に発熱の患者は診ないという医療機関も出てきている。
現行の日本のインフルエンザサーベイランスは、迅速診断キットに頼っているため、地域でのインフルエンザの患者数を示すのみで、インフルエンザ様の症状を呈する患者数全体、インフルエンザの陰性患者がどのくらいいるかが分からないという課題がある。
WHOが勧奨する世界標準とされるインフルエンザのサーベイライスは、発熱と咳の症状のある人をインフルエンザ様疾患(ILI=インフルエンザ・ライク・イルネス)と定義し、報告する仕組み。全外来受診者数に占めるILI患者比率を見ることによって、医療負荷を示唆することを主眼とする。
また、ILIに占めるインフルエンザウイルス陽性比率を見ることによって、地域で発熱と咳の症状を呈する患者を診たときに、インフルエンザであるリスクを把握することが可能になる。ILI患者数に比べてインフルエンザ陽性数が低ければ、それ以外が疑われる根拠となる。
実際、米国における19/20シーズンのILIサーベイランスでは、3つのピークがあったが、3つ目のピークではインフルエンザウイルスがほとんど検出されず、新型コロナウイルス感染症であることが分かった。
厚生労働科学研究班で実施している三重県における取り組みでは、県内の全72カ所(内科27、小児科45)のインフルエンザ定点医療機関から、感染症法の症状定義に基づいて突然の発症、高熱、上気道炎症状、全身倦怠感等の全身症状の全てを満たす患者をILIとして報告(迅速診断キット施行の有無を問わない)。
これでは上気道炎症状のみの患者が漏れてしまうため、ILI以外の上気道炎(発熱の有無は問わない)または味覚臭覚症状のある患者を新型コロナウイルス様疾患(CLI=COVID-19・ライク・イルネス)として報告する(検査の有無を問わない)。
そして、ILIおよびCLI報告が行われた症例について、インフルエンザおよび新型コロナウイルス両方の病原体検査を行い次の通り9項目の指標を把握する。(1)ILI患者数(2)CLI患者数(3)ILIにおけるインフルエンザ陽性率(4)ILIにおける新型コロナウイルス陽性率(5)CLIにおけるインフルエンザ陽性率(6)CLIにおける新型コロナウイルス陽性率(7)新型コロナウイルス鑑別対象患者数(ILI+CLI)(8)新型コロナウイルス鑑別対象患者数におけるインフルエンザ陽性率(9)新型コロナウイルス鑑別対象患者数における新型コロナウイルス陽性率-。
■記者会見
1. 毎年薬価改定で「投資優先順位は下がる」
-PhRMA:ジョバンニ・カフォリオ会長-
PhRMAのジョバンニ・カフォリオ会長(BMS会長兼CEO)は10月9日の記者会見で、「バイオ医薬品業界が継続的に革新的な医薬品を研究開発し続けていくため、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)を含む全ての疾患を予防、治療、治癒するためには、安定した予測可能な医療制度が必要だ。その制度は公平で透明なルールがあり、イノベーションを認め、報いるものでなければならない」と要望した。毎年の薬価改定に関しては「どのようなルールであっても、革新的な医薬品を年次の薬価引き下げの対象とするのは、イノベーション促進環境に悪影響を与えると考えられる。製薬企業にとって投資先としての優先順位が下がる」と語った。
ジョバンニ会長はPhRMA加盟企業がCOVID-19に対するワクチンや治療薬の研究開発を進めている他、パンデミック下のエッセンシャルワークや失業などにより患者数が増加すると予想される精神疾患領域での新薬開発を進めていることなどを紹介し、「我々の業界は大きな価値を社会にもたらそうとしている」と強調。一方、日本の社会保障費の抑制が薬価削減に依存している構造や、日本におけるバイオ医薬品業界の研究開発投資が15年から18年にかけてマイナス成長になっていることに触れた。
ジョバンニ会長は今回のパンデミックによって薬価削減に依存した社会保障費抑制を「リセットをする機会を与えられた」との見方を示し、「我々は医療制度や医療支出の全体像を見て、全体として非効率な場所を探す、そして改善の機会を探すことが必要だと思う。世界中の多くの国で縦割り型に見て、その支出の一部を見てきた。システム全体を見る機会をいま提供されたと思う。10月に具体的な政策提言がPhRMAから出てくるので、その対話を続けていきたい」と語った。
日本の投資先としての魅力に関しては「優秀な臨床医や研究医が数多く存在する。活発なエコシステムがある。日本には投資を続けたいと思う。懸念しているのは、日本の政策が我々の投資能力にマイナスの影響を与えるのではないかということだ。本当にもっとスピーディーにオープンな対話を持ちたい。研究のポテンシャルが日本のエコシステムと我々の業界との協業によって最大限発揮されることを願っている」とも語った。
■セミナー便り
1. アルコール依存症に対する適切な理解が必要
-国立病院機構久里浜医療センター:樋口進院長-
大塚製薬は10月9日、「アルコール健康障害対策~最近のトピックスと今後の課題~」をテーマにアルコール関連問題啓発プレスセミナーを開催。厚労省のアルコール健康障害対策関係者会議で会長を務める国立病院機構久里浜医療センターの樋口進院長が、アルコール依存症の診断と治療の現状や取り組み、今後の課題などを紹介した。
登壇した樋口院長は、まず始めに「飲酒パターンとアルコール健康障害の現状」について解説を行った。WHOによると、2016年には15歳以上の世界人口の約43%にあたる約23億人が飲酒をしており、そのうち約300万人はアルコール消費が原因と考えられる疾病によって亡くなっている。これは全死亡原因の約5.3%を占めており、結核やHIV、糖尿病などを上回る数字だ。また、アルコール依存症もしくは依存症ではないが健康問題が起きている状況(有害な使用)であるアルコール使用障害の人数は約2億8300万人を数え、15歳以上の人口の約5.1%に当たる。
さらに、日本人の年間平均飲酒量(APC)を10年と16年で比較すると、男性は12.0ℓ→13.5ℓ、女性は2.6ℓ→2.9ℓと、いずれも増加。樋口院長は「1年間で13.5ℓは、350mℓの缶ビールを2本強ぐらい、毎日飲んでいるということ。加えて、過去30日間に少なくとも1回以上60g以上の飲酒(HED:heavy episodic drinking)をした人の割合は、16年の日本の15歳以上人口のうち、男性で37.8%、女性で8.9%を占めている。未成年者がこのような飲み方をするとさまざまな問題が起きてくるため、WHOではこの数値を非常に重要な飲酒の指標として取り上げている」と説明した。
厚労省の科研報告書でも中高生の飲酒に関する実態調査をしており、1996年と2017年を比較すると大きく減っているものの、例えば17年は男子高校生の30.3%、女子高校生の28.5%で飲酒経験がある。そのうち、男子の月1回の飲酒でも7.7%、同様に女子も6.3%もいることが分かっており、なかなか0%にはなっていないのが現状だ。
「アルコール関連問題の広がりは非常に大きく、出生前や乳幼児期から親の影響による胎児性アルコール症候群などがあるし、青年期・成年期以降には本人の問題が加わってきて、臓器障害や精神・神経障害、暴力や飲酒運転をはじめとする家庭・社会的問題なども出てくる。このような問題が一人の人間に集積し、生活あるいは健康問題にいろいろな支障が出てくる状況をアルコール依存症と呼ぶ。多量の飲酒を続けることで脳に障害が起き、自分の意思ではお酒の飲み方をコントロールできなくなってしまっている病気だ」(樋口院長)。
ここで問題となるのが、いわゆる「アルコール依存症の治療ギャップ(治療が必要な人のうち治療を受けていない人の割合)」。厚労省の13年の調査によると、国内では生涯のどこかでアルコール依存症が強く疑われる人が約107万人いるとされているが、そのうち治療を受けている患者数は約5万人と報告されている。04年のWHOの論文でも、アルコール使用障害の治療ギャップは92%と高く、統合失調症(18%)や双極性障害(40%)、パニック障害(47%)等を大きく上回っている。
ただし、樋口院長による14年の飲酒実態調査報告書では、生涯のどこかでアルコール依存症が疑われる人のうち、調査前の1年間でアルコール依存症の治療を受けた人は13.6%だが、他の病気で何らかの医療機関を受診した人は84.1%にも上る。そのため、樋口院長は「どこかの医療機関で別の病気の治療を受けた人が紹介されて、アルコール依存症の治療の場に現れてくれれば、状況はかなり良くなるのではないか」と説明。そのための取り組みとして、保健所と医療機関、もしくは総合病院とアルコール依存症の治療機関などにおける「医療連携」等を紹介した。
そのような取り組みの一環として、樋口院長も編集に携わり、新診断治療ガイドラインを18年に作成。このガイドラインではアルコール依存症の早期診断・治療に焦点を置き、専門医だけではなく、プライマリーケアや内科の医者、研修医などが実際の医療現場でどのように対応していくかを具体的に説明している。さらに、アルコール依存症の治療目標に関する推奨事項として、「飲酒量低減」を導入。「これまで、日本では『断酒の継続』がアルコール依存症の唯一の治療目標とされてきた。しかし、近年は重症ではない患者には飲酒量低減が適応できると示唆されており、減酒治療は治療ギャップを埋める効果があると考えられている。私が勤務している久里浜医療センターでも減酒外来を始めたところ、以前はお見えにならなかったような患者が来られている」(樋口院長)。
講演の最後には、14年施行のアルコール健康障害対策基本法に関して言及した。同法は「アルコール健康障害対策を総合的かつ計画的に推進して、アルコール健康障害の発生・進行および再発の防止を図り、併せてアルコール健康障害を有する者等に対する支援の充実を図り、もって国民の健康を保護するとともに、安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与すること」を目的としている。発生・進行・再発の各段階に応じた防止対策を適切に実施するという基本理念の下、10項目の基本的施策を制定。加えて、重点課題として「飲酒に伴うリスクに関する知識の普及を徹底し、将来にわたるアルコール健康障害の発生を予防」と「アルコール健康障害に関する予防、相談から治療、回復支援に至る切れ目のない支援体制の整備」を掲げている。
また、同法は国の推進計画として施行から5年後の見直しが義務付けられており、本年中には第二期計画がまとまる予定。樋口院長は「第一期の重点課題は、数値目標が未達の項目もある。その現状を踏まえて、第二期では新たな重点課題の案として、『国民に分かりやすい飲酒ガイドラインを作成して活用周知を図る』、『アルコール依存症に対する国民の適切な認識の向上』、『SBIRTSの推進』を挙げている。SBIRTS(Screening、Brief Intervention、Referral to Treatment、Self-help group)とは、アルコール健康障害の早期発見から回復支援まで、一般病棟でのスクリーニングや専門医療機関および自助グループへの紹介など、切れ目のない支援を行うこと。治療ギャップが大幅に下がることが期待できる」とした。
■セミナー便り
2. BS「促進施策や阻害要因改善に取り組む時期」
-日本バイオシミラー協議会:南部静洋会長-
日本バイオシミラー協議会の南部静洋会長は10月14日に同会が主催した第6回バイオシミラーフォーラムで「第1回から第6回まで進める中で、認知度、それから普及は進んできている。これから先は、促進に向けた施策もしくは阻害要因の改善という時期に来ているのではないか」との認識を示した。20年6月現在、日本で承認されているバイオシミラーは14成分34品目。厚労省の19年9月の薬価調査によると、バイオシミラーの普及状況(金額ベース)は約400億円(金額シェア19.5%)、BS置き換えによる医療費適正効果(年間推計)は約226億円となっている。
シンポジウムでは南部会長と神奈川県立保健福祉大学の坂巻弘之教授を司会に、BS使用促進に向けた施策について話し合われた。
日本薬剤師会の川上純一副会長は「企業の方々、また、病院でも医薬品に係る薬剤部門の我々が説明をしっかり行う責任はあるが、一方では、制度が大きなドライバーになるということもある」と指摘。その上で「特に点滴静注製剤の使用に関しては、おそらくインフリキシマブ製剤等がターゲットになると思うが、私が勤める病院でもものすごく苦労しながら導入を図っている。ただ、これは本当に現場の関係者あるいは診療科の医師の先生方の理解等、それによって着々、年々進んでいるのが実態だ。これがどの病院でも同じように行われているわけではきっとないので、その点をご支援いただければ良いのかなと思う」と語った。
日本医師会の宮川政昭常任理事はバイオシミラー使用にあたって「どのように食わず嫌いをなくすか。病院、病院の医師、病院薬剤師の働きがものすごく重要になってくる。そこを核にして地域の医師会、医師、地域の薬局、薬剤師にどのようにうまく波及させるか」と指摘。バイオシミラーに関する品質や安全性、安定供給に関する安心感や信頼感について、地域での共通認識づくりを進めることが重要だとした。
厚労省の林俊宏経済課長は「ここ3年間は、そもそもバイオあるいはバイオシミラーとは何かという理解が一般国民や医療従事者の間でも十分とは言えない状況だということが分かったので、それに対する取り組みをしてきている」とした上で「その先をどう進めていくのかということについてはいろいろと悩ましいと思っている」と語った。
林課長はバイオシミラーだけでなくバイオ医薬品全体の振興が産業政策上の大きな課題になっているとした他、バイオシミラーに関しては「後発品という側面もあり、医療経済、医療費、持続可能性という観点で引き続き、切り替えが必要になってくると考えている。8割くらいの後発品が占める世界の中でバランスのいい市場割合をつくっていくことも課題になっている」とした。加えて、「品質、安全性もそうだが、安定的に供給されるのかという心配が最後、切り替えなりを決める際に懸念として出てきている。後発品だけでなく先発品もそうだが、安定確保が大きな課題になってきていると感じていて、その軸でも取り組みを進めないといけないと考えている。その辺りを組み合わせて、今後の産業全体の施策や医薬品の行政にあたって取り組む必要がある」と話した。
■セミナー便り
3. 33%の保護者が予防接種を延期
-すがやこどもクリニック:菅谷明則院長-
NPO法人「VPDを知って、子どもを守ろうの会」理事長を務めるすがやこどもクリニックの菅谷明則院長は10月15日、KMバイオロジクスとMeiji Seikaファルマが主催したメディアセミナーで、同会が実施した新型コロナウイルス感染症(COVID-19)と予防接種に関する調査の結果を報告した。保護者へのアンケートで、保護者の33%が外出自粛中に予定していた予防接種を延期したことが分かった。
延期の理由は「COVID-19に感染するのが怖かった」「外出自粛」が多く、菅谷院長は「小児のCOVID-19のリスクに関する正確な情報を保護者と共有し過度の不安を取り除くことが必要と考えられる」と指摘した。VPDとはワクチンで防げる病気。B型肝炎、ロタウイルス、ヒブ、小児用肺炎球菌の定期接種などが行われている。
同会は保護者を対象にした「新型コロナ感染症と予防接種に関するアンケート」を実施した。実施日は5月20日~6月9日、ウェブ形式で行い、回答数は533人。その結果、外出自粛中に予定していた予防接種に関して「接種した」が67%、「接種時期を延期したが接種した」が17%、「接種時期を延期したがまだ接種していない」が16%だった。保護者が予防接種を延期した理由(回答数182人)は「感染が怖かった」が68%、「外出自粛していた(緊急事態宣言後)」が49%、「接種が遅れても問題ないと思った」が43%、「医療機関に負担をかけたくなかった」が39%、「外出自粛していた(緊急事態宣言前)」が37%だった。
菅谷院長は結果に関して「COVID-19のリスクとVPDのリスクを比較して、COVID-19の流行期間中に予防接種のために医療機関を受診するリスクが高いと保護者が判断したためであるということが確認できた」と述べ、小児のCOVID-19に関する正確な情報を保護者と共有する必要があるとした。
菅谷院長は、厚労省の新型コロナウイルス感染症の国内発生動向の年齢階級別陽性者数(10月7日18時時点)において10歳未満が2112例(全体に占める割合2.5%)であることや、10月13日に開催された新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードで示された国内小児COVID-19症例の疫学(日本小児科学会データベースを用いた国内発症小児COVID-19症例の臨床経過に関する検討)などから「日本では小児の報告例、重症例ともに少ない。現在まで死亡例はいない」と解説。「COVID-19の流行中でも延期せずに予防接種を行うことが重要だ」と語った。