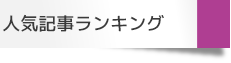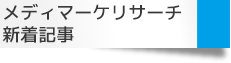■セミナー便り
1.国内医薬品市場、21年に向けて「ほぼ横バイ」
-IMSジャパン:馬場大輔取締役-
IMSジャパンの馬場大輔取締役バイスプレジデントは9月20日、同社主催のメディアセミナーで国内外の医薬品市場について解説し、21年の国内市場はほぼ横バイの10兆円にとどまることを示した。IMSによると21年の世界薬剤市場は1兆5000億ドルに達し、人口増加および発展途上国で薬剤市場が拡大するため16年からの年平均成長率は4~7%になると予測されている。一方、国内市場は21年に900~940億ドルであり、16年からの年平均成長率は-1~-2%と予想されている。米国で6~9%、EU5カ国で1~4%、中国で5~8%、韓国で3~6%の成長が見込まれる中、日本の成長率は世界で最も低い。国内市場の伸び率について馬場取締役は「高齢化により医療費は伸びていくが、人口減少に入っていくので、その部分が強く出ていると思う。各国の政策について深く入れ込んだというよりも、基本的に人口的なものだと考えている」と述べた。
メディアセミナーでは市場を牽引する抗がん剤および生物学的製剤について話が続いた。IMSの先進国8カ国と医薬品新興国6カ国(米国、EU5、日本、カナダ、中国、ブラジル、ロシア、インド、トルコ、メキシコ)の主要な治療領域の支出および成長の予測によると、21年の支出の上位3位は、がん、糖尿病、自己免疫疾患となっている。
がんの21年の支出は1200~1350億ドルで、16年からの年平均成長率は6~12%と見込まれる。糖尿病の支出は950~1100億ドルで、年率8~11%で成長。自己免疫疾患は750~900億ドルで、年率11~14%で成長するという。
がん領域に限ると、IMSの推計で全世界のがん治療費用は16年から年率6~9%で成長し、21年には1500~1800億ドルになると予想されている。国内のがん治療費用は世界と同様10%弱の成長を予想し21年には150~180億ドルになるという。伸びの要因について馬場取締役は「基本的には新しい治療が出てくるので、それにより患者の生存期間が長くなって、治療の期間も長くなる。結果として医療費を押し上げることを想定している。バイオシミラーが出てきて、多少のオフセットはこれでもされている」とした。なお、国内のがん罹患者数(肺、大腸、胃、前立腺、乳房、肝臓)は年率3.3%増と推計されている。
生物学的製剤では3大生物学的製剤市場(自己免疫疾患、糖尿病、がん)の売上げは1100億ドルあり、全体の2分の1を占めるが、馬場取締役は第2相以降にある開発品目を見ると生物学的製剤がほぼ出ていない市場の薬剤であると説明。「これまでリウマチ、IBD(炎症性腸疾患)、乾癬が主戦場であったが、喘息、脂質異常症、アレルギーなど新たな市場に生物学的製剤が出てくる」と語った。前臨床のパイプラインでは、品目数の上位からアルツハイマー(42品目)、喘息(36品目)、HIV(31品目)、アレルギー(27品目)、パーキンソン病(25品目)、エボラ(21品目)、痛み(14品目)、心不全(14品目)などがあると紹介。生物学的製剤がほぼ出ていない市場に参入する場合の問題点としては「既存薬より薬価が高くなり、コストが増加する。特に患者数が多い市場では影響が大きい。また、プライマリーケアの医師および患者が薬剤に慣れていないため浸透に時間を要する」ことを挙げた。
セミナーで馬場取締役はバイオシミラー(BS)についても補足し「BSの時代が到来しつつあるというところでレミケード(インフリキシマブ)でBSが出てきたが、我々が想定していたよりもなかなか浸透していない部分もある」と語る。国内のBS浸透率(BS÷(先発品+BS)、数量ベース)では、腎性貧血治療薬エポエチンBSがおよそ90%、好中球減少症治療薬フィルグラスチムBSがおよそ70%、糖尿病治療薬インスリングラルギンBSがおよそ50%と浸透している一方、関節リウマチ治療薬インフリキシマブBSやヒト成長ホルモン剤ソマトロピンBSは一けた台で浸透が進んでいない。馬場取締役は「日本のBSの浸透度は物によって全然違う。DPCの中に入っている、急性期で切り替えやすい、患者さんの負担が減る、そういう何かしらの見えるものがあると進んでいるのかもしれない」と語った。
■セミナー便り
2.「見える化」で良質な血糖コントロールに寄与
-東京慈恵会医科大学:西村理明准教授-
アボットはフラッシュグルコースモニタリングシステム(FGM)「フリースタイルリブレ」が9月1日からインスリン治療糖尿病患者を対象に保険適用となったことを受けて、9月22日に記者説明会を開催し、東京慈恵会医科大学の西村理明准教授が講演した。西村准教授はフリースタイルリブレについて「患者および医療従事者の負担を軽減しながらも、豊富な血糖関連データを容易に見える化してくれる」とした上で「この機器により、良質な血糖コントロールの達成を成し遂げる患者が増加し、糖尿病診療にパラダイムシフトをもたらすのではないか」と期待を述べた。
フリースタイルリブレは小型センサーと手のひらサイズのリーダーからなり、センサーを上腕の後ろ側に装着し、そのセンサーをリーダーでスキャンして、間質液中グルコース濃度を測定し記録する。センサーは2週間の使い捨てで、装着している間は何度でも測定することができる。糖尿病患者においては、高血糖や低血糖を避けて変動幅を狭めることが、患者の合併症予防や安全確保に必要とされており、現在は主に指先穿刺の血糖自己測定(SMBG)が行われている。フリースタイルリブレの位置付けは、日本糖尿病学会が7月12日に公表したフリースタイルリブレに関する見解によると「SMBGを代替するのではなく補うという位置付けから、FGMは現時点ではSMBGの回数を減らすためのものではなく、血糖自己測定を月に20回以上行うことを最低限の前提とする」とされている。フリースタイルリブレの添付文書でも本品から得られた間質液中グルコース濃度に関する情報は、自己血糖値測定間の血糖値トレンドを推定し、自己血糖値測定による糖尿病の血糖値管理を補助することを目的とするとある。
現時点ではSMBGにとって代わるものではないが、従来のSMBGが測定時点での血糖値の把握にとどまっていたのに対し、フリースタイルリブレは間質液中グルコース濃度を何回でも測定できトレンドを把握しやすくなっている。西村准教授はインスリンを使い始めた41歳の1型糖尿病患者の事例を挙げて「本人と朝の血糖値だけを見るとこちらのインスリン(インスリングラルギンU300)のほうが良かったが、全体で見ると低血糖や高血糖が起こっている。一方、こちらのインスリン(インスリンデグルデク)は低血糖も高血糖もない。本人の感覚と朝の血糖値だけで決めていたのが、全体を見て低血糖がないか高血糖がないか完全な個人個人に合わせたテーラーメードの医療が科学的にできる時代をもたらしてくれる。そういう機械が出てきた」と評価した。
西村准教授によると、国内の糖尿病患者は12年で950万人おり、そのうちインスリン使用患者は130万人いる。糖尿病の医療費は合併症のない場合で年間1人当たり平均33万円、合併症がある場合で年間1人当たり平均55万円といわれている。
特に医療費がかかる合併症は糖尿病腎症、糖尿病神経障害、大血管障害で、糖尿病腎症による新規透析導入患者は年間1万7190人、糖尿病神経障害に起因する足病変で下肢切断に至る患者は年間3000人以上、大血管障害では糖尿病患者は健常人に比べ心血管発症リスクは3~5倍、脳卒中では発症リスクが2倍という。
こうした合併症を予防するためにも、西村准教授は「私たちが考える理想的なコントロールは血糖レベルの改善、低血糖の回避、血糖変動の最小化である。平均血糖変動幅(MAGE)が大きいほど心血管イベントが多いという報告もあるので、MAGEは狭くしたほうがいいことが分かっている。また重症の低血糖を駅の階段で起こせば転んで首の骨を折ってしまうこともあるので、重症の低血糖を起こさないことも非常に重要」と強調。
血糖値情報の日内変動を可視化してより良い療養指導、治療、血糖管理が期待されるほか、1型糖尿病患者対象のIMPACT試験および2型糖尿病患者対象のREPLACE試験ではフリースタイルリブレを用いた群は従来の血糖自己測定に比べて低血糖発現時間が短縮したとした。
西村准教授は今後のデバイスの進化にも言及。「従来のSMBGに取って代われるのであれば、フリースタイルリブレのほうがいいと思う。結局、SMBGは点、点、点でその間の傾向が分からないので、私の研究者としての考えは真実をすべて見える化するというのがやはり糖尿病の治療に有用だと思うので、今後、リブレの精度がSMBGと同じかそれを超えるくらいになっていくと私は期待しているが、そうであれば基本的にはSMBGにだんだん切り替わってくるものになるんじゃないかと思う」と話した。
■セミナー便り
3.乳児血管腫にβ遮断薬「偶然の発見」
-仏ボルドー大:クリスティーヌ・レオテ・ラブレーズ医師-
マルホは9月29日、乳幼児に見られる赤あざの一種、「乳児血管腫」の疾患啓発を目的としたプレスセミナーを都内で開いた。海外からの演者を含めて3人の医師が講演し、従来の対処法である経過観察や適応外薬投与、レーザー治療などに、β遮断薬プロプラノロール(ヘマンジオルシロップ)が初めての乳児血管腫治療薬として加わり、治療戦略が変化していることを紹介した。
斗南病院血管腫・脈管奇形センター長・形成外科長の佐々木了氏によると、乳児血管腫は血管内皮細胞の腫瘍性増殖による良性腫瘍で、「いちご状血管腫」とも言われる。日本では有症率1.7%との報告がある。体のどこにでも発症するが、頭頸部が多い。一般的には、生後数日から現れ、5.5~7.5週で急速に増大し、1年までにピークに達する(増殖期)。その後、退縮期、消失期を経て、多くは小学校入学までに徐々に自然退縮する。
とはいえ、未治療の場合は約25~70%に瘢痕などの後遺症が残り、中には手術を必要とすることがある。また、血管腫の部位や大きさによっては重要臓器や感覚器に悪影響を及ぼす。そのため、現在あるいは将来の整容的・機能的問題に応じて治療が必要とされている。具体的にはステロイド投与、レーザー治療、外科的切除などだが、それぞれに一長一短があるという。
プロプラノロールの有効性は、仏ボルドー大学病院皮膚科のクリスティーヌ・レオテ・ラブレーズ医師が2008年に初めて報告した。セミナーでラブレーズ氏は「乳児血管腫へのステロイド投与で心臓に副作用を来したため、循環器科医の指示でプロプラノロールを投与したところ、血管腫が改善し、ステロイド中止後も増大しなかった。偶然の発見だった」と1例目の経過を振り返った。その2カ月後にも、ステロイド使用にもかかわらず悪化していた別の乳児血管腫患児に投与して改善が得られた。これらが契機となって仏ピエールファーブルデルマトロジー社が乳児用の液剤を開発し、14年に欧米で承認を取得した。国内ではマルホが同社から導入し、16年に承認された。国内臨床試験では、長径1.5㎝以上の増殖期の乳児血管腫(生後35~150日)32例に24週間投与したところ、約80%が治癒またはほぼ治癒した。
この試験に携わった神奈川県立こども医療センター皮膚科部長の馬場直子氏は「正確に診断し、適応となる症例を慎重に選んだ上で、早期に治療を開始することが重要だ」と指摘。そのためにも、新たな治療の登場やそれによる治療戦略の変化について産科医や小児科医への普及・啓発が必要だとの見解を示した。また、重大な副作用として低血圧、低血糖などが報告されているため、小児科医との連携が必要だと述べた。実際に与薬する保護者に対しても、用法・用量の厳守や飲み忘れた時の対応などを「口が酸っぱくなるほど言っている」とした。投与期間については6カ月を基準とし、症例によっては適宜延長する場合もあるとした。
■学会レポート
潰瘍性大腸炎の体外診断薬登場で患者負担は軽減
-大阪大学大学院医学系研究科:飯島英樹准教授-
第54回日本消化器免疫学会総会が9月28、29日の両日、都内で開催された。同学会と持田製薬による共催セミナーでは、大阪大学大学院医学系研究科消化器内科学の飯島英樹准教授が「炎症性腸疾患の診断、治療のためのバイオマーカーの現況」をテーマに講演。今年6月1日に潰瘍性大腸炎の体外診断用医薬品として国内で初めて保険適用となった「カルプロテクチン モチダ」(承認販売元三洋化成工業/販売元 持田製薬)の有用性や、臨床上の活用方法などについて語った。
潰瘍性大腸炎は腸管に慢性・再発性の炎症を引き起こす難病。患者数は増加の一途をたどっており約17万人(2014年度)いるとされる。この病気は、粘膜治癒をもたらすことが病勢のコントロールと再燃予防に重要とされているが、粘膜病変の活動性を反映する有用なバイオマーカーがないことが、診療における大きな課題とされていた。
そのような中、便中に含まれるカルプロテクチンというタンパク質の濃度を測定することで腸管内の炎症の程度を数値で表すことのできる試薬キット「カルプロテクチン モチダ」が6月20日に発売となった。潰瘍性大腸炎における腸管の炎症に特異的なバイオマーカーであり、便で簡単に測定できるのが特徴だ。
従来はCRPや血沈などの血液マーカーが使用されていたが、腸管以外の炎症でも値が上昇するため、正確な病態把握が困難だった。そのため、診断や経過観察のためには、都度、内視鏡検査が必須となっており、ゴールドスタンダードとなっている。しかし、体内にスコープを挿入することから侵襲性が高く、高コストなどの課題もあり、飯島氏は「新たなバイオマーカーの登場が望まれていた」と強調した。
カルプロテクチンは腸管炎症部位において好中球から分泌されるカルシウム結合タンパク。炎症を起こしている腸上皮に対して、細菌や真菌類の侵入を防ぐべく誘導された好中球が、腸管腔内にカルプロテクチンを放出する。糞便中のカルプロテクチン濃度は、潰瘍性大腸炎の重症度を示す「DAIスコア」との相関性が認められているという。そのため、糞便中のカルプロテクチンの濃度は腸の炎症の程度を十分に反映しており、潰瘍性大腸炎に対する感度・特異度の高い炎症性マーカーと考えられている。また、タンパク分解に抵抗性を示すため、室温で分解されにくく、4℃で48時間、20℃で24時間安定なため、「患者が室温で持参しても分解されずに保存できるメリットがある」(飯島氏)という。
同氏はその有用性について「カルプロテクチンの濃度は潰瘍性大腸炎における内視鏡的活動性と相関することが非常に多くの研究で報告されており、疾患活動性を検出するのに感度・特異性の高いバイオマーカーであり、粘膜の状態を反映する」と評価。その一方で、検査できる頻度が3カ月に1回とされ、症状のある人に何回も測定できないことや、測定に時間がかかること(検査設備が整備されている病院では測定時間は2~3時間)、また患者に便を持参してもらう必要があるため診察の場で症状を訴えている人にすぐに測定ができない、等の課題もあるとした。
対象患者に関して、飯島氏は本誌の取材に「恐らく、寛解期の患者に定期的にカルプロテクチンの値を測り、数値が上がってくれば炎症があるのではないかという予測に使われ、再燃予測のマーカーになる。すると内視鏡検査を行うきっかけになるとともに、早期に治療を開始することができる。また、IBS(過敏性腸症候群)様の症状があり、(鑑別診断のため)従来なら内視鏡検査を行っていたような人にカルプロテクチン値を調べることで、内視鏡検査を行わずに済み、患者の身体的、経済的負担を軽減できる」と期待を示した。