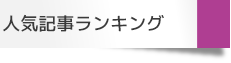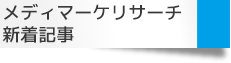■行政トピックス
1.中医協薬価専門部会 2月8日
毎年改定で厚労省、「本調査と中間年調査は別物」
中医協薬価専門部会は2月8日、昨年末にまとまった政府の「薬価制度抜本改革基本方針」を踏まえ、個別課題の議論を継続した。この日は、前回までの「最大年4回の再算定」「外国平均価格調整」に続き、「(毎年改定のうち)中間年の薬価調査」をテーマに取り上げた。厚労省が「通常の調査と中間年の調査は別に考えられるのではないか」(大西友弘経済課長)との見解を示したのに対し、診療側は同調。支払側は「一番重要なのは、通常改定の本調査と中間年の調査の考え方にあまり差があってはならないこと」(幸野庄司健保連理事)と反発した。
昨年、オプジーボ緊急薬価引き下げの中医協決定に続き、突如、経済財政諮問会議で俎上に載った「薬価の毎年改定」。塩崎厚労相、菅官房長官、麻生財務相ら4閣僚で合意した「抜本改革基本方針」には、「市場実勢価格を適時に薬価に反映して国民負担を抑制するため、全品を対象に、毎年薬価調査を行い、その結果に基づき薬価改定を行う。そのため、現在2年に1回行われている薬価調査に加え、その間の年においても、大手事業者等を対象に調査を行い、薬価乖離の大きな品目について薬価改定を行う」ことが盛り込まれた。そして具体的なルールづくりは中医協に引き継がれた。
この日の中医協薬価専門部会で、厚労省は「中間年の薬価改定を行うことになっており、価格乖離の大きな品目の薬価改定を行うための調査として、どのような調査が適当か。その際、調査実施に対象者の理解が得られやすいよう、可能な限り簡易な調査をするなど負担軽減を図るべきではないか」と問題提起した。
吉森俊和委員(協会けんぽ理事)は「まず現行の2年に1回の薬価調査における課題を明らかにした上で、それをクリアできるような手法を検討し、中間年の調査に特別な配慮が必要か否かを検討していくのが筋かと思う」と、問題提起の仕方に疑問を呈した。
これに対し大西課長は「通常の調査と中間年の調査は、同じものをやる前提で議論するのではなく、むしろ違うものを調査することが前提となっている。なぜなら中間年は価格乖離の大きな品目について薬価改定を行うこととなっている」と指摘した。
診療側は「本来下がる可能性のあるものに絞ってきちんと調査して、適切に下げていくことが、財政に一番大きな影響があると思う」(松原謙二日医副会長)、「乖離が大きい品目は想定できると思う。想定の下に中間年の調査は限定的な手法で、卸売販売業者、医療機関、薬局に極力負担の少ない簡便な方法でやるべきではないか」(中川俊男日医副会長)と同調。
一方、幸野委員は「調査の考え方は本調査と同じままで、例えば客体6280を4000や3000にするとか、購入サイドの病院を10分の1にするとか、50分の1にするとか、パラメーターを変えるだけで、基本は本調査と同じにするのが筋ではないか」と食い下がった。
■行政トピックス
2.中医協総会 2月8日
外来医療の議論を開始、遠隔診療の評価が課題に
中医協は2月8日の総会で、次回18年度診療報酬改定に向けて外来医療についての議論を開始した。診療報酬上、現行「対面診療の補完」と位置付けられている遠隔診療だが、「診療形態が日々変わってきており、適切なものは保険診療に取り入れていくのが中医協の原則」(迫井正深保険局医療課長)との観点から、その診療報酬上の評価が主要な論点に浮上。一方、引き続き調剤報酬の抑制も主要な論点となりそうで、調剤医療費の伸びに対する風当たりは強いままだ。
前回16年度改定における外来医療(その1)の議論は15年4月にスタート。その際、厚労省は論点として「外来の機能分化・連携を推進する方策や、重複投薬や残薬を減らす方策、主治医機能の強化を含め外来診療の質の向上と効率化を図る方策について、14年度診療報酬改定の答申書付帯意見も踏まえ、さらに検討していくべきではないか」と提案。年末まで3回にわたり外来医療の議論が行われ、外来の機能分化を進めるための「紹介状なしの大病院受診時の定額負担導入」や、「医療機関における減薬の評価」「認知症の主治医機能の評価」などが実現した。
今回、厚労省が提示した論点は「外来医療のニーズの変化や多様性も踏まえ、より質の高い適切な外来医療が提供できるよう、外来患者の特性や病態に応じた評価や、新たなサービス提供の在り方について、どのように考えるか」というもので、やや具体性に欠けるが、遠隔診療を意識したものと読み取れる。
遠隔診療をめぐっては、昨年12月の首相官邸主催「未来投資会議構造改革徹底推進会合」で塩崎恭久厚労相が、「18年度診療報酬改定での対応を検討していく」こと、およびAI(人工知能)について「20年度診療報酬改定において、十分なエビデンスの元に、診療支援に向けたインセンティブ付けの検討を行う」ことを表明していた。
中医協総会では、前々回の「在宅医療」の議論の時と同様、支払側と診療側の意見が対立。幸野庄司委員(健保連理事)は「遠隔診療という言葉自体がなじまない気がする。スマートフォンやテレビ電話といったICT診療と言うべきものは、慎重にではあるが進めていくべき」と持論を語った。これに対し、中川俊男委員(日医副会長)は「スマートフォンで状態を確認すればよいというのは医療の原則に反するため、私どもは一歩も譲れない」と述べ、平行線に終わった。
一方、猪口雄二委員(全日病副会長)は、厚労省が提示した「1人当たり調剤医療費を04年度と14年度で比較すると、すべての年齢で増加している」などの資料を踏まえ、調剤医療費の抑制策として「もう一度院内処方の在り方を評価することによって、院内処方を増やすのも一つの方法ではないか」と提案。
中川委員は、同省が提示した「診療種別に入院・入院外は伸びの多くが高齢化によって説明できるのに対し、調剤については人口構造の変化による影響はその他の要因よりも小さくなっている」との資料を元に、「高額な医薬品の陰に隠れて調剤技術料の伸びの影が薄くなっているが、しっかりと伸び続けている。次期改定に向けて、調剤改定財源のあるべき姿を中医協で議論していくべき」と述べた。
■記者会見
1.「日本の売上高を2倍に」
-サンド:リチャード・フランシスCEO-
サンドは2月8日、「日本は優先的重視市場である」として2022年までに日本法人の売上高を15年の2倍にするとの目標を示した。サンド インターナショナルGmbHのリチャード・フランシス事業部門責任者兼CEOと日本法人のジェイソン・ホフ社長が記者会見して明らかにした。22年までに国内で70成分を上市する計画で、中でも注射用抗がん剤や中枢神経系薬に大きなビジネスチャンスがあると期待感を示した。バイオシミラー(BS)も成長のドライバーになるとした。
足元の国内売上高は数億ドル規模だという。16年は前年比9%増で、今後は年平均11%を超える成長率を目指す。これから上市する70成分が、22年の時点では売上高の40%を占めるとの予測も示した。
業績への貢献を期待する注射用抗がん剤は、同社はグローバルで多くの製品を有しており、高度な製造技術や専門知識を持つことを優位性として挙げた。中枢神経系薬については、今後、国内で主要製品の特許切れが続くことを成長の理由とした。
同社は日本ではソマトロピン(成長ホルモン製剤)とフィルグラスチム(G-CSF製剤)のBSを上市している。昨年11 月にはリツキシマブ(抗CD20抗体薬)の承認申請を済ませた。グローバルでは他のBSもあり、「多くの製品を持ってきたい」との意向を示した。
フランシス氏は日本の市場環境について「政府のジェネリック医薬品使用促進策を追い風ととらえている。簡単ではないが、その困難な市場で成長を達成したい」と意欲を見せた。BSについては、医療システムにインパクトがあると指摘。コストを理由にバイオ製剤の導入をためらっている患者において治療へのアクセスの鍵になると述べた。
M&Aや提携については、「我々はオープンである。グローバルな規模では(M&Aや提携は)ないが、地域や国レベルでメリットが適切であれば、目指すかもしれない」と述べた。
■セミナー便り
1.小児ADHD「もっと心理社会的な支援を」
-愛育相談所:齊藤万比古所長-
児童精神科医で愛育相談所所長の齊藤万比古氏は2月14日、塩野義製薬とシャイアー・ジャパンが共催した注意欠如・多動症(ADHD)に関するプレスセミナーで「ADHDイコール薬という文化が少し走り過ぎているのではないかと医師として懸念している」と指摘。「ガイドラインでも始めに薬ありきという考え方は推奨しないと宣言している」と強調した。ADHDは不注意、衝動性、多動性を主症状とする発達障害の一つで有病率は18歳以下で5%、大人で2.5%といわれている。国内のADHD治療薬はヤンセンファーマのコンサータと日本イーライリリーのストラテラの2剤が発売されており、塩野義およびシャイアー・ジャパンは16年1月27日に小児ADHD治療薬インチュニブの国内製造販売承認申請を行った。併せて塩野義製薬は経営戦略本部内にこどもの未来支援室を設置した。
齊藤氏は薬物治療を行うことで「問題児としてしか扱われてこなかった子が、知的な力もあり、人への優しさもあり、人のことを真剣に考えているということが、周りの人間に見えるようになってくる」と重要性は認めた上で「もっと心理社会的な支援、親御さんへの支援のかかわり、ADHDの特性を踏まえた教育のあり方を開発、普及しなければならない。それにより薬物療法が必要な子どもの数はぐっと減る可能性があるのだと医療従事者の一人として追求していかなければならない」と述べた。
小児ADHDにおいて薬物治療と心理社会的治療は2本柱。薬物治療だけでなく心理社会的治療を行う利点について齊藤氏は「一つは自分が自分を変えていく主人公だと子どもが思えること。親や学校の先生が結局、薬でしかよくならないのねと思わないで、自分たちがここまで支えることができた、でももう少しうまくいくためにちょっとだけ薬の力を借りようという形で、親である自分、教師である自分のかかわりが重要なところを占めていると自己効力感を持つことができる」と語り、「本人、支援者がそういう思いを持って薬物療法を受け入れていくということが本当に大事だ。本人、親、学校の努力でここまで成長した、成長してきたと思えることが治療の本当の目的だと思う」と続けた。
セミナーでは齊藤氏が、塩野義製薬とシャイアー・ジャパンが実施した「注意欠如・多動症(ADHD)の子どもを持つ母親と小学校教師に対する意識・実態調査」の結果を報告。ADHDの子どもを持つ母親283人のうち、医療機関受診後、子どもがADHDと診断された際の気持ちについて、母親の59.7%は「症状の原因がはっきりしてほっとした」と答え、41.7%が「子どもの将来が心配で落ち込んだ」と回答した。
齊藤氏は「私(母親)の責任だとみんな言ってきたけれどそうではないと分かってほっとした、対応が少し見えてきたのでほっとしたのだろう。落ち込むのも正直な気持ちだと思う。この気持ちが、何とかなるんだという希望に変わるために支援はどうあるべきかということを考えていかねばならない」と解説した。
■セミナー便り
2.骨粗鬆症治療「何歳からでも効果ある」
-東京慈恵会医科大学整形外科:斎藤充准教授-
東京慈恵会医科大学整形外科学講座の斎藤充准教授は2月15日、旭化成ファーマ主催のメディアフォーラム「いつから始める?いつまで続ける?骨粗鬆症治療」で講演。斎藤准教授によると、骨はひび割れや老朽化している部分を破骨細胞が削り取り骨芽細胞が修繕する形で新陳代謝を活発に繰り返しており、骨は年間40%入れ替わる。この性質から「いつから治療を始めても骨折防止効果は1年間でどのような薬剤でも骨折リスクを半分に下げることができる。50歳、60歳、80歳からでも、骨が代謝している以上、薬、運動、食事療法が効く臓器だ」と述べた。治療を終える時期については「代謝しているので、やめれば戻ってしまう。基本的に骨を良い状態に保ちつつ質を悪くしないようなタイプの薬を組み合わせて一生続けることが本来必要だ」とした上で「漠然と同じ薬を使うのではなく、その患者の骨の状態を見ながら薬剤を使い分けるほうがいい」とした。
講演では骨強度は骨密度だけでなく骨質(コラーゲン架橋)の影響を受けることを説明。血中ホモシステイン測定や血/尿ペントシジン測定といった骨質マーカーを利用し、低骨密度型、骨質劣化型、骨質劣化+低骨密度型に分けて治療を行う必要性を説いた。
旭化成ファーマは16年11月、年1回投与のビスホスホネート製剤リクラスト(一般名ゾレドロン酸)を発売。『骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン2015年版』の骨粗鬆症治療薬の有効性評価一覧には国内発売前だったので入っていないが、斎藤准教授は「海外で大腿骨近位部骨折の防止効果が明らかな薬剤なので、次回改定の時には(骨密度、椎体骨折、非椎体骨折、大腿骨近位部骨折の項目で)全部Aになる」と語った。
■記者会見
1.埼玉ALC「神奈川と同人数で運営」
-メディセオ:長福恭弘社長-
メディセオの長福恭弘社長は2月3日、次世代型ALC(エリア・ロジスティクス・センター)「埼玉ALC」の竣工記者会見で「庫内で働く方は、売上げがここの3分の1の神奈川ALCと同人数で運営できると考えている」と生産性の高さを強調した。生産性の向上を目指す背景には、後発品使用促進政策の中、売上げは伸びないが物量は増える状況の下、「物量が増えてもコストは上がらないという形で供給しないと、医薬品卸として安定的継続的に企業の経営を営むことができない」(長福社長)といった事情がある。
生産性向上の施策としてメディセオは全国にALC-FLC(フロア・ロジスティクス・センター)体制を構築。09年の神奈川ALCを皮切りに南大阪、名古屋、札幌、東北、南東京とALCを稼働し、16年には初の次世代型ALCとして福岡ALCを稼働。今回、2つ目の次世代型である埼玉ALCの竣工に至った。
埼玉ALCには次世代型の特長が多く見られる。1つは医薬品、医療材料、医療機器、臨床検査試薬をフルラインで扱っていること。医療材料や臨床検査試薬は膨大な種類があるのですべてとはいかないが、地域の需要に合わせて在庫し、埼玉ALCでは医薬品、医療材料、医療機器、臨床検査試薬など3万SKU以上の商品を取り揃えている。
もう1つは新型自動倉庫AUPUS(オーパス)。AUPUSとはピース自動倉庫、ユニシャトル(高速自動入出庫装置)、クロスベルトソーター(高速自動仕分け)からなる全体のシステムのこと。神奈川ALCでは主にハイテクカート(SPIEC)によるピッキングシステムにより従業員がカートを押しながら作業していた。埼玉ALC では一部SPIECによる作業は残っているが、主にAUPUSにより商品がクロスベルトソーターに載り従業員の下に運ばれてくる。従業員が動く作業が減り、省人化が実現した。
積み込みの際にはRFIDタグ付きオリコン(箱)と読み取りゲートシステムを導入。すべてのオリコンにICタグを装着し、ゲート通過時にボックスの数量や行き先の一括読み取りができるようになった。複数個のオリコンを一括で処理できるようになったため、リードタイムの短縮につながる。ALCからFLCへの配送に便利なほか、物量が多い大病院への配送にも生かすことができる。
埼玉ALC独自の取り組みとしては医療機器の保守点検・修理サービスのMMコーポレーションが物流センター内に入った。
また、会見で長福社長は得意先に対し個口スキャン検品や棚ロケーション順納品を提案。「医薬品卸共通で公正取引委員会の中で労務提供と認定されたのが医薬品の棚入れだ。そうしたサービスができなくなってきているので、検品、棚入れの効率化はお得意先に求められている。相当ニーズが広がるのではないか」と見通した。
■セミナー便り
1.イラリス「劇的にQOLは良くなっている」
-京都大学発達小児科学:平家俊男教授-
京都大学大学院医学研究科発生発達医学講座発達小児科学の平家俊男教授は2月20日、ノバルティスファーマ主催のメディアセミナーで同社の抗IL-1β抗体イラリスについて「劇的にQOLは良くなっている」と手応えを語った。イラリスは昨年12月に「既存治療で効果不十分な家族性地中海熱」、「TNF受容体関連周期性症候群」、「高IgD症候群(メバロン酸キナーゼ欠損症)」の治療薬として効能追加の承認を取得した。
どの疾患も周期性発熱症候群に分類される自己炎症性疾患(自然免疫の遺伝子変異により病原体非存在下でも炎症が惹起され自己の組織が傷害される)。周期熱で発症することが多く、皮疹、関節痛、消化器症状を伴い、患者のQOLは著しく低下する。家族性地中海熱の国内症例数は500 人、TNF受容体関連周期性症候群は20家系、高IgD症候群は8家系10人。家族性地中海熱の治療薬にはコルヒチンがあるが、患者の約10%が抵抗性または不耐容であった。TNF受容体関連周期性症候群と高IgD症候群は治療薬として承認されているものがなく、非ステロイド系抗炎症剤と副腎皮質ステロイドを使用してきたが、副腎皮質ステロイドによる副作用が問題であった。
講演で平家教授は、「病気や薬の副作用に悩んできたので、イラリスが承認されて心からホッとしている。ずっと効いてくれますようにと不安と祈りにも似た気持ちが少しある」という患者の声を紹介。イラリス以外にも治療選択肢が増えることへの期待を述べ、イラリス自体には「IL-1βが病態と推定される他の疾患に対してもさらなる臨床応用が期待される」と語った。