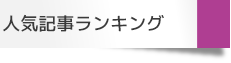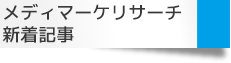■行政トピックス
1.中医協薬価専門部会 4月12日
原価計算方式の正確性向上で議論
中医協薬価専門部会は4月12日、昨年末にまとまった政府の「薬価制度抜本改革基本方針」を踏まえ、個別課題の議論を継続し、この日は「原価計算方式の正確性向上」をテーマに議論した。支払、診療の両側から原価計算方式の係数を改めて検証する必要性が示された。
新薬の薬価算定は、原則として類似薬効比較方式で行われ、比較薬が存在しない場合、原価計算方式が用いられる。オプジーボの収載時薬価も原価計算方式で算定された。
原価計算方式とは、1.原材料費 2.労務費 3.製造経費 4.一般管理販売費 5.営業利益 6.流通経費 7.消費税-を積み上げていく算定方式。一般管理販売費率、営業利益率、流通経費率の各係数は、直近3カ年の平均値を用いており、現在、一般管理販売費率の上限は45.9%、営業利益率は14.6%、流通経費率は7%を用いている。なお、イノベーションの評価として、営業利益率に対して、-50%~+100%の範囲内で補正を行う場合がある。
幸野庄司委員(健保連理事)は、「一般的な企業は営業利益率を2ケタにすることが宿題であり、医薬品産業の営業利益率を見て驚く。一般管理費も同様で、45%程度が上限となっているが、大体の産業を見てみると、10%前半程度と思う」と指摘。その上で「成功確率がかなり低いことは、一般企業でもあることで、医薬品産業だけ特別扱いするのはいかがなものか」と問題視した。
一方、中川俊男委員(日医副会長)は「一般管理販売費率、営業利益率は、医薬品企業の中でも優良企業30社に限定した日本政策投資銀行の産業別財務データハンドブックを使用しており、イノベーションの手当てには十分配慮してきたのではないか」と指摘。「原価計算方式は透明性が低い。こういう流れで算定しているという実態を一度文書で示してほしい」と要望した。
また、厚労省が「原薬の輸入を含めた輸入医薬品については、特に外国で販売されておらず日本で初めて医薬品が上市され、輸入価格の妥当性の評価が困難となる場合があるが、このような場合において、収載後に、外国平均価格調整を適用することについてどう考えるか」と問い掛けたのに対し、松原謙二委員(日医副会長)は「いったん価格を決めても、条件によって速やかに補正していくことをルール化することは賛成」との考えを示した。
■記者会見
1.キイトルーダ上市で「業績、ポジティブに」
-MSD:ウェストハイゼン社長-
MSDは4月4日、年次事業説明会を開催し、2016年の国内売上げは、薬価改定の影響や長期収載品の不振、DPP-4阻害剤市場の競争激化(最主力品のジャヌビアの売上げは6.1%減の724億円、IMS調べ)を要因として、前年比7.8%減の約3120億円となったと発表した。ただ、今年2月15日に悪性黒色腫および非小細胞肺がん(1次/2次治療)治療薬の抗PD-1抗体キイトルーダを発売。17年の業績見通しについてヤニー・ウェストハイゼン社長は「よりポジティブな結果が期待できる」と述べた。
2016年の研究開発活動を振り返り、白沢博満副社長執行役員・グローバル研究開発本部長は「7つの申請と8つの承認を達成し、前例のない素晴らしい年だった」「今年から始まる大きな成長の波に向かう移行期のような年だった」と表明。
その上で、17年の取り組みについて「成長をさらに加速していくために非常に大事な時期。キイトルーダをより広く多くの患者さんに届けていくために注力する。がん領域のため、実臨床の中での安全性をきちんと確保していくことは会社として最優先事項だ」と語った。
白沢副社長によると、キイトルーダの開発は、ホジキンリンパ腫で承認申請中のほか、乳がん、大腸がん、胃がんなど9つのがん種で第3相試験段階にあり、「併用を含めて、これからのがん治療の体系のいろんなところで、きちんとベースとして使えるようにもっていくことが大事」と語った。
米本社(メルク)は2月14日にBACE阻害剤ベルベセスタットについて、軽度および中等度のアルツハイマー型認知症(AD)患者を対象とした第2/3相試験であるEPOCH試験(017試験)の中止を発表したが、軽度症候性前期認知症(Prodromal AD)を対象としたAPECS試験(019試験)は継続している。
白沢副社長は「中止した試験は、すでにADになってしまっている患者を対象としており、結果を出すのに、かなり難易度が高い。もう一方は、現在の診断ではADになっていない人、つまり普通の生活はできるが、ちょっと認知機能が落ちたかなという人で、かつ、きちんと画像診断をして脳にアミロイドβが沈着し始めている人が対象で、より厳格な試験が走っている」と説明した。
2013年6月に同社のガーダシルを含むHPVワクチンの積極的な接種勧奨が差し控えられて以来、4年近く経過したが、ウェストハイゼン社長は「政府に対して積極的勧奨の再開を強く、継続的に要望していく。広く接種を実施している国では、HPV感染率や前がん病変の発症が減少している」と訴えた。
■記者会見
2.21年の国内稼働CMR数は「6000人以上」
-日本CSO協会:清水昇会長-
日本CSO協会の清水昇会長は4月13日、16年度活動報告会で「製薬企業や医療機器メーカーの経営課題が変化していく中、我々はソリューションプロバイダーになる。経営課題を一緒になって解決するため、新しいサービスをつくり出し提供する」と抱負を述べ、結果として21年の国内稼働CMR数が「6000人以上になる」と見通した。16年の国内稼働CMRは3882人(前年比1.2%増)。14年の4148人をピークに減少傾向だが、「製薬企業、医療機器メーカー、色々なヘルスケア関連企業との取引も増えているし、各々で求められるサービスの幅も広がってきている。そのサービスを実際に増やすということ、またそれに向けた人材づくりに一層拍車を掛ける」とした。
これまでCMRはプライマリー領域の製品を診療所に情報提供することが多く、製薬企業の欠員補充や中途採用のリソースとして利用されてきた。今後は「スペシャリティケアの領域が確実に増えてくる。しかも品目数が多く出てくる。実際、我々の各社にもがん領域に対応できるMRがいないかどうかリクエストが増えてきている」と指摘。「外資は抗がん剤の経験が長いので、抗がん剤のMR経験が無くても受け入れる。内資は特定の部位のがんの経験が3年以上という条件を付ける。こうした傾向が見られるが、抗がん剤といえども普及していけば、もっと幅広く人材を受け入れていくようになるのではないか」とし、「必ずしも抗がん剤の経験が無くても、病院経験があるとか、患者ベース、疾患ベースで医師と話ができるMRを育てていけば、もっと広がるだろう。そういうエビデンスをつくりながら、市場の拡大はできると思う」と述べた。
加えて地域包括ケアシステムにもチャンスがあるという。「2020年以降の医療制度がどうなっているか。急性期の病院が減り、居宅在宅のほうに患者が増えてくる方向に向かっている。その時の対応を製薬企業も考えているので、我々がどうサポートできるか」とした上で「実際に地域に密着して患者の動きなど地域をきちんと理解している人間をつくっていけば、製薬企業からそういうチームを使いたいということになってくる」とした。
16年度活動報告では全体のCMRに占めるMSL(メディカルサイエンスリエゾン)の割合が0.4%とMSLの派遣需要もわずかに見られる。こうした点について清水会長は「製薬企業自体、MSLの定義に幅がある。MR寄りの仕事をそう呼んでいたり、外資の中では米国や欧州の本国の基準に合わせて日本でも完全にサイエンス寄りの仕事をしていたり。日本の中でMSLが何をやってどういう付加価値を付けていくかというのはまだ迷っている段階なのかなと思う。その中で我々は海外の事例を学び、製薬企業の方がご存じではないような情報を提供しながら、日本に一番適した取り組みを一緒にやっていきたい」と話した。
■セミナー便り
1.乾癬治療の生物製剤、幅広い効果ではヒュミラに分
-東大大学院皮膚科学:佐藤伸一教授-
乾癬治療用の生物学的製剤(抗インターロイキン(IL)-17抗体)3製品が最近相次ぎ発売されたが、アッヴィ日本法人は4月10日、「乾癬メディアセミナー」を開催し、東大大学院医学系研究科皮膚科学の佐藤伸一教授が、乾癬の適応も持つ抗TNF-α抗体ヒュミラを使用するメリットを私見を交えて解説。「乾癬の皮疹を改善するだけでなく、関節炎や併存疾患等にも効果を発揮する」と強調した。
ヒュミラは関節リウマチ治療薬として2008年4月に発売。10年1月には2番目の適応として乾癬の追加承認を取得した。最近では16年にぶどう膜炎の適応追加承認を取得し、現在9つの適応を持っている。同じ抗TNF-α抗体では、レミケードが乾癬の適応を持っているほか、11年3月には抗IL-12/23p40抗体ステラーラが乾癬治療薬として発売された。またこの1、2年は、IL-17阻害剤の発売ラッシュとなっており、15年2月には抗IL-17A抗体コセンティクス、16年9月には抗IL-17RA抗体ルミセフ、同11月には抗IL-17A抗体トルツが発売された。
佐藤教授によると、乾癬の発症や悪化に関係していることが分かっているサイトカインは、TNF-α、IL-23、IL-17の3つ。TNF-αがIL-23を誘導して、さらにIL-17を誘導して乾癬の皮疹に至るというように、TNF-αは最上流に位置する。TNF-αは、乾癬だけでなく、さまざまな炎症性疾患と関連している一方、下流にあるIL-17は乾癬に特異的という。このため、佐藤教授は抗TNF-α抗体の優越性として「乾癬としばしば合併する炎症性腸疾患やぶどう膜炎を一緒に治療できる。発症させなくすることができる」ことを挙げた。安全性に関しては、下流にある抗IL-17抗体がより限定的な副作用なのに対し、上流の抗TNF-α抗体は、より全身的な副作用がある点でリスクが高いが、「発売されて非常に長期間たっているので、どのように対応すればいいか十分分かっている」と述べた。
一方、乾癬の皮疹においては、TNF-αが大量に産生しており、血中に漏れ出て、血液を介して全身の臓器に回り、併存疾患(心筋梗塞、脳卒中、糖尿病、高脂血症、高血圧、動脈硬化、脂肪肝、高尿酸血症など)を起こすことが知られているという。
その上で、佐藤教授は乾癬患者8845人を対象とした、心血管系イベント(心筋梗塞など)に対する抗TNF-α抗体の影響を調べた、後ろ向きコホート研究の結果を解説。それによると、「全身療法なし群」では、心血管系イベントの発生率は6.73%、「経口全身療法群(ネオーラル、チガソン)や光線療法群」での発生率は3.85%だったのに対し、「TNF-α阻害剤群」は3.05%と、「全身療法なし群」より55%低下、「経口全身療法および光線療法群」より21%低下した。「現時点で併存疾患に有効性が報告されている生物学的製剤は抗TNF-α抗体のみ」と説明した。
■セミナー便り
2.「LDL-Cは低いほどよいを証明」
-日本大学循環器内科学:平山篤志教授-
抗PCSK9抗体薬レパーサ(一般名エボロクマブ)が心血管イベントを抑制するとの試験結果が第66回米国心臓病学会(ACC)で発表されたことを受け、アステラス・アムジェン・バイオファーマは4月3日、都内でメディアセミナーを開いた。日本大学医学部循環器内科学分野の平山篤志主任教授は「The Lower,the betterが証明された。最適治療を受けていても心血管イベントを起こした患者など、(レパーサ上乗せの)ベネフィットを受ける患者を見つけていきたい」と述べた。
帝京大学臨床研究センターの寺本民生センター長は、家族性高コレステロール血症(FH)の診断率が低下していることに触れ、「LDL-Cをより強力に下げれば効果がある。(抗PCSK9抗体薬という)手段を手にした今、FHを早期に診断して的確に治療するべきだ」と説いた。
今回のFOURIER試験では、心筋梗塞既往などのリスク因子を有し、スタチン投与中の患者約2万7000人にレパーサまたはプラセボを上乗せし、2.2年(中央値)追跡した。
主要評価項目の複合心血管イベントで同剤は有意差をもって15%のリスク低減を示した。主要評価項目から「不安定狭心症による入院」などを除いたハードエンドポイントでは20%の有意なリスク低減であった。LDL-C中央値は同剤群30mg/dL、プラセボ群92mg/dLで、両群に有意差が認められた。
全有害事象、重篤な有害事象、投与中止に至った有害事象、認知機能の悪化、新たな糖尿病の発生に関して両群間に差は認められなかった。
平山氏は「最も興味深いこと」として、ベースラインのLDL-Cを4 段階に分けた解析で、LDL-Cが低い方がイベント抑制効果が大きかったことを挙げた。「1つの解釈として、到達したLDL-C値が低ければ低いほど、イベント発現が低下したと考えられる」と述べた。一方、評価項目のうち心血管死だけをみると両群に有意差はなかった。「この数十年で心筋梗塞による死亡率が低下したためだろう」との見方を示した。
■セミナー便り
3.ゴーシェ病「その病気を疑うまでに時間がかかる」
-東京慈恵医大小児科学講座:井田博幸教授-
日本ゴーシェ病の日である5月4日を前に、サノフィは4月11日、ゴーシェ病の疾患啓発セミナーを開催。酵素補充療法や基質合成抑制療法により治療は可能になったが、国内の発症頻度が33万人に1人といわれる希少疾患であることから、診断の際、医師に想起されにくいといった問題がある。東京慈恵会医科大学小児科学講座の井田博幸教授と、患者会の日本ゴーシェ病の会の古賀晃弘会長が講演し、疾患啓発の重要性を語った。
ゴーシェ病はライソゾーム病の1つで、日本では難病に指定されている。グルコセレブロシダーゼ遺伝子変異により、グルコセレブロシドという糖脂質を分解するグルコセレブロシダーゼという酵素が無いか働きが弱いため、細胞の中のライソゾームにグルコセレブロシドが蓄積する。その結果、肝臓や脾臓の腫れ、貧血や血小板減少、骨痛や骨折、あるいはてんかんや発達の遅れといった症状が現れる。臨床病型にはⅠ型(非神経型)、Ⅱ型(急性神経型)、Ⅲ型(亜急性神経型)がある。国内では96年に酵素補充療法薬セレデース、98年に酵素補充療法薬セレザイム、14年に酵素補充療法薬ビプリブ、15年に基質合成抑制療法薬サデルガが発売され、治療が可能になった。
その上で井田教授は「症状があってもその病気を想起しなければ検査しない。まずその病気を疑うまでに時間がかかる」と指摘。「Ⅰ型の患者であれば肝臓や脾臓が腫れて血小板減少や貧血があるので、白血病、ホジキン病を考える。そちらの方が一般的で、ゴーシェ病は非常に稀な病気だから想起できない。Ⅱ型はまず神経の病気ではないかとされ、進むうちに疑う」と語った。早期診断と早期治療に向けては、疾患啓発のほか、「一般の臨床家の方が入ってこれるように、専門医とネットワークをつくる必要がある」とした。
日本ゴーシェ病の会の古賀会長は「一番の課題は根治療法がないこと。また、神経型に対して有効な治療法がないこと」とアンメットニーズを指摘。代表的な治療法である酵素補充療法は肝臓や脾臓の症状に効果が見られ、ゴーシェ病による死亡率を減少させたが、中枢神経症状に対する効果は乏しい。遺伝子治療や、中枢神経への効果が期待される化学シャペロン療法の開発進展が望まれる。加えて古賀会長は「患者の環境整備は進んでいるが、患者の親(家族)に対するグリーフケアなどを含めた環境整備が問題になっている」と指摘。ゴーシェ病患者の就学・就労問題など課題解決に向けて患者会は様々な活動に取り組んでいる。
■セミナー便り
4.天然物創薬におけるアジアの有利性を確認
-第6回アジア製薬団体連携会議-
日本を含むアジア11の国/地域の規制当局関係者・アカデミア・業界団体が一堂に会するアジア製薬団体連携会議(APAC)が4月5、6の両日、東京カンファレンスセンターで開催された。
今回の会議では、新薬へのアクセス改善に向けた連携強化とアジア発創薬への挑戦をテーマに議論が進められた。アクセス改善については、新薬承認の審査期間を短縮するために設立された規制・許認可WGの取り組みが成果を挙げていることが報告された。同WGでは、申請を提出する側の規範GSubP(GoodSubmissionPractice)と、審査側のレビュー規範GRevP(GoodReviewPractice)を合わせたGRM(GoodRegistrationManagement)の普及と、審査状況の透明化向上による承認審査の効率化を目指している。すでに、GSubP普及へ資材を用いたトレーニング段階に入っており、企業側の審査対応プロセスの改善が進んでいる。GRMについてはAPECの場でも取り上げられており、今後、各地域で申請の実務者を対象にしたトレーニングの開催を積極的に進めていくことが確認された。
GRMの重要性について、製薬協の畑中好彦会長は会見で「審査、申請両側とも、時間だけでなく、リソースも減り、(承認審査にかかる)トータルのコストも減る。開発プロセスがエコシステムになることで、アジアの患者の新薬へのアクセスもよくなる」と語った。
アジア発創薬に向けては、アジアには多様性に富む生態系を維持している国が多く、今後、アジア諸国で天然物ライブラリーが整備されれば製薬企業との創薬連携を推進する貴重な研究アセットになり得ることを確認。創薬連携(DrugDiscoveryAlliances:DA)のワーキンググループでは、製薬協研究開発委員会と連携して、天然物の創薬応用をサポートするガイドラインづくりや、パイロットプロジェクトを立ち上げ、それを通じて人材育成を行い、天然物の創薬研究における可能性の最大化を目指すことで合意された。
天然物創薬は技術的に困難な上に、生物多様性条約に関連する制約から取り組む企業が限られているのが実情。製薬協国際委員会の平手晴彦委員長は「会議で、アジアが天然物の宝庫であること、天然物をターゲットにすることがアジアにとって有利でありユニークあることが確認された意義は大きい」とし、天然物創薬に拍車が掛かることに期待を寄せる一方、「成功には産官学連携のプライベートパブリックパートナーシップのオープンイノベーションも欠かせない」とした。
畑中会長は、アジアには天然物に詳しい研究者が多い一方で、森林資源、海洋資源、土壌資源といった天然資源を活用し切れていないとした上で「有効物質の抽出技術、同定技術、有効物質の精製技術、構造特定の技術、天然物のスクリーニング技術など、天然物から創薬につなげる次のステップの進歩を再認識した」と語った。すでに、タイや台湾では天然物ライブラリーを充実させる動きが強まっている。今後iPS細胞などを通じた新規のスクリーニング技術の確立が進展すれば、天然物からの新薬創出は大いに期待できよう。
DAワーキンググループでは、アジアにおけるオープンイノベーションの基盤として、アカデミア創薬シーズの産業活用を目的とした情報共有のプラットフォームづくりにも取り組んでいる。これは大阪商工会議所が開発した情報共有システム(DSANJ3)のマッチングシステムを応用したもので、大手企業の参加を促している。
今後は、アジアにおけるベンチャー支援策として、マッチングのみならず、育成の一環として、人材紹介、投資を呼び込む活動やインキュベーション施設の提供などについてもAPACならではの活動に期待したいところである。