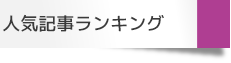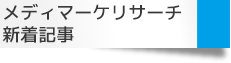■記者会見
1.バイオシミラー「自然な普及にならざるを得ない」
-東京理科大学経営学部:坂巻弘之教授-
東京理科大学経営学部の坂巻弘之教授は7月10日のバイオシミラー(BS)協議会の会見でBS普及促進に向けた方策として「日本のやり方として自然に普及させていくことにならざるを得ない。諸外国では様々な使用促進策が講じられているが、実は日本に馴染まないところがある」という認識を示した。国内ではインフリキシマブBSのように普及が進んでいない品目もある一方、インスリングラルギンBSのように普及が進み始めている品目もある。普及が進んでいないBSをどのように普及させていくのか議論になっている。
坂巻教授は先行品からBSへの切り替えについて「医師に裁量があり、一切の制限がない。エビデンスを積み重ねることで、医師がエビデンスを見ながら切り替えを進めていく方向しかない。それを無理やり政策的に切り替えるのは難しい」としたほか、インフリキシマブBSの普及が進んでいない要因として挙げられている高額療養費により患者が経済的メリットを感じないという問題に関しては「参照価格制度を導入するとか、高額療養費の対象にBSやジェネリックを使うとか、日本に馴染むのかどうか、議論がある。これも制度として強引に進めることは難しい」とした。
低分子化合物の後発品のように使用目標を掲げ普及を推進する政策も考えられるが、会見に同席した厚生労働省医政局経済課ベンチャー等支援戦略室の飯村康夫室長はBSのシェア目標は「できていない」と語った。その理由として「大きな市場がある製品のBSが出てくると、それによって分母と分子が大きく揺れてしまう。ジェネリックと違ってそういった問題がある。大きな市場の製品のBSが発売された後、先行品が圧倒的に強いとなると、一気に使用率が下がる。その凸凹がある中で数値目標が立てられない」としている。医療費削減効果についても「もともとのBSのシェア目標が立てられない中で削減額の目標を立てるのは難しい状況だ」と話した。
こうした意見の中、BS協議会の南部静洋会長は「医療費の削減だけでなく国内のバイオ産業の育成という面でも国内企業がバイオシミラーに参入できる環境は重要だ。結局、使われ出せば価格は下がってくるわけで、いまはなかなかそこが回転していない。ジェネリック医薬品は普及することで品質が上がって一般的になって価格がアクセスできるようになってきた。下がった医療費は他の新薬に回すことができる。一方、安価になる分、さらに普及すれば、より安価になってくる。それで一つの産業が回っていく。動き始めてきたら変わってくる」と話した。
■セミナー便り
1.20年ぶりの治療の進歩「輝かしい歴史」
-近畿大学医学部:中川和彦主任教授-
抗PD-L1抗体イミフィンジが非小細胞肺がんの3期で承認を取得したことを受けて、近畿大学医学部内科学腫瘍内科部門の中川和彦主任教授は「非常に輝かしい歴史。肺がん治療は重要なターニングポイントを迎えた」と話した。アストラゼネカ主催の7月23日のメディアセミナーで語った。
非小細胞肺がんの4期の治療薬では抗PD-1抗体キイトルーダ、オプジーボ、抗PD-L1抗体テセントリクが承認を取得したが、3期ではイミフィンジが初めて。切除不能な3期の非小細胞肺がんの標準治療は、化学療法と根治的胸部放射線療法の同時併用(CRT:ケモラジオセラピー)だが、20年間、治療法に進展がなかった。ここにイミフィンジがCRT後の維持療法として承認を取得したことで、パシフィックレジメンが誕生し、「治療が進歩していなかった領域がイミフィンジの承認をスタートとして動き始めていくだろう」(中川教授)と他剤の3期への適応拡大を含め期待を示した。
非小細胞肺がんの臨床病期の1期は原発巣のみの状態、2期は肺門リンパ節転移がある状態、3期は縦郭リンパ節転移がある状態、4期は肺から離れた他の臓器やリンパ節に転移がある状態だ。がん研究振興財団のがんの統計’17によると、非小細胞肺がんの初回治療の症例のうち3期は21.1%、4期は24.9%を占めている。3期は4期よりも患者数は少ないが中川教授は「潜在的に治癒可能なポピュレーションであることから非常に重要なターゲットだろう」と指摘。その上で「3期になると縦郭リンパ節まで進んできているので、残念ながら手術では取れない。特に縦郭リンパ節に1個だけ転移している場合は手術をすることもあるが、複数の縦郭リンパ節が入ってくると手術の適応はなくなってくる。その場合はCRTの適応になる」と解説。海外データのメタ解析で、同時CRTは根治を治療目的としながらも89%はCRT後に病勢が進行または転移、5年生存率は15%にとどまっていることを挙げ、イミフィンジによる維持療法がこの治療成績を延長することに期待を示した。
イミフィンジの承認の基になったPACIFIC試験ではプラセボに比べ主要評価項目の無増悪生存期間(PFS)でハザード比0.52[0.42~0.65]と再燃のリスクを半分にする効果があった。なお、安全性では肺臓炎に注意が必要とした。
中川教授は今後の課題として「どういう化学療法を行った方がどういうアウトカムになるのかという詳細をぜひ知りたい」とした。イミフィンジの前に使用するCRTには、シスプラチン+ビンデシン+マイトマイシンのMVP療法、カルボプラチン+イリノテカン、カルボプラチン+パクリタキセルなど選択肢がある。中川主任教授は「アメリカでは週1回のカルボプラチン+パクリタキセルが多そうだ。週1回のカルパクに放射線で、その方々のアウトカムが保証され、それでもいいとなると、パシフィックレジメンは患者にやさしい、すごく長期間の生存期間の延長と治癒率の向上をもたらすような治療法になるかもしれないと期待している」とした。
AZは18年第1四半期決算でPACIFIC試験の主要評価項目の全生存期間(OS)を達成したと発表しているが、その詳細は今後の学会で報告される。中川教授は「正直に言ってあまり期待していなかった。しかし、こんなに大きな改善を示したのは世界的な朗報だ。ニボルマブ、ペムブロリズマブよりも強いインパクトだと思う。治療成績に対していまはすごく希望的な感触を持っている」と話した。
■セミナー便り
2.乳がんの治療体系が「かなり変わる」
-愛知県がんセンター中央病院:岩田広治副院長-
愛知県がんセンター中央病院の岩田広治副院長は7月30日、アストラゼネカ主催のメディアセミナーで化学療法歴のあるBRCA遺伝子変異陽性HER2陰性の手術不能または再発乳がんに適応拡大したPARP阻害剤リムパーザについて解説。「アンスラサイクリン系やタキサン系がすでに使用されている患者が対象になる。さらに生殖細胞系列のBRCA遺伝子変異陽性の患者が適応になることによって、日本の乳がんの治療体系自体がかなり変わる要因の一つになった」と述べた。
医師は、再発乳がんの治療を考える際、(1)本人の要因(年齢、閉経の状況) (2)治療の要因(前治療の有無、効果) (3)がんの状況(ホルモン受容体やHER2の発現状況、再発部位、自覚症状、増殖スピード)-を考え治療方針を決定するという。この本人の要因にBRCA遺伝子異常の有無が加わった。岩田教授は「後天的にがん細胞が獲得した遺伝子異常(ソマティックミューテーション)ではなく、患者が持って生まれた遺伝子異常で一生変わることはない。これをもとにがんの治療が行われる時代が乳がん治療に訪れた」と語る。
リムパーザはDNA損傷応答(DDR)に着目した新薬でPARP阻害剤としてはファーストインクラス。DNA一本鎖切断の修復を行う酵素であるPARPの働きを阻害する。DNA一本鎖の切断が修復されないと、DNA複製に伴い、DNA二本鎖切断が生じる。正常な細胞やBRCA遺伝子変異のないがん細胞の場合は、DNA二本鎖切断がBRCAを介して修復されるが、BRCA遺伝子変異のあるがん細胞の場合は、二本鎖切断が修復されず、細胞死に至る。
乳がんへの適応取得の基になった国際共同第3相OlympiAD試験では、リムパーザ投与群は、ゼローダ(カペシタビン)、ハラヴェン(エリブリン)、ナベルビン(ビノレルビン)のいずれかを投与した群と比較して主要評価項目の無増悪生存期間(PFS)を統計学的有意に延長した。
岩田副院長は「ポイントで見ると、オラパリブ群は6カ月時点でも腫瘍が増殖していない方が54.1%、1年のところでも25.9%いる。投与した4分の1の方は1年たった時点でも腫瘍が小さくなるあるいはそのままでもっていけることが示されている」とコメント。
副次評価項目の全生存期間(OS)では統計学的に有意な差は得られなかったが、「転移性再発乳がんに対して化学療法をまったくやっていない患者だけに限って見ると、オラパリブを使った方が長く生きることができている。なので、再発したら早めにオラパリブを使う。それによって生存期間が長くなることが示唆されている」とした。
副作用の面では「貧血はオラパリブの方が多く出ている。好中球の減少と白血球の減少は化学療法の方が多く出ている。オラパリブは貧血に少し注意する必要はあるが、それ以外は他の化学療法の方が多いだろうという印象だ」と述べた。
乳がんには、ホルモン受容体(エストロゲン受容体とプロゲステロン受容体)陽性かつHER2陰性のルミナールタイプ乳がんと、エストロゲン受容体およびプロゲステロン受容体が陰性かつHER2陰性のトリプルネガティブ乳がんがあり、リムパーザはBRCA遺伝子変異陽性であればどちらのタイプの乳がんにも使用できる。
岩田副院長は薬剤の使い分けについて「ルミナールタイプ乳がんに関しては優先されるべきはホルモン療法だ。ホルモン療法が効かなくなってきて、化学療法への変更を考慮した際には、アドリアマイシン(ADR)やタキサンを術前・後で使用している場合、オラパリブの早期の使用を考慮する。ADRやタキサンを使用していない場合は、ADRやタキサンと比べてオラパリブが有効であったというデータはないので、ADRやタキサンを優先してPD(疾患進行)となった時点でオラパリブを考慮する」とした。
トリプルネガティブ乳がんには「ADRやタキサンが使用されている場合が多いので、なるべくオラパリブの早期の使用を考慮する。もし使っていない場合はADRやタキサンを使った後に考える」とした。
■セミナー便り
3.ネキシウムの小児適応取得「大きな一歩」
-信州大学医学部:中山佳子講師-
信州大学医学部小児医学教室の中山佳子講師は7月13日、アストラゼネカ(AZ)主催のメディアセミナーでプロトンポンプ阻害剤(PPI)ネキシウムの小児適応追加を歓迎。「10年近く医療現場で小児の患者にPPIを適応範囲内で使うことができない状況だったが、ようやくネキシウムが小児の用法・用量を1歳以上で得られた。私たちとしては非常に大きな一歩であると考えている」と話した。
抗生物質やアレルギー治療薬などのように小児の適応を取得している製品が多い領域もあれば、消化器のように小児の適応を取得している治療薬が少ない領域もある。PPIで小児適応があるものはネキシウムが初めて。
セミナーでは小児の胃食道逆流症(GERD)の診療について解説。中山講師は「小児の患者は胸焼け、呑酸といった成人で特徴的といわれる症状を自ら訴えることがない。主な症状は嘔吐、腹痛、吐き気といった非特異的な症状であることが多い。このため一般の診療でこれらの症状がGERDであることが見過ごされやすい」と指摘。また小児期の特徴として「呼吸器症状、体重増加不良、姿勢異常といった多彩な消化器外症状を呈し、消化器疾患であることに気づかれない患者が実際にいる」とした。
こうした見逃しを回避するため中山講師は年長児の場合、患者の胸に手を当てて「こういうところがジリジリ焼けるように痛いことはある?」「酸っぱい水や苦い水が上がってくる?」と具体的に聞くことが重要とした。もし胸焼けや呑酸があり、貧血や消化管出血などその他の器質的疾患を疑う危険徴候がない場合は、ネキシウムを2週間投与し症状の改善を確認する。有効なら4~8週間の治療を継続し、無効・再燃例の場合は小児消化器病医に紹介してもらいたいとした。
AZによると日本のGERDの患者は15歳以上で1344万人、1~14歳で3万7000人、1歳未満で2300人と推計されている。
■セミナー便り
4.L-ドパとL-ドパ以外「65歳で分けている」
-順天堂大学:服部信孝教授-
順天堂大学大学院医学研究科神経学の服部信孝教授は7月24日、武田薬品主催のパーキンソン病(PD)に関するメディアセミナーで、PD診療ガイドラインについて解説した。
服部教授はガイドラインから(1)早期PDの治療は早期から治療を開始した場合としない場合と比較してどうなったか(2)早期PDの治療はL-ドパで開始した場合とL-ドパ以外の薬で開始した場合と比較してどうなったか-を取り上げた。
(1)に関しては、ガーナのPD患者について、同時期にイタリアで実施されたPDの大規模コホート研究を対照群とし、運動合併症(ウェアリング・オフやジスキネジア)の発現、L-ドパ治療期間、PD罹病期間との関連について検討した結果に基づき、「ガーナでは診断と治療開始が遅れるので、ハネムーン期間(症状を良好にコントロールできる期間)が短い。早期診断、早期治療介入がPD患者では重要である」(服部教授)とした。
(2)については第一選択薬としてL-ドパ、ドパミン作動薬、MAO-B阻害剤がある。服部教授は、運動障害により生活に支障を来す場合は、L-ドパで開始する方が良く、おおむね65歳以下発症など運動合併症のリスクが高いと判断される場合は、L-ドパ以外の薬物療法を考慮するとした。「L-ドパを投与するとレボドパ誘発性ジスキネジアが問題になる。そのリスクに若年発症が挙げられる。若年発症という点は現在65歳というのが基本的な流れになっている」(服部教授)。またドパミン作動薬で開始する場合は衝動調節障害や眠気に注意する必要があるとした。
■セミナー便り
5.血友病、保因者女性に正しい知識とケアを
-久留米大学医学部:松尾陽子助教-
血友病患者の母親のうち、自身に起こり得る健康上の問題として女性特有の「月経過多」や「分娩時の出血の多さ」があることを知っていたのは3~4割にすぎず、7割以上が「血が止まりにくい」などの健康上の問題を経験しているものの、血友病に関連した問題である可能性を踏まえた対応をしているのは3人に1人だった-。バイエル薬品が7月26日に発表した血友病患者の母親の心と体のケアに関する意識調査の結果を受けて、同社が同日開催したプレスセミナーでは、久留米大学医学部小児科学教室の松尾陽子助教が保因者女性への適切な情報提供や周産期管理を含めた包括的ケア推進の必要性を語った。
血友病は、血栓形成に必要な血液凝固因子(第Ⅷ因子または第Ⅸ因子)の欠乏あるいは活性低下に起因する、遺伝性の出血性疾患である。X染色体連鎖性の劣性遺伝形式のため、患者のほとんどが男性であり、患者の家族には血友病の原因となる遺伝子を持つ女性(保因者)もいる。
調査は血友病患者の母親54人を対象に18年5月~6月にかけて行われた。その結果、自身にも健康上の問題が起こる可能性について正確に認知していると回答したのは81.5%で、不正確な認知も含めて「知っている」と回答した保因者のうち、青あざ(内出血)ができやすいことへの認知度は95.6%に達した一方、月経過多の認知度は42.2%、分娩時の出血の多さについては35.6%にとどまった。自身に健康上の問題があった場合に、家族に血友病患者がいることを話した上で一般の医療機関を受診するなど、血友病に関連した健康上の問題である可能性を踏まえた対応をしている人は34.1%、3人に1人にすぎなかった。
この調査の監修者の一人でもある松尾氏は、保因者の多くは凝固因子活性値が健常者の40%~60%で、これは一般的には止血には十分な量だと考えられているものの、自身のフォローする保因者の中では一番低い方で9%、高い方だと90%前後あり、個人差が大きいこと、さらに、保因者は因子活性が保たれていても出血傾向があるという報告も多いことを紹介した。
こうした背景で今回の調査が行われたわけだが、患者会などで保因者の健康上の問題などについて話すなど保因者ケアに真剣に取り組んできたという松尾氏は、自身を通じても集められた対象者における調査結果が前述のようなものであったことについて「ショックだった。適切な情報提供や支援の必要性を改めて認識した」と述べた。
松尾氏が約10年前に実施した調査では、12例中6例が、血友病の子どもを出産するまで、自分が保因者かもしれないということを家族から告知されていなかった。その後に行われた同様の調査でも、同じような結果が報告されているという。つまり、血友病のリスクについて、妊婦である母親も、産科医も、誰も知らずに出産に臨んでいたということだ。松尾氏によれば、血友病患者にとって分娩は最も頭蓋内出血を来しやすいリスクの1つであり、「凝固因子製剤が飛躍的に進歩し健常人と変わらない生活が送れるようになった現在でも、分娩にかかわる頭蓋内出血のために重篤な後遺症を来した血友病の赤ちゃんの数は減っていない」実感があると語る。
妊婦が保因者であると分かっていれば、妊婦に対しても、生まれてくる赤ちゃんに対しても、適切な対応を取ることができる。「保因者女性が正しい知識を持って適切に対応していくことが大切であり、産科、婦人科を含めた保因者女性への包括的なケアが行われるよう連携を進めていきたい」と訴えた。
■セミナー便り
6.SMA、スピンラザ登場で早期診断が重要に
-久留米大学医学部小児科学教室:弓削康太郎助教-
バイオジェン・ジャパンは7月31日、脊髄性筋萎縮症(SMA)治療薬スピンラザが今年8月に発売から1年を迎えるに先立って第1回メディア向け勉強会を開催した。久留米大学医学部小児科学教室の弓削康太郎助教はスピンラザ登場でSMAが治療可能になったこと、そのために早期診断が重要になったことを説明したうえで、「多くの一般小児科医はSMAを聞いたことしかない。ちょっと運動が遅れている程度であればSMAを思い浮かべもしない」と述べて医療現場への啓発活動を一番に取り組むべき課題に挙げた。
SMAは脊髄の運動神経細胞の病変によって起こる神経原性の筋萎縮症で、体幹や四肢の筋力低下、筋萎縮を進行性に示す疾患である。常染色体劣性遺伝の形式をとるため、父親、母親がともに保因者である場合、子どもは4分の1の確率で発症する。乳児期から小児期に発症するSMAの罹患率は10万人あたり1〜2人とされる。原因遺伝子となるのはSMN1遺伝子で、SMN1遺伝子の欠失または変異により運動ニューロンの正常な機能を維持するSMNたんぱく質が欠乏を来し、筋肉が脳からの信号を受信できなくなる。
スピンラザ(一般名ヌシネルセンナトリウム)は、SMN1の重複遺伝子であるSMN2のスプライシングを変え、完全に機能するSMNタンパク質の産生を増やすようデザインされている。日本初のアンチセンス核酸医薬品である。
弓削氏は、スピンラザを投与する患者8例のうち3例を紹介し、特に指の力がアップした、リモコンのボタンが押せるようになったなどの微細運動における変化が早く現れた一方、全身を使うような粗大運動への効果は遅いようだと感想を述べた。しかし、ハイハイの高這いの体勢を取れなかった子が取れるようになってきているという事例を挙げて、ゆっくりと効果は上がってきており、いずれ座れなかった子が座れる、立てなかった子が立てるようになることも「期待できる薬だと思っている」と語った。
弓削氏によれば、SMAの診断は、従来は「治療がないので、告げられたときの親の気持ちも考慮してあまり急がずにゆっくり行ってきた」が、スピンラザ登場によって治療が可能になったことで、早期診断が重要になったという。その一方で、「本来はかかりつけ医に相談するのが一番良い」としつつも、一般開業医の小児科医はこの病気については聞いたことしかなく、ちょっと運動が遅れている状態であればSMAを思い浮かべもしないと思うと述べて、一番に取り組むべき課題として医療者への啓発活動の必要性を訴えた。
スピンラザは髄腔内の脳脊髄液中に投与され、投与には十分な知識・経験を持つ医師のもとで行うこととされている。SMAでは成長とともに脊柱が曲がる、捻れるなどの側弯の症状が出ることも多く、弓削氏はスピンラザの髄腔内投与について、「小児科医だけではできず、麻酔科医や脊髄の痛みをコントロールする専門のペインクリニックの医師らと共に工夫しながら行っている」とその苦労を語っている。同社メディカル本部の希少疾患(SMA)・アルツハイマー病領域の飛田部長は、「患者にどんな薬が良いかを伺うと「飲み薬が一番」だと返ってくる。今すぐどうという話をできるところにはないが、そういう風になる方向に一生懸命やっている」と改善に取り組んでいることを明らかにした。
■行政トピックス
1.中医協総会7月18日
「オンライン服薬指導」保険適用へ、特区が試金石
厚労省は7月18日の中医協総会に、国家戦略特区法の一部改正に基づき、3地区(愛知県、兵庫県養父市、福岡市)において、テレビ電話による服薬指導が可能とされたことを受け、暫定的に「薬剤服用歴管理指導料(調剤基本料1でお薬手帳活用で41点、それ以外53点)」を算定できることとしてはどうかと提案し、了承された。同省は「国家戦略特区の場合の特例として暫定的な措置」と説明したが、すでに18年度改定で「オンライン診療」が保険適用になっており、中医協委員からは、将来の「オンライン服薬指導」の保険適用を見据えた意見が出た。
特区におけるオンライン服薬指導には、(1)離島、へき地に居住する者 (2)遠隔診療が行われる (3)対面での服薬指導ができない-といった条件が付いている。厚労省は「薬剤服用歴管理指導料の算定要件を満たし得る」との判断の下、中医協に対し、同指導料の算定を可能とすること、その際、 (1)患者の手元に薬剤が届いた後にも、改めて必要な確認を行う (2)厚労省の定める情報通信を用いた診療に係る指針を参考に情報セキュリティー対策を講じる (3)お薬手帳の活用を前提とする-を求めることを提案し、了承された。
前回18年度改定で新設された「オンライン診察料(70点)」および「オンライン医学管理料(100点)」は、対面診療の原則の上で、有効性や安全性等への配慮を含む一定の要件を満たすことが前提。日常診療で活用するもので、遠隔地においてということは前提とはしていない。一方、今回は、あくまで特区の条件下で「離島、へき地に居住する者」に限定している。
将来のオンライン服薬指導の保険適用を見据え、支払い側の吉森俊和委員(協会けんぽ理事)は「特区における実証においては来るべき将来のオンライン化を踏まえ、まずは実証、成果ならびにエビデンスを蓄積して丁寧に分析してほしい」と要請。診療側の松本吉郎委員(日医常任理事)は「オンライン診療と同様のガイドラインや枠組みが必要になるのではないか」と提案。
これに対し厚労省は、「特区においてさまざまなデータが出てくると想定されるので、改めて算定要件や点数を検討いただきたい」「オンライン診療の議論を踏まえて進めていこうと考えている」などと応えた。