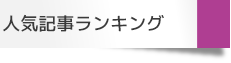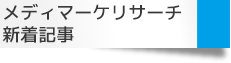■セミナー便り
1.HPVワクチン接種後の「機能性身体症状」の診療体制は不十分
-JR東京総合病院前副院長:奥山伸彦医師-
JR東京総合病院前副院長の奥山伸彦医師は10月13日に日本医師会館(文京区)で開かれた日医・日本医学会合同公開フォーラム「HPVワクチンについて考える」で、「HPVワクチン接種後の機能性身体症状」をテーマに講演し、「(同症状を呈した)患者にとって十分な診療体制が用意されていないことは事実。患者はしばしば極めて困難な状況に置かれている」と述べ、小児内科医が積極的に関与するなど、診療体制を再構築する必要性を訴えた。
HPVワクチンは13年4月に定期接種化されたが、接種後に広範な慢性の疼痛などの多様な症状が見られ、「十分に情報提供できない状況」にあったことを理由に、2カ月後の6月に「積極的な接種勧奨の差し控え」が実施された。
その後、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会と薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(14年1月、合同開催)は、多様な症状を「機能性身体症状」と結論付けたが、現在に至っても「積極的な接種勧奨」は再開されていない。「機能性身体症状」の診療体制が整っていないことも要因の一つと考えられる。
奥山医師は「改めて機能性身体症状として定義して認知行動療法を主体としてエビデンスを蓄積していかなければならない」と指摘。その治療に当たっては、患者と医療者の疾患認識の共有が重要であり、特に (1)痛みや刺激がきっかけとなって広く体の痛みや多様な症状が出現することがあること (2)現在の医学ではHPVワクチン接種が原因であるとも、原因でないとも証明できていないこと-の2点を共有することが大事だと述べた。
診療体制については、全国に設置されている相談窓口から接種医療機関を受診、協力医療機関(HPVワクチン接種後の症状に対する診療を行うために都道府県ごとに設置されている医療機関)を受診という流れになるが、「協力医療機関で担当する多くは麻酔科であり、小児科は10施設程度にとどまる」と指摘。「個人的には小児内科医が積極的に参加してほしい。一人の主治医が継続的に診ることがとても大事だ」と強調した。
■セミナー便り
2.米国を巻き込んで日本に強いエコシステムを
-製薬協:中山譲治会長-
製薬協の中山譲治会長は10月10日、横浜市で行われたバイオジャパン基調講演「創薬イノベーションの将来像」で、米国の高い創薬力の背景には、バイオベンチャーを含む創薬エコシステムの存在があると指摘。「日本はもっと複雑で強力なエコシステムを持たないと創薬競争に勝てない」とした。その上で「アメリカはベンチャーを育てるノウハウを持ち、エンジェル投資家の企業を判断する力も日本とはものすごく違う。こういう人たちを巻き込んだ日本のエコシステムを作れないか」と提言した。
米国ではアカデミアやベンチャー企業が新薬の種を見いだし、ベンチャーや製薬企業が臨床試験を行い、新薬として上市する中で、NIH(国立衛生研究所)やFDA、医療機関、投資家もエコシステムを支えている。中山会長はオールジャパンというよりも「日本でのエコシステムをさらにオープンでボーダレスなものでアメリカにつないでいきたい。ベンチャー企業の方々がアメリカで様々な投資家と会い、日本発のアセットとして彼らをこちらに呼んできて一緒にやるくらいのボーダレスなシステムを作っていただく。それがこれからの日本を変えていくと信じている」と語った。そのほか、創薬力を高める施策として、医療IDに基づくデータベースの整備や基礎研究への十分な資金提供を挙げた。
中山会長は国内で薬剤費を含む医療費の削減が行われ医療の質が劣化することを懸念。それにより国民の健康が損なわれる「デビルサイクル」ではなく、創薬イノベーションにより社会的費用が軽減されるほか、再生医療を含むライフサイエンス分野に多くの業界が参入することによる経済効果、さらには国民の健康寿命が延伸する「エンジェルサイクル」に転換しなければならないとした。
■セミナー便り
3.国際標準に向け連続生産の確立に挑戦
-MAB組合:小林和男GMP施設長-
次世代バイオ医薬品製造技術研究組合(MAB組合)の神戸GMP集中研の小林和男GMP施設長は10月2日の製薬協プレスツアーで、抗体医薬の連続生産の確立に向けた取り組みを紹介した。「連続生産のプロトタイプとなるような技術は全世界でまだ誰もきちんとしたものを持っていない」とし「そこで今回、MAB組合の中で、日本の中で、一つのプラットフォームとして技術を作っていく」と意気込みを語った。
MAB組合は国内のバイオ医薬品製造にかかわる企業、大学、公共機関が集まり、抗体医薬の製造技術の研究開発を進めている。抗体生産細胞の構築から原薬までのプロセスを手掛けている。現在、33企業、4団体、1国立研究開発法人、4大学が組合員だ。
小林GMP施設長によると、13年にMAB組合が設立された当時は、日本のバイオ医薬品製造は欧米に比べて2周遅れているといわれていたが、この5年間で「技術では追いついた」。18年度からは「従来のバッチプロセスはコストの限界があったが、これを自動化、連続的に製造することでコストダウンが図られるのではないかということでMAB2が始まった」と言う。
MAB2ではMAB組合として連続生産の確立に向けて(1)細胞構築要素技術開発 (2)細胞培養要素技術開発 (3)精製要素技術開発 (4)解析評価要素技術開発 (5)ウイルス管理技術の開発 (6)連続生産技術のプラットフォーム化および実証-を進めている。
神戸GMP集中研は連続生産が事業化できるか検証する。具体的には50リットルのスケールで2カ月間の連続生産を実証することが目標だ。従来のバッチプロセスに比べ製造コストが3割減となることも目指す。さらには連続生産にかかわるレギュレーションは定まっていないので、規制当局と連携し、レギュレーション構築も進める。
連続生産の技術が確立した際には「製薬企業でバイオ医薬品のシーズが見えている時にこのプラットフォームを使ってコスト削減ができるだろう。規制当局のガイドラインも作っていくので申請書の記載なども一つのフォーマットとして提供できるようになる」とした。
プレスツアーではバイオロジクス分野の人材育成を行うバイオロジクス研究・トレーニングセンター(BCRET)の内田和久理事も登壇し「全日本で何とかバイオロジクス産業を盛り上げたい。その人材育成、教育ではBCRETが担いたい」と抱負を語ったほか、将来的には「教育ビジネスをアジアにまで広げ、アジアのレギュレーターに対する教育を行っていきたい」とした。BCRETは4月に講習業務を開始した。初年度は製薬企業などの社員を主な対象とし6〜8月で座学4回、実習4回を実施した。座学はのべ120人、実習はのべ40人が参加した。
■セミナー便り
4.FMI事業「医師の負荷軽減に貢献」
-中外製薬:飯島康輔PHC推進部長-
中外製薬の飯島康輔PHC推進部長は9月28日、FMI(ファウンデーションメディシン)事業の説明会で、がんゲノム医療中核拠点病院やがんゲノム医療連携病院で患者の治療方針を決定する専門家会議において、FMI事業が提供するレポートが「医師の負荷の軽減に貢献できるのではないか」と期待を語った。
FMI事業はロシュ傘下でがん関連遺伝子検査を手掛ける米国FMI社の事業を国内で展開するもの。中外製薬は3月に米FMI社の医療機器について国内承認申請を行った。医療機関から検体を受け取り、それを検査し、検査結果を実臨床で活用しやすい形のレポートにして医療機関に渡す。医療機関に医療機器や試薬を販売するのではなく、このレポートによる情報提供サービスに対して対価を受け取る。
国内承認申請している米FMI社の医療機器はがん関連遺伝子を一括で検出できる次世代シークエンサー(NGS)に基づくもの。17年11月にFDAから固形がんを対象とした網羅的遺伝子解析パネルおよびコンパニオン診断の使用目的で承認を取得した。324のがん関連遺伝子を一括で検査できるほか、コンパニオン診断ではがん種17治療薬に対する適応を有している。
非小細胞肺がんで言えば、がんの発生や増殖にかかわるドライバー遺伝子変異として、EGFR、ALK、ROS1、BRAF、MET、RET、HER2などがある。免疫チェックポイント阻害剤を使用するなら、有効性のバイオマーカーといわれているTMB(腫瘍遺伝子変異量)やMSI(マイクロサテライト不安定性)を調べる必要も出てくる。こうした事柄を1つずつ個別の検査で調べていくと検査期間が長引くほか、検体の量が不足する懸念がある。そのため一括で検査できるNGS検査が開発されている。
ただ、NGS検査で得られる情報は膨大な量になるため、そのままでは実臨床に生かすことは難しい。この検査結果に適切な解釈を加えて、医療現場に返す必要が出てくる。FMI事業では「解釈の部分が肝」(飯島PHC推進部長)としている。例えば、患者や医療機関などの背景情報、検出された変異結果のサマリー、対応する分子標的薬の承認情報、検出された変異に対する進行中の臨床試験、検出された変異および候補治療薬の文献サマリーが付いたレポートとして医療機関に検査結果を返す。このようなレポートが医師の治療方針の決定の補助となり、加えて、専門家会議における医師の負荷の軽減に役立つという。
飯島PHC推進部長はこのほかにも「情報サービスとして検査を届けることによって患者の適切な治療へのアクセス向上や遺伝子情報に基づく医薬品の開発に貢献できる」と語った。現在は固形がんを対象とした組織検体の医療機器の国内承認申請中だが、米FMI社が開発中の固形がんを対象とした血液検体の医療機器に関しても国内導入を進めるとした。
■セミナー便り
5.非代償性肝硬変、DAA未承認で高いアンメットニーズ
-武蔵野赤十字病院:黒崎雅之消化器科部長-
ギリアド・サイエンシズが10月4日に開催した、非代償性肝硬変のリスクと治療実態に関するメディアセミナーで、武蔵野赤十字病院消化器科の黒崎雅之部長は、日本では「最も治療を必要としているはずのC型肝炎ウイルスによる非代償性肝硬変に有効な治療薬はいまだ無い」とアンメットニーズの存在を指摘した。
肝硬変には、肝臓の働きが悪いながらも保たれていて、自覚症状がない代償性肝硬変と、代償性肝硬変が進行して、浮腫、黄疸、腹水、肝性脳症に伴う精神神経症状(意識障害、異常行動、昏睡など)などの症状が表れる非代償性肝硬変がある。チャイルドピュー分類(肝機能分類)別に3年生存率をみた調査では、グレードA(最も軽度。代償性肝硬変に相当)が93.5%なのに対し、非代償性肝硬変に相当するグレードCでは30.7%にまで低下しており、非代償性への進行は生存率にも大きく影響することが明らかになっている。また、肝硬変の進行は肝がんの発症リスクを上昇させるといい、肝硬変患者全体のうち、肝がんで死亡する患者は54%で最も多く、肝臓の働きが悪化することによる肝不全で死亡する患者は39%とする調査結果も示された。
肝硬変を引き起こす原因として最も多いのがC型肝炎ウイルス(HCV)で、53.3%と過半を占めるという。そのHCVに対しては近年多くのDAA(直接作用型抗ウイルス薬)が登場し、幾つもの治療選択肢があるものの、それらの適応はC型慢性肝炎およびC型代償性肝硬変に限られており、国内では、より症状の進行した非代償性肝硬変への使用は今のところ認められていない。
一方で、海外ではDAAの使用が認められており、(1)DAA投与によって患者の予後が改善したことを示すデータがある(2)HCVを除去することで肝がん発症のリスクが軽減するという幾つもの論文があり、それらのメタ解析ではリスクを5分の1に減少させた(3)別の調査ではウイルス除去により死亡リスクを半分以下に軽減させた-ことなどが示された。
■セミナー便り
6.ローブレナ、アレセンサ後の2Lとして11月にもGL反映へ
-近畿大学医学部:光冨徹哉主任教授-
第3世代とよばれるALK阻害剤ローブレナ(一般名ロルラチニブ)が、ALK陽性非小細胞肺がん(NSCLC)治療薬(2次治療以降)として、条件付き早期承認制度の適用を受けて9月21日に承認された。これを受けてファイザーが10月11日に開催したプレスカンファレンスにおいて、近畿大学医学部主任教授で日本肺癌学会理事長の光冨徹哉氏は、「ロルラチニブは、現在1次治療として最も推奨度が高いアレクチニブが効かなくなった場合の2次治療として、11月には肺癌診療ガイドラインに入ってくるだろう」との見通しを示した。
ALK遺伝子とEML4遺伝子が転座によって融合したALK融合遺伝子は、肺腺がんの3〜5%で発現が確認されており、ALK融合遺伝子から産生されるALK融合タンパクは二量体化することで常に活性化した状態になり、シグナル伝達因子が活性化され、細胞増殖が促進されると考えられている。肺癌診療ガイドライン(2017年版)ではALK遺伝子転座陽性のⅣ期のNSCLC(非小細胞肺がん)の1次治療としては第2世代のアレクチニブ(製品名アレセンサ)が推奨され、第1世代のクリゾチニブ(ザーコリ)、第2世代のセリチニブ(ジカディア)が続いている。しかし、ほとんどのケースで耐性を獲得してしまうことが課題となっており、特にアレクチニブでG1202Rなどの二次耐性変異が出現した場合は他のALK阻害剤での効果も期待できず、プラチナ併用療法が行われてきた。ロルラチニブはG1202Rを含む既存薬の耐性変異克服および中枢神経系への移行性を高めることを主目的に開発された。
同じく講演した兵庫県立がんセンターの里内美弥子呼吸器内科部長は、ロルラチニブ申請の基になった国際共同第1/2相試験の結果を解説した。試験は日本人39例を含むALK陽性またはROS1陽性の切除不能な進行・再発NSCLC患者275例を対象に行われ、主要評価項目は奏効率(CR+PR)、頭蓋内病変の奏効率(CR+PR)に設定された。試験の結果、奏効率は47.2%、頭蓋内病変奏効率は53.0%だった。ALK阻害剤による前治療別のサブグループ解析では、クリゾチニブを含む群で奏効率50.3%、アレクチニブを含む群35.1%、セリチニブを含む群で34.2%だった。
耐性獲得には、二次遺伝子変異による場合と、バイパス経路の活性化など、遺伝子変異によらない、他の何らかの要因による場合があるという。血しょう中のセルフリーDNA(cfDNA)解析で二次耐性遺伝子変異の有無別に奏効率を検証した結果、第2世代ALK阻害剤を使用した群のうち、二次耐性遺伝子変異を有する群では61.2%、二次耐性遺伝子変異の認められない群では26.4%と差が付いた。さらに、G1202Rの変異を有する患者に限って見れば、57.9%に奏効していた。里内氏は「耐性遺伝子変異に効くようにつくられた薬剤としての力が出ている」と評価した。
副作用については、全体の94.9%に発現した。このうち最も発現率が高いのが81.5%に発現した高コレステロール血症だ。しかし早めにストロングスタチンを使うことで十分にコントロール可能であり、グレード3以上の症例はその使用が遅れただけではないかとの見解を示した。認知障害、気分障害、言語障害などの中枢神経系障害も20%弱に発現したものの、休薬することで回復する可逆性の症状であることを強調した。
肺癌診療GL改訂について光冨教授は「最も推奨度の高いアレクチニブが効かなくなった場合、現在は普通の抗がん剤だが、そこに入ってくると思う。今年の11月には出てくるだろう」と述べた。