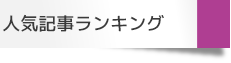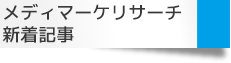■行政トピックス
1.医薬品等安全対策調査会 9月25日
スタチン・フィブラート併用に関する「原則禁忌」を解除
厚労省の薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策調査会は9月25日、HMG-CoA還元酵素阻害剤(以下スタチン)と、最近発売されたパルモディアを含むフィブラート系薬剤(以下フィブラート)の併用時の安全性について検討し、腎機能に関する臨床検査値に異常が認められる患者に対する「原則禁忌」を解除することで意見が一致した。日本動脈硬化学会からの添付文書改訂の要望を踏まえたもの。ただし「重要な基本的注意」の項に記載を移し、注意喚起を継続する。
スタチンとフィブラートの併用をめぐっては、1994年5月からベザフィブラート(先発品はベザトール)の添付文書の「慎重投与」の項に、「スタチンを投与中の患者」、また「相互作用」の項に、「スタチンとの併用により横紋筋融解症があらわれやすいので注意すること」と記載された。しかし、その後も横紋筋融解症の副作用が継続して報告された。
このため、ベザフィブラートの再審査時(99年3月)において、スタチン併用例で横紋筋融解症が発現した症例のうち、多くが、投与前の血清クレアチニン値が1.5mg/dLを超えていたことから、「禁忌」および「併用禁忌」の項に、「血清クレアチニン値が1.5mg/dLを超え、スタチンを投与中の患者」が設定された。
その後、ベザフィブラートは、腎機能に異常がある患者では、血中濃度が上昇しやすく、スタチンとの併用は横紋筋融解症のリスクがあるものの、医療現場において併用される患者が存在することから、「禁忌」および「併用禁忌」の項から、「原則禁忌」および「原則併用禁忌」の項に移行し、「原則禁忌」の項の記載は、「腎機能に関する臨床検査値に異常が認められる患者に、本剤とスタチンを併用する場合には、治療上やむを得ないと判断される場合にのみ併用すること」と記載された。スタチンと他のフィブラートについても添付文書の記載に整合が図られた(99年6月16日付、安全対策課長通知)。
日本動脈硬化学会は18年4月11日付で安全対策課長あてに、腎機能低下患者におけるスタチンとフィブラート併用に関する原則禁忌に係る添付文書改訂の要望書を提出。この中で、「(スタチンによって)LDL-Cを十分に低下させても、脳心血管イベントを完全に防止できるわけではない。高トリグリセライド(TG)血症や低HDL-C血症に対する治療の重要性が大いに注目され、スタチンとフィブラートの併用による治療が臨床現場で求められている」と指摘。
さらに、17年7月に承認された(発売は18年6月)パルモディア(ペマフィブラート)に触れ、「TGの低下の強さ、HDL-Cの上昇の強さに加え、肝・腎への影響が少なく、スタチンとの併用が可能な新しいクラスの薬剤と期待されるが、従来のフィブラートと同様にスタチンとの併用に関して原則禁忌の制限が設定され、医療従事者が困惑する状況であるとともに患者にとっての不利益が懸念される」と問題提起した。
これを受けPMDAは、海外添付文書の記載状況や、国内外のGL、製造販売後調査結果、国内副作用報告の集積状況などを調査し、安全対策調査会に報告。同調査会で、併用に関する「原則禁忌」および「原則併用禁忌」の削除が決まった。
■セミナー便り
1.セルフメディケーション税制の利用実績2.6万人
-日本OTC医薬品協会-
日本OTC医薬品協会は9月27日のメディアブリーフィングで、セルフメディケーション税制の利用状況を解説した。国税庁調べ(18年3月31日確定値)で確定申告を行った2200万人のうち、同税制を利用したのは2.6万人だった。同税制は、スイッチOTC医薬品の購入額が年間1万2000円を超える時は、その超える部分の金額(上限8万8000円)について、その年の総所得金額などから控除するというものだ。抗アレルギー薬など、対象品目は9月18日現在で1700品目ある。
日本製薬団体連合会および日本一般用医薬品連合会が18年3~4月に実施したセルフメディケーション税制の認知・利用に関する生活者調査では、同税制申告群は平均約3万4000円の対象品を購入し、同税制による所得税減税額は平均約4000円だった。
一方、1万2000円以上購入しているが、申告しなかった下限超え非申告群では平均約2万6000円購入しており、同税制を理解しているのは約4割だった。どちらの群も同税制に対して、還付金の増加や手続きの簡素化を求めている。
■セミナー便り
2.レンビマ「肝細胞がん1次治療の主流になる」
-近大医学部消化器内科:工藤正俊教授-
切除不能な肝細胞がんに対する1次治療薬はバイエル薬品のネクサバール(ソラフェニブ)しかなかったが、約10年ぶりにエーザイのレンビマ(レンバチニブ)が登場した。これを受けて近畿大学医学部消化器内科の工藤正俊教授は9月18日、同社主催のレンビマ説明会で講演し、同剤の特長として忍容性や奏効率の高さを挙げ「1次治療の主流になる可能性がある」とし「ソラフェニブを最初から使う理由はあまりない」とした。
国際共同第3相REFLECT試験でレンビマはネクサバールと比較し主要評価項目の全生存期間(OS)において非劣性を証明した。OSの中央値はレンビマ群13.6カ月、ネクサバール群12.3カ月(ハザード比0.92、95%信頼区間0.79~1.06、非劣性マージン1.08)。ただ、工藤教授は同試験の患者背景でベースライン時のAFP値(予後規定因子)が200以上の患者がレンビマ群46%、ネクサバール群39%だったことを指摘し、「レンバチニブにとって不利だった。同等に割り付けられたと仮定した場合では優越性が有意に証明された」とした。補正した場合のOSのハザード比は0.856(95%信頼区間:0.736~0.995)という。
試験中に発現した有害事象はレンビマ群の方が高血圧、甲状腺機能低下症、蛋白尿が多く、ネクサバール群の方が手掌・足底発赤知覚不全症候群(手足症候群)、下痢、脱毛症が多かった。工藤教授は「患者が自覚する副作用はソラフェニブに多い。レンバチニブは薬剤でコントロール可能で患者はほとんど症状を感じない」とし、特に「手足症候群はソラフェニブにとって極めて重篤な副作用だった。その頻度がレンバチニブで低いということは、患者にとって継続しやすい薬剤ということになる」とした。手足症候群は抗がん剤により手や足の細胞が障害されて起きる皮膚障害で、ピリピリとした感覚の異常や痛みが起きる。重度になると足の裏に潰瘍ができるなどして歩くことが困難になる。この副作用はネクサバールの投与を中断する理由の一つになっていた。
副次評価項目では独立画像判定による奏効率(ORR)がレンビマ群40.6%、ネクサバール群12.4%だったことを取り上げ、「肝細胞がんの分子標的薬として奏効率が40%を超えたのは初めてだ。少なくとも奏功した患者は長期延命効果が得られることが分かっている。その割合が多いということは患者にとってメリットがあるということにほかならない」とした。
なお、レンビマは様々ながん種で免疫チェックポイント阻害剤キイトルーダとの併用試験を進めている。切除不能肝細胞がんに関しては第1相試験段階。18年6月のASCO(米国臨床腫瘍学会年次総会)で第1b相116/KEYNOTE-524試験について報告されている。主な有害事象は食欲不振、高血圧、下痢、疲労で、奏効率は42.3%(95%信頼区間:23.4~63.1)だった。
工藤教授は併用療法の手応えについて「有害事象は私が経験した患者はそんなには強く出るということはなかった。奏効率は観察期間が短い症例が入っているので、症例が増えて観察期間が増えたら奏効率が良くなるのではないかと考えている」と語った。
高い奏効率が得られれば、がんのダウンステージングによって根治的な治療法(切除、マイクロ波、ラジオ波、塞栓療法)にスイッチできる可能性が出てくるという。
■セミナー便り
3.化膿性汗腺炎への生物学的製剤使用に前向き発言
-虎の門病院:林伸和皮膚科部長-
虎の門病院の林伸和皮膚科部長は9月27日、アッヴィ主催の化膿性汗腺炎についての疾患啓発メディアセミナーで講演し、「認可されている良い治療法はない」としたうえで、生物学的製剤が登場した場合に「積極的に使いたい」との意向を示した。
化膿性汗腺炎は青年期に発症する難治性の炎症性皮膚疾患で、腋窩、鼠径部、乳房、臀部などに頻発し、赤く腫れ上がったおできのような症状が表れる。進行すると結節、膿瘍、瘻孔の形成まで至る。瘻孔は内部にトンネルのようなものができ、そこに膿が溜まっている状態だ。長期にわたる炎症は結果的に皮膚がん(有棘細胞がん)を引き起こす可能性があり、がんが瘻孔にできた場合は発見が遅れ、すでに転移している場合もある。
当初は細菌感染が炎症の原因とされていたが、現在は感染に関係なく炎症が起きていること、喫煙、肥満などの環境的要因だけでなく、遺伝的要因も重要なことが分かってきている。
推定罹患率は、日本では医療機関受診患者のおよそ10万人に4人、海外では各調査にばらつきがあるが、平均して1000人に1人くらいという希少疾患だ。認知度も低く、林氏らの調査によれば、診断・治療法などの詳細を知っている医師は、皮膚科医で61.4%、一般内科開業医ではわずか1.0%にすぎず、全体でも34.8%にとどまっており、日本よりは罹患率が高くポピュラーな海外の調査ですら、受診から診断までの期間が7年以上との報告もある。
現在の治療法は抗生物質の内服・外用、切開排膿(切って膿を出す)、手術(病変部の切除および縫合または植皮)があるが、林氏によれば、抗生物質には薬剤耐性菌が出る可能性があり、長期の慢性炎症に対する使用は不向きで、「他に治療法がある場合は他の治療をしたい」という。切開排膿は一時的には良くなるが、再び化膿する可能性がある。手術は病変部位をすべて取れば基本的には再発しないものの、淵から再発するリスクがあり、植皮する場合には瘢痕が残る難点もあることなどを説明し、現時点での治療は「必ずしも満足できるものではない」との認識を示した。
海外ではすでに承認され、「かなり積極的に使われている」という生物学的製剤。林氏は日本において使えるようになった場合、「膿が出て手術しなければならない患者には、まずは生物学的製剤を使って炎症を取り、腫れがなくなった状態で手術すれば、手術もしやすく、成功確率も高くなる。ハーレー1(臨床的重症度分類。1が最も軽度)なら従来治療で対応できると思うが、2以上の患者には積極的に使いたい」と期待を寄せた。