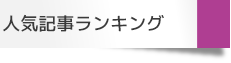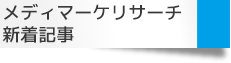■行政トピックス
社保審医療保険部会 10月26日
スイッチ化された処方薬、給付率下げに慎重論
社会保障審議会医療保険部会は10月26日、「スイッチOTC化された医療用医薬品に係る保険給付率の在り方」をテーマに議論した。厚労省が論点として提示したスイッチ化された処方薬の保険給付率引き下げに対して、日本薬剤師会をはじめ慎重論が大勢を占めた。
政府は、誰でもスイッチ化候補品を提案できる仕組みや、スイッチOTC薬の購入費用の所得控除を導入するなどしてセルフメディケーションを促進。製薬企業も長期収載品の売上げ下落に歯止めがかからず、スイッチ化による収益補完を模索している。こうした中で、スイッチ化された処方薬の保険給付率引き下げは、製薬企業の意欲にブレーキをかけかねず、社保審医療保険部会は難しい判断を迫られている。
医療保険部会における議論は、閣議決定された経済・財政再生計画・改革工程表に「16年末までに結論」と盛り込まれたのを受けたもので、厚労省は 1.スイッチOTC化された医療用医薬品に着目して、保険給付率を引き下げることについてどう考えるか 2.02年健保法改正法附則の「将来にわたって7割の給付を維持する」という規定との関係についてどう考えるか-と2つの論点を提示した。
日薬の森昌平副会長は、スイッチ化された処方薬の保険給付率引き下げに反対の立場で、「保険で使える高薬価な医薬品へのシフトが考えられ、安くてかつ安全性が確立した医薬品が医療保険の中で使いにくくなるのではないか。国はスイッチ化を進めているが、ブレーキがかかるのではないか。国民のためにはならない」と述べた。
法政大学の菅原琢磨経済学部教授は「財政効果を狙って、この議論が出てきているとすれば、メーカーは今後スイッチ化しないだろうから、短期的な効果は出ても、長期的な効果は見込めない」と指摘した。
日本労働組合総連合会の新谷信幸副事務局長は、02年健保法改正法附則の大原則を守る立場から、「特定の領域なり、特定の医薬品の分野で穴を開けていくことに対しては、先例となることを危惧している」と発言した。
一方、健康保険組合連合会の白川修二副会長は、「スイッチOTC化されたら保険適用から外すのが本来あるべき姿」とし、「それにとどまらず、一般類似薬、軽度の薬剤は保険収載から外すとか、フランスのように保険給付割合を変えるとか真剣に議論していかないといけない」と提案した。
日本経済団体連合会は10月18日に公表した提言で、「長らく市販品として定着している製品(湿布、うがい薬等)については、保険償還率の引き下げや保険給付の適用外とする」としており、望月篤社会保障委員会医療・介護改革部会長は「02年健保法改正法附則との関係を踏まえると保険給付率を引き下げるというよりは保険給付の対象外とした方が制度の安定性は確保されるのではないか」と述べた。
全国健康保険協会の小林剛理事長は「どのような考え方でスイッチOTC化された医薬品だけを対象とするのか、16年度診療報酬改定で湿布薬について対応したように処方量を勘案する必要がないかなど、もう少し詳細に議論していく必要がある」と述べた。
■記者会見
1.患者掘り起こしと新治療法開発でC肝撲滅へ
-ギリアド日本法人:折原祐治社長-
ギリアド・サイエンシズ日本法人の折原祐治社長は10月12日記者会見し、C型肝炎治療薬2剤に「特例拡大再算定」が適用され、4月に薬価が32%引き下げられたことを踏まえ、「そこそこの規模の会社が1つ消滅したようなインパクト」とコメント。「しかし、ギリアドはミッションに立ち返る会社だった」と述べ、日本にコミットし続け、潜在患者の掘り起こしとともに、現在治療選択肢のないアンメットニーズに対応していくことにより、C肝撲滅に強い意欲を示した。
ギリアドの今年4-6月のグローバルでの製品売上げは、前年同期比6%減と成長が鈍化。折原社長は「日本の状況もそうなってきているが、ハーボニー、ソバルディを待ち望んでいた患者が一通り治癒して、大きなうねりが一巡した」と説明した。
同社推計では、現時点での日本国内のC肝罹患者数は80万人、うち診断者数は60万人、うち肝炎専門医通院患者数は24万人。16年にインターフェロン(IFN)フリーの直接作用型抗ウイルス薬(DAA)のみによる治療を開始する患者数は10万人、IFNフリーが初登場した14年からのDAAのみによる治療患者数は累計18万人超と推計している。
折原社長は「予想では3年くらいかかって(19年)、診断者数とDAA治療患者数(治癒)がほぼ同じくらいになって、C肝が日本に無いということをWHOを含めて言われるようになりたい」と語った。
開発面では、C肝治療におけるアンメットニーズである 1.遺伝子型3型 2.リバビリンが使えない遺伝子型2型 3.DAA治療不成功例 4.非代償性肝硬変-に注力。現在ハーボニー(12週投与)は遺伝子型1型、ソバルディはリバビリンとの併用(12週投与)で2型に対応。日本のC肝患者の大部分は1型(約7割)か2型(約3割)だが、3型も2800人の患者がいると推定されており、ここに対してソバルディとリバビリンの併用(24週投与)を開発し、8月末に承認申請を行った。
リバビリンの副作用やリバビリン禁忌などでリバビリンが使えない遺伝子型2型に対しては、ハーボニーの適応拡大(12週)の第3相試験を実施中。DAA治療不成功例に対しては、ソバルディとベルパタスビル配合剤をリバビリンとの併用(12週と24週の2群)で第3相試験を実施中だ。
ベルパタスビルは、ハーボニーを構成するレジパスビルと同じNS 5A阻害剤だが、「レジパスビルと比較して変異を持ったウイルスに対してより強い効果を示す」(表雅之開発本部長)という。エプクルサという販売名で、1〜6型まで全遺伝子型に対応する治療薬として米国で6月に、欧州で7月に上市されている。
C型非代償性肝硬変に対しては、現在承認されているDAAは、C型代償性肝硬変(軽度)の適応のみで、治療薬が無い。ここに対しては、ソバルディとベルパタスビル配合剤(12週投与、リバビリン併用あり、なしの2群)の第3相試験を計画中だ。
■記者会見
2.売上高を20年に2倍、25年に4倍にしたい
-メルクセローノ:レオ・リー社長-
メルクセローノは10月28日、事業説明会を開催した。レオ・リー社長が登壇し、「我々は日本において最も尊敬されるオンコロジー領域と不妊治療領域における企業になりたい」とした上で「2020年の売上高は16年の2倍にする。25年は4倍にしたい」と述べた。なお、16年12月期の予想売上高は非開示としたが、本誌推定で200億円とみられる。
その成長を牽引するオンコロジー領域では抗PD-L1抗体アベルマブの開発を進めている。国内では非小細胞肺がんを対象に第3相、胃がんを対象に第3相、メルケル細胞がんを対象に第2相となっている。
リー社長は「17年に抗PD-L1抗体の最初の適応を日本市場に上市できるのではないか」と述べて、「メルケル細胞がんの適応で17年第2四半期ぐらいに承認を取得できればと考えている」と見通しを示した。
抗PD-L1抗体はアストラゼネカのデュルバルマブ、中外/ロシュのアテゾリズマブと開発が進んでいるが、他社との差別化についてリー社長は「それぞれ併用療法の考え方が違う。我々はファイザーと共同研究をしており、2剤、3剤の併用療法でも研究しているので、それぞれの企業が併用療法に対してどのような考え方を持っているか、そこに焦点を当ててみると興味深いことが分かるのではないか。我々の併用療法については第1相に進み次第、情報提供したい」と述べた。
不妊治療領域では不妊治療薬のゴナールエフ、セロトタイドに加えて、9月にワンクリノンを発売。またオビドレルが9月に承認を取得し発売準備中となっている。他方、不妊治療に係わる医療機器では自動ガラス化保存機器のガビ、インキュベーターのジェリなどの上市準備を進め、17年の発売を予定している。
不妊/内分泌領域事業部の池田秀子事業部長は「私たちにとって大事な大事な1年となる。これからも不妊に悩むカップルのみなさんを不妊治療サイクルのあらゆる段階でサポートするというメルクのグローバルなミッションを国内でも加速させたい」と語った。
■セミナー便り
1.リクラスト、BP製剤市場の5〜10%目指す
-旭化成ファーマ:堀一良社長-
旭化成ファーマは10月18日、骨粗鬆症治療薬リクラスト(ゾレドロン酸)の新製品説明会を開催し、同社の堀一良社長は「年1回という際立った特長がある。患者のライフスタイルに合わせた新たな治療選択肢を提供できるものと期待している」と語った。リクラストは年1回投与のビスホスホネート製剤。ノバルティス社創製で、旭化成ファーマが10年に国内における骨粗鬆症治療薬としての独占的開発および販売権を取得した。今年9月に承認を取得した。
製品売上げ見通しについて堀社長は「薬価が付いていないので確実なことは言えないが、患者ベースでビスホスホネート製剤市場の5〜10%(12万〜24万人)くらいは目指すべきところではないか」と目標を語った。
なお、海外ではノバルティス社が販売し欧米を含む115カ国で承認を取得しており、海外でのピーク時売上高は2010年度510億円であった。
新製品説明会では鳥取大学医学部保健学科の萩野浩教授と沖本クリニックの沖本信和教授が登壇した。萩野教授はリクラストの国内第3相AK156-Ⅲ-1試験(ZONE試験)を解説。主要評価項目のカプランマイヤー推定における24カ月間の新規椎体骨折の累積発生率についてプラセボ群に対し優越性が示されたほか、萩野教授は特筆すべき点として非椎体骨折の発生率を挙げ、「国内で行われた骨粗鬆症治療薬の試験の中で非椎体骨折についてダブルブラインドで前向きに有意に証明したのはこれが初めて」と語った。
副作用では頻度の高い発熱に着目し「これは急性期反応でビスホスホネート製剤に共通するものだが、特に多い量が入るとなりやすい。リクラストは年1回投与で量が多いので出やすい。比較的短期間に治まり2回目の投与からは出にくいが、患者さんには注意していただくところだ」と注意を促した。
他方、沖本院長は年1回の投与がとりわけ適する患者像を解説し、大腿近位部骨折を起こし2次骨折を予防したい患者や、通院困難な患者を挙げた。年1回投与のメリットとして「これまでの製剤は煩雑であった」と説明。経口のビスホスホネート製剤は服薬後少なくとも30分たってからその日の最初の食事を摂り食事を終えるまで横にならないなど用法・用量上の注意がある。その煩雑さを解消するため4週に1回の点滴静注ボナロン(アレンドロン酸)、月1回静注のボンビバ(イバンドロン酸)が発売されたが、病院やクリニックに何度も通うのが大変な患者もいるのだという。
そこで年1回の製剤が登場した。
加えて、沖本院長は骨粗鬆症治療薬は骨折予防を目的としているため「良くなったとなかなか実感できないのでやめてしまう方が多い。その意味ではこの薬も実感できないかもしれないが年1回だから導入しやすい」と指摘した。また、2次骨折予防を目的に急性期病院、リハビリテーション病院、かかりつけ医が連携して、そのどこかで年1回の骨粗鬆症治療薬が投与できれば、薬物治療の開始と継続100%が目指せるのではないかと期待を示した。
ビスホスホネート製剤の重大な副作用である顎骨壊死(頻度不明)について、リクラストは国内第3相において顎骨壊死およびそれ以外の骨壊死の発現割合はプラセボ群と同程度であったが、類薬と同様に注意喚起する必要がある。
沖本院長は顎骨壊死について「現実に数が多いかというと、色々な言い方があって、大したことないと言う先生もいるが、ただ、おふくろや親父がなったら大変なことだから、それに手を打つ必要がある」と指摘。「広島県呉市では医師会と歯科医師会が話し合って、ビスホスホネート製剤を使う時はできるだけ歯科医やかかりつけ医に紹介しようということでいま動いている。歯科医は診ていたら顎の骨があまりにも薄いし骨粗鬆症ではないかと医師に紹介する形で逆連携している。投与前と投与後に歯科医と医師との連携をしっかりするのが一番重要ではないかと思うし、現実、それは明日からでもできることだろう」と対策の具体例を示した。
■セミナー便り
2.武田薬品との共同研究で有望な成果
-京大iPS細胞研究所:山中伸弥所長-
山中伸弥京大教授(京大iPS細胞研究所=CiRA所長)は10月24日の第1回再生医療産学官連携シンポジウムで講演し、iPS細胞技術の臨床応用に向けた武田薬品との共同研究(T-CiRA)について「すでにいくつかの有望な成果が出ている」と明らかにした。
T-CiRAは、武田薬品とCiRAの研究者が共同で 1.神経堤細胞に注目し腎臓、消化器、神経系などに関連する疾患への創薬応用および細胞移植治療応用のための基盤技術開発研究 2.筋萎縮性側索硬化症(ALS)治療薬開発 3.1型糖尿病に対する再生医療の開発。2型糖尿病に対する創薬研究 4.新しいがん免疫療法の開発 5.筋ジストロフィーやミオパチーなど筋疾患に対する治療薬の創出および疾患モデルの研究 6.心疾患創薬プラットフォームの開発と心不全の新規治療開発-の6つのプロジェクトに取り組むもの。
T-CiRAについて山中教授は「従来の企業との共同研究は、企業の研究者が大学にやって来て、一緒に研究を行うやり方だったが、全く逆で大学の研究員が武田薬品の湘南研究所に行って研究を行うやり方」と説明。結果として「従来できなかったようなノウハウを取り込むことができ、リソースを有効に使える」と強調した。
iPS細胞のポテンシャルについては、「薬の開発が本当の意味での使い方」との認識を示し、「再生医療は一過性の医療であり、100年後も今わたしたちが志しているような再生医療が同じように行われているとは思っていない。もっといい治療ができていると思う。一方、薬の開発においてはiPS細胞の利用は今後何十年と続いていくと考えている」と語った。
iPS細胞を用いた再生医療は、患者本人由来の自家移植と、他人由来の他家移植の2つに分けられる。自家移植では、理化学研究所の高橋政代氏をプロジェクトリーダーとした加齢黄斑変性患者への移植手術が最初で、実施から2年が経過したが、「手術をした方の目はそれ以降、一切眼球内への抗VEGF抗体の注射をしていないが、視力の低下がぴたっと止まっていると伺っている」と説明。
一方、他家移植では、CiRAは昨年8月、臨床用iPS細胞の出荷を開始した。「研究用も決して簡単ではなかったが、臨床用を作るのは想像よりもはるかに大変だった。たくさんの人がお正月もお盆も返上して失敗に失敗を重ねた」とした上で、「作製にかかわった50人のうち、京大の正規教員は5人だけ。あとの45人は有期雇用であるということが、日本の国立大学の持っている課題の一つである」と指摘した。
■セミナー便り
3.軽度の認知症なら適用の範囲
-順天堂医院脳神経内科:服部信孝教授-
アッヴィ合同会社は10月27日、記者説明会「パーキンソン病薬 物治療の新時代」を開催し、順天堂大学医学部附属病院順天堂医院脳神経内科の服部信孝教授が講演した。
アッヴィは9月、進行期パーキンソン病治療薬デュオドーパ配合経腸用液を発売。同剤はレボドパ含有製剤を含む既存の薬物療法で十分な効果が得られないパーキンソン病の症状の日内変動(ウェアリングオフ)の改善を効能・効果とし、専用の小型携帯型注入ポンプとチューブを使い胃ろうを通じ空腸に直接投与する。ピーク時売上高は10年度50億円。予測本剤投与患者数は961人となっている。
服部教授は経腸用液のメリットについて「極端な例だが、経口投与でデュオドーパが効いている時間が1時間だとすれば16時間起きているとすると16回服用することになる。経口投与は必ず胃を通るが空腸に直接投与できれば胃内容物の排出遅延をクリアすることができる。あくまでゴールドスタンダードであるレボドパの血中濃度をいかに一定に保つかということに対して、空腸にカテーテルを挿入することですべての問題を解決する」と紹介した。進行期パーキンソン病では服薬回数が多くなることのほか、胃など消化管の動きが悪くなり、胃内容物の排出遅延が起こり、薬が小腸で吸収されるタイミングにばらつきが生じ、薬物血中濃度を安定して維持することが困難といった課題があった。
治療選択肢にはDBS(脳深部刺激療法)もあるが、服部教授は差別化について「DBSは認知症があると適応にならない。デュオドーパは操作がシンプルなのでポンプ操作ができる範囲内の軽い認知症なら適応の範囲と考えていいだろう」と述べ、国内で知見を集積してデュオドーパ配合経腸用液が適した患者クラスタを明らかにしていく必要があると説いた。
講演は全国パーキンソン病友の会東京支部の高橋治雄副会長も登壇し、「私の場合は(一日の服用回数が)朝昼晩に食前食後と2回ずつありまして、朝と昼、昼と晩の食間、そして就寝間際に1回と、そういう形で全部で9回飲んでいるので、絶えず薬を飲んでいる感じです。飲み忘れた時もありますが1日薬がないととても行動できない」と服薬の状況を説明。「服部先生が説明された薬もそうですがこれから新しい薬がどんどん開発されてくる。iPS細胞や遺伝子治療にも期待している」と述べた。
服部教授によると、パーキンソン病は無動(動きが緩慢になること)、振戦(ふるえ)、筋固縮、姿勢反射障害を主な症状とし、国内患者数は推計15万人という。
■学会トピックス
1.SGLT2阻害薬使用調査を発表
-第30回日本臨床内科医学会-
第30回日本臨床内科医学会が10月9〜10日、都内で開かれ、「糖尿病者に対するSGLT2阻害薬の使用状況〜アンケート調査」が発表された。同調査は、今年5〜7月に実施され、内科医2万4000人にアンケートを配布、1908人の回答を得た。その結果、SGLT2阻害薬の処方経験のある医師は1585人と83.1%に上り、処方理由の1位は「体重減少」だった。ただ、DPP-4阻害薬かSGLT2阻害薬のどちらを先に使用するかは、66.3%がDPP-4阻害薬と回答、15.9%のSGLT2阻害薬を大きく上回った。
SGLT2阻害薬を処方するきっかけ(複数回答)は、「処方にメリット」50.0%、「学会・研修会」49.7%、「MRの訪問・説明」43.4%、「イメージ」37.1%、「製薬会社の研究会」28.4%、「論文」19.7%-の順。
処方する理由(複数回答)は、「体重減少」が85.6%でトップ。「HbA1cの低下」も83.4%と高かった。次いで「血糖値の低下」67.4%、「肝臓に負担をかけない」31.4%、「脂肪肝の改善」25.8%、「既存の薬では不十分」23.4%-などとなっている。
注意する副作用(複数回答)は、脱水84.6%、尿路・性器感染症75.5%、多尿・頻尿38.4%-などであった。
一方、処方経験のない医師に理由(複数回答)を尋ねたところ、「長期的な効果・安全性に疑問」44.3%、「対象者がいない」35.9%、「安全性が確立されていない」33.7%、「エビデンスが足りない」22.0%、「薬価が高い」17.0%-などとなった。今後、処方を増やしていく医師は糖尿病専門医で79.0%、非専門医で76.4%となった。
■学会トピックス
2.競合激化する新規抗凝固薬でセミナー
-第30回日本臨床内科医学会-
10月9〜10日開かれた第30回日本臨床内科医学会では、新規抗凝固薬に関するセミナーが開かれた。
このうち、第一三共共催の「心房細動の治療戦略〜DOACをいかに使いこなすか」で講演した住吉正孝・順天大練馬病院教授(循環器内科)は、ワルファリンについて 1.出血を助長する副作用があり、特に頭蓋内出血を起こした場合は致命的となること 2.納豆や青汁などある種の食物や消炎鎮痛剤や抗生物質などとの相互作用があること 3.定期的な採血による抗凝固モニタリングで用量調節が必要なこと-を挙げ、「非専門医にはハードルの高い薬剤である」と指摘。
その上で、「新規抗凝固薬は、ワルファリンの短所を改善する」と位置付け、上市されている4種類の薬剤の中で「安全性からみた高齢者・低体重・CKD患者への使い分けでは、エドキサバンがバランスのとれた薬剤ではないか」と評価した。
また、「実地医家を対象とした非弁膜症性心房細動患者の脳卒中および全身性塞栓症に対するリバーロキサバンの有効性と安全性に関する登録観察研究(GENERAL)」について講演した国立循環器病研究センターの草野研吾・心臓血管内科部門不整脈科部長は、目標症例数を5000例とした背景について、「高齢化社会において非弁膜症性心房細動患者が増加しており、循環器専門医のみならず地域の実地医家(かかりつけ医)が診療する機会が多くなっている」と説明。
GENERALは、17年3月に症例登録期間が終了し、18年9月までに観察研究が行われることになっているが、「実地医家の心房細動患者像や診療実態が明確になるとともに、脳梗塞予防効果の向上が期待される」と述べた。