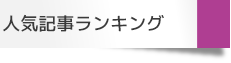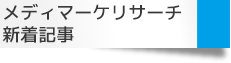■行政トピックス
1.中医協薬価専門部会12月12日「消費税引上げに伴う薬価改定の骨子」が決定
■セミナー便り
1.オプジーボ併用腎細胞がん1次治療、「インパクト大」-慶大医学部泌尿器科:大家基嗣教授-
2.再発ALLを寛解へ ビーリンサイト-国際医療福祉大学三田病院:小林幸夫副センター長-
3.「不適切なデータ処理はすぐに見破られる」-大阪市立大学:新谷歩教授-
■行政トピックス
1.中医協薬価専門部会12月12日
「消費税引上げに伴う薬価改定の骨子」が決定
中医協薬価専門部会は12月12日、「消費税引上げに伴う薬価改定の骨子」を取りまとめた。最大の焦点となる改定時期については、「最終的には政府の予算編成過程で定まることになる(12月17日の大臣折衝で、19年10月改定が確定)」としつつ、「中医協としては実勢価改定と消費税引き上げ相当分の転嫁を同時に行うことが自然である」との認識の下、適用すべき算定ルールについて検討を行ってきた。その結果、新薬創出等加算を通常通り実施するなど、製薬業界の要望に沿った内容で決着した。
12月5日の同部会では、関係業界からの意見聴取を実施。日薬連の手代木功会長(塩野義製薬社長)は、「18年度の医薬品価格調査はあくまでも19年10月の消費税率引き上げへの対応を目的とした特例的な調査であり、その目的以外に調査結果を用いることがあってはならない。消費税率引き上げに伴う薬価改定は19年10月に実施されるべき」と改めて強調。
また、「通常改定で薬価が維持される品目の薬価が引き下がるのは妥当ではない」として、新薬創出等加算、基礎的医薬品(不採算品再算定、最低薬価になる前の薬価を下支えする制度)、最低薬価(剤形ごとにかかる最低限の供給コストを確保するため、成分に関係なく剤形ごとに設定しているもの)を通常どおり実施するよう要望。
一方、「2年に1回の通常改定とは位置づけが異なる」として、長期収載品に係る追加的な引き下げや再算定、新薬創出等加算の累積額の控除などは実施しないよう求めた。
12日にまとまった骨子を見ると、新薬価は「税抜きの市場実勢価格×(1+消費税率)+調整幅」の消費税率を10%で計算するとともに、改定前薬価の108分の110を乗じた額を超えないこととした。基礎的医薬品、最低薬価ルールは適用。新薬創出等加算も適用する(ただし、18年度改定以降に後発品が収載されるなどして対象から外れた品目は、加算の対象としない)。また、同加算の累積加算額の控除は、市場実勢価格から追加的に薬価を引き下げる仕組みであり、20年度の通常改定で実施することとした。
新薬創出等加算見直しで火花
なお、5日の部会では、製薬協の中山譲治会長(第一三共会長兼CEO)が20年度薬価制度改革に向けた課題に言及。新薬創出等加算について、品目要件の拡充と企業要件の見直しを求めるとともに、イノベーションの適切な評価について「優れた医薬品が持つ多面的な価値を適切に評価し、その価値を薬価に反映する仕組みづくりが必要である」と訴えた。
新薬創出等加算についてEFPIA japanのオーレ・ムルスコウ・ベック会長(ノボ ノルディスクファーマ社長)は「要件を再検討し、患者にとっての追加的な有用性の評価、例えば有効性・安全性の向上だけでなく、医薬品の投与の利便性等に対する評価も考えてほしい」と要望した。
これに対し、支払側の幸野庄司委員(健保連理事)は、18年度薬価制度抜本改革で導入された、長期収載品の価格を後発品の価格によって設定し、徐々に引き下げていくG1、G2ルールに触れ、「適用されるまでに特許が切れてから10年もかかり、スピード感に欠ける。新薬創出等加算の制度を見直すのであれば、特許が切れたものも速やかに撤退するという方向と同時にセットで議論していくべき」と切り返した。
■セミナー便り
1.オプジーボ併用腎細胞がん1次治療、「インパクト大」
-慶大医学部泌尿器科:大家基嗣教授-
小野薬品とブリストル・マイヤーズスクイブは12月7日、8月に承認を取得した腎細胞がん1次治療での抗PD-1抗体オプジーボ(ニボルマブ)と抗CTLA-4抗体ヤーボイ(イピリムマブ)の併用療法に関するプレスセミナーを開催した。慶大医学部泌尿器科の大家基嗣教授は、承認の根拠となった国際共同第3相CheckMate-214試験成績を解説し、「教科書やガイドラインを書き換える大きなインパクトを与えた」と述べた。
腎細胞がんは早期発見された場合は外科療法が行われ、予後も良いが、転移が見つかった場合は非常に予後が悪いのが特徴で、薬物療法の対象となるという。腎がん診療ガイドラインによれば、薬物療法はステージ4の治療に登場する。
大家教授によれば、腎細胞がんの薬物療法はかつて、主にIFN製剤が使われていたが、骨転移や肝転移には効果がなく、難治性の中の難治性がんとされていた。それが2008年1月に第1世代TKIとなるネクサバール(ソラフェニブ)、4月にはスーテント(スニチニブ)と、相次いで分子標的薬が承認されたことで、腎細胞がんの歴史が完全に変わったという。その後10年にはmTOR阻害剤のアフィニトール(エベロリムス)やトーリセル(テムシロリムス)も承認され、第2世代TKIのインライタ(アキシチニブ)、パゾパニブ(ヴォトリエント)と続き、治療薬のラインナップが増えた。そして16年のオプジーボの承認は長らく黄金ラインとされた1次治療スーテント、2次治療インライタのシーケンスを変えることとなり、新たな時代を迎えている。
CheckMate-214試験は腎細胞がん1次治療でのニボルマブ/イピリムマブ併用療法の有効性をスニチニブを対照に検証したもの。未治療の進行または転移性腎細胞がん患者を組み入れた。主要評価項目に設定されたのは、IMDC分類による中および高リスク患者における、無増悪生存期間(PFS)、全生存期間(OS)および奏効率(ORR)だった。このうちOSについては、スニチニブ群に対するニボルマブ/イピリムマブ併用群のハザード比は0.63(99.8%信頼区間0.44~0.89)、p<0.0001で、併用群で有意な延長が示された。OS中央値はスニチニブ群26.0カ月に対して併用群は推定不能だった。ORRも、スニチニブ群27%、併用群42%で有意差が付いた(p<0.001)。一方PFSは、2群間に有意差は認められなかったHR: 0.82(99.1%Cl[0.64.1.05]、p=0.0331)。安全性の面では、肝毒性、内分泌障害、胃腸毒性、肺毒性(間質性肺炎)などが多く発現した。胃腸毒性、肝機能障害は主にイピリムマブ、内分泌障害は主にニボルマブで多く報告されている。大家教授は、治験薬毒性による投与中止例が、スニチニブ群11.8%に対して併用群は24.5%と多いことに触れ、併用療法には重篤な副作用による中止という二面性があると語り、免疫関連有害事象には常に気を付けなければいけないとした。国内ではこうした試験結果を基に一変申請され、18年8月に化学療法未治療の根治切除不能または転移性の腎細胞がんの適応が承認されている。大家教授はCheckMate-214について、「OS の延長以上に、CR(完全奏効)が9%あったことが臨床家にとって衝撃だった」と振り返った。
大家教授によると、がん免疫療法薬を主体とした併用療法で腎細胞がん1次治療を目指した第3相試験が数多く存在する。そのうち抗PD-1抗体キイトルーダ(ペムブロリズマブ)とインライタを併用したKEYNOTE-426試験、抗PD-L1抗体バベンチオ(アベルマブ)/インライタ併用のJAVELIN RENAL101試験は10月に主要評価項目の達成を発表している。
■セミナー便り
2.再発ALLを寛解へ ビーリンサイト
-国際医療福祉大学三田病院:小林幸夫副センター長-
再発・難治性のB細胞性急性リンパ性白血病(ALL)の新薬ビーリンサイト(ブリナツモマブ)の発売を機に、アステラス・アムジェン・バイオファーマは12月10日にメディアセミナーを開いた。講演した2人の専門医は、同剤が再発・難治例を寛解に導き、根治が期待できる造血幹細胞移植へとつなげられると指摘した。
同剤は「二重特異性T細胞誘導抗体」と呼ばれ、B細胞に発現するCD19抗原とT細胞のCD3の双方に結合し、T細胞をB細胞性腫瘍に誘導して抗腫瘍効果を発揮する。
国際医療福祉大学三田病院悪性リンパ腫・血液腫瘍センターの小林幸夫副センター長によると、ALLは小児に多く、最も高い1~4歳の発症率は人口10万人あたり8例弱、成人では10万人あたり1例程度となっている。標準治療は化学療法(寛解導入・地固め・維持)、分子標的薬、造血幹細胞移植で、患者背景に応じた治療により小児では約80%、成人では15~35%が長期生存する。
言い換えれば、特に成人では再発・難治例が多いこととなる。小林氏は、寛解後の持続期間が短いことや再発後の治療法が確立していないことが課題だとして、ブリナツモマブについて「再発後に寛解を再度得られる治療。根治を目指す移植につなげられる」と期待感を示した。
小児の再発・難治性ALLに関しては、国立病院機構名古屋医療センター臨床研究センターの堀部敬三センター長が講演し、同剤で血液学的完全寛解が約40%に得られること、化学療法と比べて安全でQOLが維持できることを評価した。
その上で、ブリナツモマブの位置付けとして「再発直後は従来の化学療法や抗体薬を用い、腫瘍量が減少したところで使用して移植につなげる」「副作用で化学療法が施行しにくい患者にも使える」ことを挙げた。ただし、小児の試験で無再発生存期間が4カ月(中央値)と短いため、「移植への橋渡しとしての有用性は検討を要する」とも指摘した。
■セミナー便り
3.「不適切なデータ処理はすぐに見破られる」
-大阪市立大学:新谷歩教授-
日本医療研究機構(AMED)が12月5日に開催した2018年度研究公正セミナーで大阪市立大学の新谷歩教授は「統計解析から見た研究不正事例」と題して講演。メンデルの法則から始まり、ディオバン事件の臨床研究試験データや厚労省池田班の子宮頸がんワクチンデータなどで不正が疑われた事例を示しながら不正を見抜く方法を解説し、「不正や捏造はすぐに見破られる」と強調した。
統計学の父とも言われるフィッシャーがメンデルの分離の法則は得られた実験データの数値が理論値とあまりにも一致しており、使えるデータだけが取り出された可能性があると指摘したことを挙げて、新谷教授は「自然なデータにはランダム性があり、‘Too Good To be True(話がうますぎる)’の好例」とした。
ディオバンの臨床試験成績においては、京都大学の由井芳樹氏による、血圧値の平均と標準偏差が二群間でほとんど同じ値であるのはかえって不自然であるとの指摘が事件発覚の発端であったと紹介。また、鹿児島大学・信州大学が行った子宮頸がんワクチンに関するHLA(白血球型)調査は両側F検定で有意差あり(p=0.0162)としたのに対して、京都大学の松田文彦氏は検定回数の多重性の調整を行うと有意差はない(p=0.1625)と指摘した事例を示した(ここでのF検定は分散分析ではなく、直接確率計算法と推測される)。
さらに、無作為化比較試験のデータに不正・捏造がないかを見破るためのチェックポイントとして(1)数値の偏りやデータの最後の位の数値の分布を検定で確認すること(2)背景因子に対する均質性検定のp値が一様に分布しているか―を挙げた。また、比較的少数例の動物実験データでは、検定の結果に対応しない不自然なエラーバーの長さ、死亡までの日数などで最後の位の数値に0が多いなどのチェックポイントを具体例で示した。
臨床試験の統計解析において、観察研究では傾向スコアなどを用いた多変量回帰モデルにより交絡因子を調整しないと誤った結果になる恐れがあるとし、無作為化試験に限らず、試験前に解析計画書を作成し、それにしたがって解析を行って結果を報告することが、不適切なデータ処理の防止策であると指摘した。