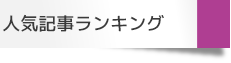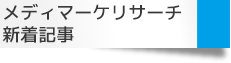■セミナー便り
1.ワクチン拡充「国を守る上で重要」
-東京病院:永井英明臨床研究部長-
国立病院機構東京病院の永井英明臨床研究部長は9月5日、サノフィ主催の高齢者のインフルエンザワクチン接種に関するメディアセミナーで「製造方法や接種方法が多岐にわたる体制が国を守る上で重要だ」と強調した。
米国は多種多様なワクチンが使用可能である一方、日本は4価不活化ワクチンの標準用量の1種類しかなく4価遺伝子組換えワクチンや高齢者用の3価不活化ワクチンの高抗原量は使用できない。
加えて、インフルエンザワクチンの定期接種の対象者が(1)65歳以上(2)60~64歳で心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能に障害があり身の回りの生活を極度に制限される人またはHIVにより免疫の機能に障害があり日常生活がほとんど不可能な人-に限られていることにも言及。(2)に関しては身体障害者1級相当の障害に限られ条件が厳しいほか、肝疾患、代謝性疾患、血液疾患が含まれていない。永井部長は65歳以上は50%程度と接種率が伸び悩んでいることから全額無料が望ましいとしたほか、65歳未満の対象疾患を拡大し、60歳未満でも「基礎疾患のある方はいずれも受けられるように対象を広げて公費助成してもらいたい」と提言した。高齢になるほどインフルエンザ関連死亡が増加するほか、インフルエンザは虚血性心疾患、COPD、糖尿病など慢性基礎疾患を悪化させることが知られている。インフルエンザワクチン接種による予防効果は認められており、特に高齢者に対しては積極的に接種すべきとした。
永井部長は「インフルエンザ、肺炎球菌、帯状疱疹、この3つの高齢者用ワクチンを駆使し入院などさせないで高齢者を元気な状態に維持することが医療費削減に役立つ」と語った。
■セミナー便り
2.高齢者は2種類の肺炎球菌ワクチン接種が理想
-慶大医学部:長谷川直樹教授-
特に慢性肺疾患、喘息、慢性心疾患、糖尿病などの基礎疾患を有する高齢者は、定期接種の多糖体ワクチンに加えて、任意接種である結合型の、2種類の肺炎球菌ワクチンを接種することが望ましい-。慶応義塾大学医学部感染制御センターの長谷川直樹教授は9月6日、ファイザーが主催したプレスセミナーで、特にハイリスク高齢者への沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン(プレベナー13)接種を推奨した。
長谷川教授によれば、日本では肺炎で亡くなる人の97.9%が65歳以上の高齢者であり、また、死亡にまで至らなくとも、高齢者の肺炎は日常生活動作の低下、心身機能低下、嚥下機能低下などの負のスパイラルをもたらし、健康寿命を大きく損ねることになるという。そして基礎疾患を有する65歳以上の肺炎発症率比は、海外データではあるが、基礎疾患無しを対照群として、COPDで6.6倍、喘息4.6倍、慢性心疾患3.8倍にリスクが上がることが示されている。
肺炎の起炎菌として最も多いとされる肺炎球菌に対する2種類のワクチンのうち、多糖体ワクチンである23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン(ニューモバックスNP)は14年から定期接種に組み込まれている。しかしその効果持続はおおよそ5年間で、徐々に抗体価が落ちる。一方、14年6月に高齢者への適応拡大が承認されたプレベナー13は13価、つまり23価であるニューモバックスが23種類の血清型抗原を含むのに対して、13種類の血清型抗原を含むに留まるのだが、終生免疫を付けることができるという特長がある。長谷川教授はこうした両者の特性を説明し、「2種類を打てるのが理想」と述べた。
プレベナー13は現在、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会で高齢者への定期接種化が検討されている。
■セミナー便り
3.便秘症治療薬リンゼス「腹痛や腹部膨満感の改善に期待」
-兵庫医大:三輪洋人主任教授-
兵庫医科大学内科学消化管科の三輪洋人主任教授は9月11日、アステラス製薬主催の慢性便秘症治療薬リンゼスに関するメディアセミナーで同剤の特長について「薬剤の相互作用が少なくお年寄りに使いやすいだろう。それに腹痛や腹部膨満感の症状が強い方にはリンゼスの方が効果が期待できる」と語った。安全性の面では忍容性が高いと評価し、主な副作用である下痢や軟便は用量の調節で対応可能だとした。米国では12年の承認以降200万人以上に使用されている。
国内第3相試験では主要評価項目の投与1週間におけるSBM(自発的排便)頻度の週平均値の変化量がプラセボに対し統計学的有意に増加した。副次評価項目の便形状の週平均値の推移ではブリストル便性状スケールのタイプ4(表面がなめらかでやわらかいソーセージのような便、普通便)になることが示されている。副次評価項目の腹部症状の改善効果でもプラセボに対し有意に改善。CSBM(残便感のない自発的排便)頻度の週平均値が3回以上であり、かつ排便習慣観察期におけるCSBM頻度の週平均値から1回以上増加した患者の割合は56週時点で76.9%だった。
日本の慢性便秘症治療薬市場は酸化マグネシウムが圧倒的なシェアを占める。酸化マグネシウムの特長は効果が高く用量を調整しやすく安価であること。ただし、一部腸管から吸収されるので高マグネシウム血症に注意が必要。腎機能低下患者や高齢者には定期的にマグネシウムを測定することが求められる。その中で、リンゼスは薬の相互作用も少なく忍容性も高く高齢者にも使いやすいという。
ただ、国内の第一選択薬に関して三輪主任教授は「わが国ではやはり酸化マグネシウムではないか」とした。米国で第一選択薬となっているポリエチレングリコールに関しては「酸化マグネシウムとどちらが良いか極めて甲乙つけ難い。薬価、有効性、飲みやすさなど様々な要素がある。基本的にはポリエチレングリコールは水に溶いて飲むので、日本にどれだけ受け入れられるかこれから考えていかないといけない」と述べた。リンゼスを第一選択薬にするには薬価が課題のようだ。
■セミナー便り
4.肺がん遺伝子変異検査、普及に課題
-国立がん研究センター東病院:後藤功一呼吸器内科長-
国立がん研究センター東病院の後藤功一呼吸器内科長は9月12日、ノバルティスファーマ主催のメディアセミナーで患者のがん細胞の遺伝子変異を一度に複数調べることができる次世代シークエンシング(NGS)について課題を語った。ノバルティスファーマのタフィンラーとメキニストの併用療法が3月に「BRAF遺伝子変異を有する切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌」の適応を取得。そのコンパニオン診断薬としてサーモフィッシャーサイエンティフィックのBRAF V600E遺伝子変異を特定するためのNGSを用いた診断システム「オンコマインDx Target Test CDxシステム」が4月に承認された。国内で初めてのNGSを用いた診断システムだ。後藤呼吸器内科長はNGSの課題のひとつとして「肺がんはサンプルが非常に小さいので、良いサンプルでないと解析の成功率が落ちる」と指摘した。
後藤呼吸器内科長が旗振り役を務める全国肺がん遺伝子診断ネットワーク(LC-SCRUM-Japan)では新鮮凍結の組織を使用しているので解析成功率は95%だが、日常臨床で使用されるホルマリン固定のサンプルでは核酸が壊れるので解析成功率は60%程度になるという。「NGSは高いキットで何回もできるわけではないので、解析成功率の低下が色々な影響を及ぼす」とした。
後藤呼吸器内科長はNGSにより検査した場合の料金、検査を実施する施設の要件など議論の余地があり、普及に向けて解決していくことは多いとしている。
なお、LC-SCRUM-Japanでは17年12月から肺がんの患者を対象として血液を用いた遺伝子解析を開始した。気管支鏡による組織採取が必要なく採血だけで済むのが特長。血中の腫瘍の遺伝子を解析してドライバー遺伝子を見つけ分子標的薬を選択する。血液による遺伝子解析は組織の場合と比べて感度が低く改善の余地はあるが、技術の進歩が早いことから後藤呼吸器内科長は「5年たつと血液だけで診断をして分子標的薬を投与するという新しい個別化医療の時代に入ってくるだろう」とした。
また、LC-SCRUM-Japanは今秋にも台湾が参加し、来年には中国も参加する予定だ。日本だけでなくアジアのスクリーニング基盤を構築するステージに入ってきている。
■セミナー便り
5.タグリッソ、一次治療での使用を推奨
-国立がん研究センター中央病院:大江裕一郎呼吸器内科長-
タグリッソ(オシメルチニブ)がEGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺がんに対する1次治療として8月21日、承認された。これを受けてアストラゼネカが9月13日に開催したプレスセミナーで、国立がん研究センター中央病院の大江裕一郎呼吸器内科長は「最初からタグリッソを投与することが、患者にとって一番メリットがある」と評価した。
第1世代(イレッサ、タルセバ)、第2世代(ジオトリフ)を投与した後、増悪した症例にタグリッソを使用するとしても、T790M変異が検出される症例は限られている。例えば、国立病院機構を中心とした49施設共同の前向き観察研究(REMEDY試験)では、第1、第2世代のEGFR-TKI治療で病勢進行を来した症例(236人)のうち、T790M 変異検査実施症例は199 人。そのうちT790M変異が検出された症例は61人だった。その中でタグリッソの投与がされたのは56人だった。タグリッソ投与に至った症例は23.7%である。また、タグリッソの1次治療を検討した第3相FLAURA試験でも、標準治療群(イレッサまたはタルセバ)で病勢進行した場合でT790M変異があり2次治療としてタグリッソが投与されたのは病勢進行した症例の26.7%だった。
タグリッソが1次治療でも使えるようになったことで、EGFR-TKIの投与順としては(1)第1世代→タグリッソ、②第2世代→タグリッソ、③第3世代の3パターンが考えられる。タグリッソの2次治療におけるPFSは10.1カ月(第3相AURA3試験)、1次治療では18.9カ月(FLAURA試験)で、第1世代、第2世代の1次治療でのPFSは順におよそ9~11カ月、11~15カ月であることから、それぞれのPFS中央値を単純に足すと、先に第1世代、第2世代を投与した後で第3世代を投与する方が長く見える。これについて大江氏は「うまく25%に入れば少し長いのかもしれないがそうでない患者も多い」とした。その上で1次治療からタグリッソを使うメリットとして毒性が第2世代と比べると「第3世代の方がはるかに軽度」であり、患者のQOLの観点でも第3世代に軍配を挙げて、「第3世代を最初から使うのが、患者にとってよりよい治療だと思う」と述べた。
また、タグリッソを1次治療に使用した場合の2次治療については、効果を検証したデータが全くないとして現時点での第1、第2世代の使用を否定し、殺細胞性抗がん剤の使用を挙げた。