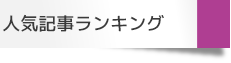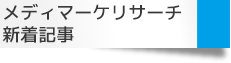■セミナー便り
1.ゲノム医療が今後のがん医療を大きく変える
-国立がん研究センター:中釜斉理事長-
国立がん研究センター(がんセンター)の中釜斉理事長は12月27日、厚労省・がんセンター・国会がん患者と家族の会共催「がんとの闘いに終止符を打つ‐がんゲノム医療フォーラム2016」で講演し、「がん患者の40%は治療効果が及ばず亡くなるケースがある。その約半数は早期発見・早期治療、均てん化によって救うことができるが、残る20%の難治がん・希少がん・進行がんはなかなか難しい」とがん医療の限界を説明。その上で、近年発展著しいゲノム医療によって、がん医療が「がんとの闘いに終止符を打つ」転換点を迎えていることを指摘した。
近年遺伝子に異常が起きることで、がんが発生・悪性化する仕組みが次々に解明されており、EGFR阻害剤、ALK阻害剤、ABL阻害剤といった元となっているゲノム異常をターゲットとした治療薬の開発が進んでいる。
中釜理事長は、がんゲノム医療の特徴として、例えば肺がん以外にもALK遺伝子異常を持つがん種が複数あることを挙げ、「肺がんで効いたのであれば、同じようなタイプの遺伝子異常を持っている別の臓器のがんでも、その治療薬が効くのではないかということが容易に想定できる」と、臓器横断的に効果を示す可能性を指摘。「従来は開発が難しかった希少がん、小児がんでも、こうした捉え方をすることによって新しい薬の開発が進むことが期待される」と続けた。
すでにがんセンターでは、患者から検査試料を採取し、ゲノム検査に基づき治療法を選ぶ研究(TOP-GEAR)を実施中で、「非常に希少ながんを含めてゲノム解析は可能なので、検査試料を採取できる患者であれば、さまざまながん種で、ゲノム異常に応じた治療法を選択できる」と説明した。
中釜理事長は、今後のがんゲノム医療の発展を支えるキーワードとして、1.希少がんにも対応できるよう、日本中のコアとなる医療機関のネットワークづくり 2.大きな蓄積データに対応できるよう、人工知能や知識データベースの活用推進 3.ゲノム情報に基づく創薬体制-の3点を挙げた。また、「ゲノムの異常は人種によって差があることが分かっており、日本のがん患者に適したゲノム医療の仕組みを構築する必要がある」との認識を示した。
厚労省、がんゲノム医療計画を策定へ
同フォーラムに出席した塩崎恭久厚労相は、「がんゲノム医療の計画的な推進を厚生労働大臣に行わせる」との安倍晋三総理の指示の下、「日本中の英知を結集し、17年の夏をめどにがん医療に革命を起こすプロジェクトを策定する」との方針を明らかにした。
フォーラム後に会見したがんセンターの間野博行研究所長は「日本のがん研究者として、厚労省ががんゲノム医療を大きなプロジェクトとして進めますという態度を示したということはすごく画期的で、非常にありがたいと思っている」と述べた。
セミナー便り
2.ハーボニー、実臨床でも好成績
-武蔵野赤十字病院:泉並木院長-
武蔵野赤十字病院の泉並木院長(消化器科)は12月21日、ギリアド・サイエンシズ主催のメディアラウンドテーブルで講演し、C型慢性肝炎治療薬ハーボニー配合錠(一般名レジパスビル・ソホスブビル)の市販後の臨床データを紹介した。実臨床でも、患者の年齢やインターフェロン治療歴などにかかわらず、100%に近いSVR(持続的ウイルス陰性化)率が得られた。今後の課題として、SVR後の発がんを注視する必要性や他の直接作用型抗ウイルス剤(DAA)が治療不成功だった場合にハーボニーなどの治療を行うかどうかの判断を挙げた。
同院では16年9月までにジェノタイプ1型C型慢性肝炎患者274例に使用した。投与終了後12週を経過した97例におけるSVR率は97.9%で、国内第3相試験の成績(100%)とほぼ同様であった。泉氏は「高齢患者が多いのがわが国の特徴だが、ウイルス消失は治験通りの結果であった」と総括した。
全国の赤十字病院のデータでも、投与終了4週後に判定した780例のSVR率は99%で、治療歴や代償性肝硬変、投与前のNS5A領域のY93H変異の有無による差は認められなかった。SVRが得られなかった症例に、治療歴の有無や投与前の薬剤耐性などの特徴は見られなかった。ソホスブビル耐性に関連するNS5B領域の変異も検出されなかった。
今後の課題として泉氏は「ウイルスが消失しても安心せず、定期的に超音波検査をすることが重要だ」と述べ、SVR後の肝発がんスクリーニングを挙げた。
別のDAAであるダクラタスビル/アスナプレビルで失敗後の治療選択も課題だとした。患者の発がんリスクによっては速やかに次の治療を行う選択肢もあるが、仮にハーボニーを投与してもSVRを達成できなかった場合、「より複雑な変異が生じて、今後出てくる薬剤が効かなくなるリスクがある。どのような患者は治療を待機した方がよいかの指針を整備したい」との見解を示した。
学会レポート
医療におけるビッグデータの可能性を紹介
-日本臨床疫学会 発足記念講演会-
「クリニカル・マインドとリサーチ・マインドを持つ医療者による質の高い研究を、ビッグデータを活用した研究などの振興と研究人材育成を通じて推進し、現在の医療が直面する諸課題の解決に貢献する」をミッションとして16年に発足した日本臨床疫学会は同年12月18日、東京大学弥生講堂で発足記念講演会を開催した。午後に開催された「ビッグデータを活用した臨床研究の現状と展望」と題するシンポジウムでは堀田知光国立がん研究センター名誉総長を座長に、慶應義塾大学医学部の宮田裕章教授、東京大学大学院医学系研究科の康永秀生教授、京都大学大学院医学研究科の川上浩司教授が講演した。
「Big data時代における臨床データベースの活用」について講演した宮田氏は、免疫チェックポイント阻害剤を例に挙げて、NCD(National Clinical Database)、DPC、レセプトデータに基づいて「3500万円を使って治療して、予後が10年延びるのか、2カ月しか延びないのか、実態に基づきながらサステイナブルな医療を考える時代に来ている」との認識を示した。
NCDは2010年に手術症例のデータベースとして外科系臨床10学会が連携してスタートした。現在は13学会が参画し、登録症例数は15年までで736万症例に上る。さらに、NCDに加え、患者とその家族のDBであるPeOPLe(Person centered Open PLatform for well-being)の試行も始まっている。
こうした臨床データベースシステムの可能性について、ある薬が単に高齢者に対して要注意というだけではなく、高齢者でも何歳以上なのか、糖尿病や透析の有無、がんの進行度合いなどの様々な要素を踏まえた上での患者にとって最善の治療が提案できれば、「現場と臨床疫学専門家との連携によって新しいEBMが構築されていくだろう」と期待を寄せる。
なお、ビッグデータの解析ではもはや有意差を議論する意味は失われ、プロセスの再現性が必要であることを強調した。その上で、データおよび解析の質を担保する必要があり、日本臨床疫学会が横軸の役割を果たす方法論を示すことで、すべてのデータで最高の質を担保し、データの活用につなげていきたいと述べた。
康永氏の演題は「レセプト・DPCデータを活用した臨床研究」。ビッグデータで何ができるのか、多くの事例を紹介した。なかでも薬効については、アルガトロバン、エダラボン、オザグレルを取り上げ、「エビデンスのない手探りの世界」で医師たちが「効いているのか効いていないのか分からない」と口をそろえる薬剤を、厳格に管理された状態下で非常に限られた集団への投与となる治験ではなく、まさにリアルワールドの効果を見ることができる、とその有用性を訴えた。
医薬品の有効性評価のほか、院外心肺停止患者の医療費、東日本大震災後の避けられた入院の増加などの研究も各領域のリーディングジャーナルに掲載されたことを紹介し、臨床疫学が前向き研究の困難な希少疾患の疫学研究や記述研究に有用であることを示した。そして臨床の医師等が現場で持つクリニカルクエスチョンに即した研究こそ臨床疫学研究であり、意義ある研究にするためには臨床の医師等のアイデアが必要だとも述べた。「ライフコースおよびリアルワールドデータを活用した臨床研究」の演題で登壇したのが川上氏。
21世紀は自発データ、リアルデータの時代であるとして、これまでの臨床試験の順位である介入研究(1:ランダム化試験、2:非ランダム化試験)、観察研究(3:コホート研究、4:ケースコントロール研究)に対して、介入研究の1軍と観察研究の2軍が戦っている状況であるとした。また、DB研究には学会、レジストリー等の疾患登録系とレセプト、DPC、カルテ等のリアルワールド系の2つがあることを示し、自らが地方公共団体を訪問して自治体のデータ活用を訴えており、最近は学校健診、母子保健情報のDB化に取り組んでいることを力説した。
また、氏の教室では大手調剤薬局チェーン4社と契約し、年間約3000万枚の処方せんデータを解析している。調剤薬局データは例えば秋田と京都では薬の出し方がどう違うか、後発品の置き換わり方はどう違うかを分析できるという。
内閣官房の事業の1つとして電子カルテのDB構築も進めている。現時点で医療機関117施設、200万人超の電子カルテ情報を収集した。電カル情報を提供する医療機関には、例えば2型糖尿病患者におけるA1cコントロールの全国平均との比較や、A1c8以上のインスリン未使用の患者にインスリンを投与した場合の半年後の違い、などの情報を提供しているとした。
DBの可能性については、例えばある薬剤が使われている患者と使われていない患者とで、尿中アルブミンやクレアチニンにどのように差が出るかという数値系のアウトカム研究もできると挙げた。
副作用についても、「特定使用成績調査、3000例調査はコントロールがなく学術的には意味がない。副作用が出ても薬のせいか病気のせいなのか分からない」と述べたうえで、「適応拡大や添付文書改訂で必要とされている臨床試験をDB解析で代替して薬を評価できるようになれば、DBの役割はかなり拡大するだろう」と期待を寄せた。
中央大学の大橋靖雄教授はフロアより、製薬企業が実施する製造販売後調査に対してPMDAは意識を変えつつあると発言した上で、DB構築において個人情報保護に対する特例法が必要か?DBで医療費の適正化の道は開けるか?の2点について演者に質問した。特例法には3人とも必要と答え、2点目については医師の意識を変える必要があること、HTA(Health Technology Assessment)の技術者が不足しており育成が必要、償還や個人負担も必要との返答もあった。