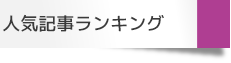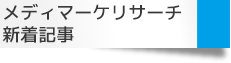■行政トピックス
1.中医協薬価専門部会 5月17日
業界代表、「新薬創出等加算」コンセプト維持を要望
中医協薬価専門部会は5月17日、関係業界からヒアリングを行った。昨年末にまとまった政府の薬価制度抜本改革基本方針に「新薬創出・適応外薬解消等促進加算制度をゼロベースで抜本的に見直す」と盛り込まれたことを踏まえ、日薬連の多田正世会長は「加算の制度化」という表現を用いず、「特許期間中の新薬の薬価を維持する薬価改定方式の制度化」を求めた。製薬協の畑中好彦会長も「新薬創出等加算のコンセプトを維持しながら、新たな形で薬価制度を構築してほしい」と訴えた。
新薬創出等加算をめぐっては、昨年の中医協で中川俊男委員(日医副会長)が「新薬のイノベーションに新薬創出等加算で対応するのは限界がある。ほかの財源を検討すべき」と繰り返し主張したほか、政府の基本方針には「ゼロベースでの見直し」が明記され、業界に危機感が高まっていた。
薬価専門部会で今後、新薬創出等加算の見直しに向けた議論が予定されており、それを前に、業界側は先手を打った形。多田会長は、「今回の意見陳述において最も強調したいのが新薬創出等加算」と切り出し、同加算のコンセプトは「特許期間中の新薬の薬価維持によるイノベーションの推進」と指摘。
その上で、「後発品への置き換えが加速度的に進み、特許期間中の新薬から得られる収益は、将来に向けた研究開発への投資を継続的に行う上で、これまで以上に重要なものとなっている」現状や、「製薬企業は新薬創出に向け積極的に取り組んでおり、未承認薬・適応外薬の解消も順調に推移している」実績を説明し、「同加算のコンセプトに基づく薬価改定方式の制度化」を求めた。
一方、米国研究製薬協(PhRMA)のパトリック・ジョンソン在日執行委員会委員長は「新薬創出等加算の導入は、特許期間中の新薬の薬価を維持する仕組みであり、外資系企業にとって日本への研究開発投資を活性化させる上での重要な判断材料となってきた」として制度の維持を求め、「現行の仕組みから薬価を維持する品目の適用範囲を縮小すべきではない。特許期間満了後には大幅な薬価引き下げを行うとともに、速やかに後発品へと置き換えることで、イノベーション推進を継続する十分な財政的余地を生むことが可能と考える」と訴えた。
これに対し、吉森俊和委員(協会けんぽ理事)は「我々患者サイドとしては、企業のR&Dに対する将来に向けたインセンティブ的なコストを上乗せされて患者が負担することは、なかなか納得感が持てないのではないか。新薬創出等加算は試行であり、抜本的改革の時でもあるので、そろそろ違う方式を要件として考えて算定していく時期ではないか」との見解を示した。
日医の中川委員から同加算に関する発言はなかった。松原謙二委員(日医副会長)は「個々の患者にとって自分の病気が治るのは何にも代え難いもの。その費用をみんなで負担するのが保険本来の在り方。そこの制度をきちっとしてもらいたい」と発言した。
2.未承認薬・適応外薬検討会議 5月17日
ジプレキサ、がん緩和ケアに係る適応追加を公知と判断
厚労省の医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議は5月17日、抗精神病薬ジプレキサ(一般名オランザピン)について、抗悪性腫瘍剤投与に伴う消化器症状(悪心・嘔吐)の効能・効果を医学薬学上公知であると判断した。近く開催される薬食審医薬品部会で公知申請にかかわる事前評価を通過すれば、その時点から保険適用となる。
検討会議では堀田知光座長が「各国(欧米等6カ国)で効能・効果のところに記載されているものはない。ガイドラインにはある。その意味で、日本で初めて、順調に進んでいけば、効能・効果に追加される」とコメントした後、構成員から反対意見はなく公知申請への該当性が了承された。
また、今回の検討会議では、ケノデオキシコール酸(一般名、製品名チノ、藤本製薬)の脳腱黄色腫症に対する効能・効果、カペシタビン(一般名、製品名ゼローダ、中外製薬)の神経内分泌腫瘍に対する効能・効果、テモゾロミド(一般名、製品名テモダール、MSD)の神経内分泌腫瘍に対する効能・効果について、医療上の必要性が高いと認められた。
■セミナー便り
1.卵巣がん治療にPARP阻害剤オラパリブの登場を期待
-慶応大学医学部産婦人科:青木大輔教授-
慶応大学医学部産婦人科の青木大輔教授は5月11日、アストラゼネカ主催のメディアセミナーで講演し、同社が遺伝性卵巣がん治療薬として開発中のPARP阻害剤オラパリブについて「患者を診ている立場からは早く使ってみたい」と期待を述べた。
オラパリブは、BRCA遺伝子変異陽性白金製剤感受性再発卵巣がん患者を対象としてオラパリブ維持療法とプラセボを比較した国際第3相SOLO-2試験2試験(n=295人)の結果、主要評価項目である治験医師評価による無増悪生存期間(PFS)中央値においてプラセボ5.5カ月に対してオラパリブ維持療法19.1カ月と統計学的に有意に延長を示した(ハザード比0.30;95% 信頼性区間0.22~0.41、p<0.0001)。
青木教授は「色々な臨床試験が行われているが、最近、これほど(PFS中央値の)間があいているのをあまり見たことがない」と評価した。SOLO-2試験は副次評価項目で二次進行または死亡までの生存期間(PFS2)についても検討しており、青木教授は「その後の治療の推移を見据えた解析も行われている。再発の卵巣がんはなかなか治癒に結び付けられないという観点では、このような解析も大変大事だと思う」と話した。
卵巣がんのうち、遺伝性の卵巣がんは5~10%と推計されている。遺伝性の卵巣がんのうちBRCA1遺伝子変異を原因とするものは~70%、BRCA2遺伝子変異陽性が原因のものは~20%といわれている。オラパリブはBRCA1/2遺伝子変異陽性の卵巣がんに対する治療薬として欧米で承認され上市されているが、国内では第3相段階にある。
今年3月には国内でBRCA遺伝子変異陽性の卵巣がんを予定される効能・効果として希少疾病用医薬品に指定された。なお、アストラゼネカでは4月下旬から国内でBRCA遺伝子変異を有する白金製剤感受性再発卵巣がんに対する維持療法(単独投与)を対象とした人道的見地から実施される治験(拡大治験)を開始している。
卵巣がん対象のPARP阻害剤としてはテサロ社のニラパリブ、クロビス・オンコロジー社のルカパリブ、ファイザーのタラゾパリブ、アッヴィのベリパリブが開発中。青木教授は「確実にオラパリブが日本で最初に登場することになる。今後、何が使いやすいのか患者に個別に対応することになるだろう」とした。
青木教授は「BRCA遺伝子変異がある卵巣がんに対してPARP阻害剤などの開発が進められている。こういうものがしっかり使える体制を今から構築しておく必要がある」とした上で「自分の遺伝的リスクを知りたくないという人もいるかもしれないが、知ると卵巣がん予防や治療にダイレクトに応用できる時代が来ているので、こうした観点で遺伝学的検査が普及していけばいいのかなと思う」とした。
■セミナー便り
2.特発性慢性蕁麻疹に抗体薬「早い人は1日で」
-広島大学大学院:秀道広教授-
広島大学大学院医歯薬保健学研究院統合健康科学部門(皮膚科学)の秀道広教授は5月22日、ノバルティスファーマ主催のメディアセミナーで講演し、特発性慢性蕁麻疹治療剤ゾレア(一般名オマリズマブ)について、「強力なツールが登場した」と評価した上で「我々は誰にいつまで使うか問われている」と指摘。「早い人は1日で良くなる。欧米では1週間で多くの人が良くなるということが言われている。遅い人は3回打って初めて効く人もいる。全然効かない人もいる。なので、3回までは使ってみる。3回打って全然効果が無い人は望みが薄いので、いったんはその治療を見直すのがいい」と語った。
ゾレアは気管支喘息治療剤で、17年3月に特発性の慢性蕁麻疹(既存治療で効果不十分な患者に限る)への適応が追加された。食物、物理的刺激などの蕁麻疹の症状を誘発する原因が特定されず、ヒスタミンH1受容体拮抗薬の増量などの適切な治療を行っても、日常生活に支障を来すほどの痛みを伴う膨疹が繰り返して継続的に認められる場合にゾレアを追加して投与する。
用法および用量は成人および12歳以上の小児には、1回300mgを4週間ごとに皮下注射する。用法および用量に関する使用上の注意として、日本人を対象とした臨床試験において、ゾレアの12週以降の使用経験はないため、12週以降も継続して投与する場合は、患者の状態を考慮し、その必要性を慎重に判断することとされている。
講演では特発性の蕁麻疹の初期治療への反応性と予後を提示。急性蕁麻疹(発症後1カ月以内)の患者は発症後1週間以内に医療機関で治療を開始した場合、治療開始1週間以内に治癒率(薬を使わなくても症状が出ない状態)が73.2%、4週間以内に85%、1年で93.3%であった(田中稔彦ほか、アレルギー64:1261-8,2015)。秀教授は「これらの治療のほとんどは抗ヒスタミン薬の治療で治っている。だから多くの発症して間もない患者は抗ヒスタミン薬でうまくいく。ところが一部の患者は慢性に経過する」と解説。
慢性蕁麻疹(発症1カ月以上経過)では、発症後6週間以上経過後1種類の標準量の抗ヒスタミン薬で症状消失しない場合、治癒率は1年で11.5%、2年で13.9%、5年で27.7%であり、軽快率(通常量の抗ヒスタミン薬を使っていれば症状が出ない状態)は1年で40%、2年で60%であった(Hiragun M, et al.Allergy 68:229-235,2013)。秀教授は「患者にとってはまずとにかく症状が無くなるまでに結構時間がかかり、薬を使っていれば症状が出ないが止めるとまた症状が出るという期間が結構長い。この期間は患者にとって大きな不安」とアンメットニーズを説明。「多くは抗ヒスタミン薬で治るけれども、一部はそれだけではうまくいかなくて、そうした人たちは長く疾患に悩まされることになる」とし、こうした既存治療による効果が不十分な患者に対しゾレアという治療選択肢が増えたことについて期待を示した。
なお、日本皮膚科学会は5月17日、ゾレア使用可能施設についての注意喚起を行い、皮膚科専門医またはアレルギー専門医が喘息およびアナフィラキシーに対応できる医療施設で使用することとしている。日本アレルギー学会からも同様の声明を出す予定だ。
秀教授は「アナフィラキシーショックは日本では報告はないが、海外では報告があり、最大2%くらいかもしれないといわれている。可能性がないわけではないため慎重にする必要がある」とコメントした。