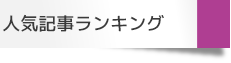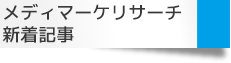■行政トピックス
1.中医協費用対効果評価等合同部会 11月10日
課題山積、今度は企業分析と再分析結果に大きな乖離
厚労省は11月10日の中医協費用対効果評価、薬価、保険医療材料専門部会の合同部会で、来年4月の診療報酬改定時に費用対効果評価結果を価格に反映させることを目指している、試行的導入(医薬品7品目を含む13品目)について「一部の品目につき、企業分析の結果と再分析の結果が大きく異なることが分かった」と説明。その上で、両分析のうち、価格変動のより少ない方を採用して4月に価格調整をいったん行い、その後、妥当性の高い分析のあり方について検証作業を進め、最終的な価格調整を行うという2段階で対応する方針を示した。
試行的導入は、16年4月に対象品目が選定され、5月から企業分析について分析手法等に関する事前相談を開始、9月には費用対効果評価専門組織において分析枠組み等の妥当性を確認し、10月から企業分析が開始された。17年4月に企業分析の結果が提出され、5月からは第三者による再分析がスタート。10月に再分析結果がまとまり、現在、総合評価(アプレイザル)の段階にある。
この段階に至って厚労省が、一部の品目で、企業分析と再分析結果に大きな乖離があったことを明らかにしたことに、中医協委員は「最終段階のアプレイザルのとりまとめという段階において、基本的な課題が出てくることに対しては甚だ遺憾であると言わざるを得ない」(吉森俊和協会けんぽ理事)と苦言を呈した。
厚労省の説明によると、両分析の結果が大きく異なったのは、企業分析を開始する前に、分析の枠組み等に関する事前相談を行った上で進めてきたが、それでも互いの認識の違いや、より適切なデータについての見解の相違が残ったままだったことが要因という。
吉森委員は、「費用対効果評価制度がご破算にならないように、しっかり具現化できるような体制強化を要望しておきたい」と述べた。
両分析結果が大きく異なった品目について、妥当性の高い分析のあり方についての検証作業は18年中をめどに実施するが、最終的な価格調整時期について厚労省は、「具体的な時期については改めて相談したい」と述べるにとどめた。
また、最終的な価格調整について「それまでの一定期間、別の形でいったん価格を設定していることから、その間の分を勘案して調整するということになる。時間軸的にかなり複雑なオペレーションになるので、改めて整理して提示したい」と説明した。
■セミナー便り
1.耐性菌の新薬開発に総合的施策を
-製薬協国際委員会:山口栄一幹事-
日本製薬工業協会(製薬協)国際委員会幹事の山口栄一氏(塩野義製薬)は11月9日の製薬協メディアフォーラムで、AMR(薬剤耐性)に対する製薬協の取り組みを説明した。AMRの新薬に関して、「研究開発の推進」「薬事承認の迅速化」「採算予見性の確保」を総合的に行うことが重要だと述べた。具体的には、AMRに特化した創薬コンソーシアムの設立や国際共通の臨床評価ガイドラインの策定、優先審査制度の創設、新薬承認時に報奨金が政府・公的機関から企業に支払われる制度などを挙げた。
コンソーシアムは、アカデミア・大学の創薬シーズだけでなく、製薬企業の創薬シーズ、化合物ライブラリー、そして研究開発のノウハウを活用して研究開発を加速させるために設立する。
臨床評価GLは、日本では耐性菌感染症の発生が少ないことから、必要最小限の有効性・安全性のデータパッケージで審査を行うために策定する。臓器別の適応に限定せず、起炎菌別の承認形態を考慮することも求めた。また、データを他国でも利用できるように日米欧共通の基準を明確化することも提案した。
承認取得時の報奨制度は、AMRの新薬、ワクチン、診断法などの開発に成功した企業が適切な利益を確保できるように、政府や公的機関から報奨を受ける仕組み。抗菌薬の収益性の低さを補償する意味合いがあるという。「診療の対価ではないので、財源は通常の診療報酬制度から切り離して運用されるべきだ」と山口氏は補足した。
採算の予見性を高めるために「薬価の事前審査制度」も提案した。開発品のターゲットプロファイルに基づく薬価を事前に申請し、合意した上で開発を進めるものだ。
製薬協はこれらをまとめ、今年(2017年)4月に厚生労働省に提案している。その中で、審査期間を9カ月程度に短縮する優先審査制度の創設については、「すでに厚労省審査管理課から『薬剤耐性感染症治療薬・診断薬については優先審査制度に含める』と言われている」(山口氏)とした。
■セミナー便り
2.ダラザレックス「治す可能性がある薬」
-日赤医療センター:鈴木憲史骨髄腫アミロイドーシスセンター長-
日本赤十字社医療センターの鈴木憲史骨髄腫アミロイドーシスセンター長は11月8日、ヤンセンファーマ主催の多発性骨髄腫治療薬ダラザレックス(ダラツムマブ)のメディアセミナーで「治す可能性がある薬が出てきたという意味ではルネッサンスだ」と期待を示した。多発性骨髄腫は血液がんの1種で、骨髄にある形質細胞ががん化する疾患。「これからは3剤を3つくらいのレジメンにし、3年くらいきっちり使用して、MRD(微小残存病変)ネガティブを確認して治療をやめる。10年間で半分の方が生きて、3割の方が治るというのを目標にしようと考えている」と話した。
ダラザレックスは9月27日に再発・難治性の多発性骨髄腫の効能・効果で国内承認を取得した。試験ではレナリドミド+デキサメタゾン併用およびボルテゾミブ+デキサメタゾン併用に上乗せし、いずれも主要評価項目の無増悪生存期間(PFS)を有意に延長した。
将来的には「初発で使うべき薬」(鈴木センター長)という。安全性では投与後にアレルギーのような症状が現れるインフュージョンリアクションに注意が必要。課題は点滴静注が長時間になることで、鈴木センター長は「外来化学療法室のベッド数によっては本当は使いたいのだけれど使えないということがある。いま開発されている皮下注に持っていけないか」と指摘。ヤンセンでは皮下注の開発を進めており、鈴木センター長は「初発に使えるのが来年(2018年)あたり、皮下注は再来年あたり」と見通した。
■セミナー便り
3.国内初のメルケル細胞がん治療薬
-国がん中央病院:山﨑直也皮膚腫瘍科科長-
国立がん研究センター中央病院の山﨑直也皮膚腫瘍科科長は11月6日、ファイザーとメルクセローノが主催した国内初のメルケル細胞がん治療薬抗PD-L1抗体バベンチオ(アベルマブ)のメディアセミナーで「長期生存が望めるようになった」と期待を語った。
メルケル細胞がんは皮膚がんの1種で、国内患者数は14年の厚労省患者調査の皮膚悪性腫瘍患者数1万5000人のうち0.5%にあたる75人と推計されている。遠隔転移のない患者には、外科的切除と放射線療法が標準治療となっており、50%は根治可能。残りの50%は再発を来たし、転移症例は1~2年内に死亡する。転移症例の5年生存率は18%と低かった。遠隔転移のあるステージ4患者には、適応外ではあるが、白金製剤による化学療法(カルボプラチンにエトポシドなど)が実施されていた。「形態が小細胞肺がんに似ていて、小細胞肺がんの薬が効く。小細胞肺がんの標準治療になっているからメルケル細胞がんにも使われるという形で行われてきた」(山﨑科長)。
ただし、白金製剤による化学療法は「手応えはあるが効く期間は短い」。山﨑科長によると、1次治療の奏効率は55%、無増悪生存期間(PFS)は94日。2次治療は奏効率23%、PFSは61日であった。そこに登場したのがバベンチオで、国際共同第2相JAVELIN Merkel 200試験は化学療法歴のある患者を対象としたパートAで奏効率31.8%、6カ月奏効持続率93%、12カ月奏効持続率74%であった。山﨑科長は「2次治療で2カ月前後だったのが、このくらいになったのが使っていて素晴らしいなと思う」と評価。今後の展開として「現在推奨されていないが、ステージ3のハイリスク患者において術後の再発予防として使用する可能性も探っていく」と話した。
■セミナー便り
4.オテズラ「開業医が使用している」
-NTT東日本関東病院皮膚科:五十嵐敦之部長-
NTT東日本関東病院皮膚科の五十嵐敦之部長は11月7日、セルジーンが3月に発売した経口乾癬治療薬オテズラ(アプレミラスト)について「9月時点で1万1000例に使用されている。注射製剤は10年以降6剤発売され、のべで1万2000~3000例と聞いているので、かなりハイペースだ。一説によると8~9割は開業医の先生方に使われている」と現況を語った。オテズラはシクロスポリン以来25年ぶりとなる内服薬。乾癬治療薬は抗IL-17A抗体コセンティクス、トルツ、ルミセフが上市されたが、生物学的製剤は日本皮膚科学会の承認施設だけで使用できる。一方、オテズラは承認施設でなくても処方できることから、開業医の処方が多いという。腎機能障害や肝機能障害などの臓器障害が少なく、原則モニタリング検査が必要なく扱いやすいことも一因とした。
臨床上の位置付けについては「外用剤(光線療法)でダメだった時に生物学的製剤に行くのではなく、まずアプレミラスト。内服薬にはレチノイド(エトレチナート)、シクロスポリンもあるが、アプレミラストのほうが副作用が少なくはるかに扱いやすい」と語った。
セルジーンはオテズラ発売により炎症・免疫性疾患領域に参入した。同社の野口暁社長は「早期からウェブ等デジタルを使用してコミュニケーションを始めて、3月の発売以降は営業が訪問した。情報の取り方に関して先生方のニーズが多様化しているので、それに合わせるように営業体制を整えていきたい」と話した。
■セミナー便り
5.双極性障害はうつの治療が重要
-赤坂クリニック・坂元薫氏-
赤坂クリニック坂元薫うつ治療センターの坂元薫センター長は11月7日、共和薬品工業主催のプレスセミナーで講演し、うつ病相と躁病相を繰り返す双極性障害について、生涯再発率が95%と極めて高く、自殺率も一般人口の25倍以上であることなどを挙げ、適切な診断と治療が必要だと指摘した。同疾患の経過ではうつ病(双極性うつ病)が病相期のほとんどを占めることから、双極性うつ病の診断・治療が重要な課題だとも指摘した。
双極性障害は、うつ病の期間の他に、入院を要するような重度の躁病を呈するⅠ型と、軽度の躁病で持続期間も短いⅡ型に分類される。「だいたいはうつ症状から始まる」(坂元氏)ものの、双極性うつ病と単極性うつ病との鑑別は難しいという。坂元氏によると、海外では、うつ病外来受診者の60%が実は双極Ⅱ型障害だったと報告されている。別の研究では、双極Ⅱ型障害患者の13.4年の経過の中で、うつ病相が50%、寛解期が50%弱で、躁病・軽躁病相は1.3%にすぎなかった。
双極性うつ病に抗うつ薬を投与した場合、効果が見られないか、逆に躁病に転じることがある。そのため、治療は炭酸リチウムやバルプロ酸などの気分安定薬が「ほぼ必須」(坂元氏)で、抗精神病薬も使用される。
今年(2017年)10月、抗精神病薬クエチアピン徐放錠(ビプレッソ)が双極性障害のうつ症状の新薬として発売された。坂元氏は「国際的に評価されているクエチアピンに適応がないことは歯がゆかった。大いに期待している」と述べた。すでに双極性障害のうつ症状に承認されている抗精神病薬オランザピンとの違いについては、「(適応外で使用していた)クエチアピンとの比較」と前置きして「決定的な差異はないという感覚。オランザピンがいいという人もいれば、クエチアピンがいいという人もいる。ツールは多い方がよい」とした。
■セミナー便り
6.支持緩和医療、難治がん例では早期介入で生存期間延長も
-福岡大学医学部総合医学研究センター:田村和夫教授-
日本医師会と米国研究製薬工業協会(PhRMA)が「超高齢社会における緩和ケアのあり方」をテーマに11月9日に共催したシンポジウムにおいて、福岡大学医学部総合医学研究センターの田村和夫教授は「がんと診断されたときからの緩和ケア~がんを標的とした治療と支持・緩和医療の統合を目指して~」の演目で基調講演を行った。
田村教授は、がんと診断されたときからがん治療科と支持・緩和医療科が連携・統合されるのが理想的な形のがん治療だが、その統合にはまだ幾つかの課題があると述べた。第1に挙げたのが、がん治療が厳格な基準を持つevidence-basedであるのに対して、支持・緩和医療はexperience-basedに留まっている点だ。統合するためには、経験的な医療がかなり含まれている支持・緩和医療がevidence-basedに進化していかなければならないとの認識を示した。
次に挙げたのは開始時期についてである。2010年のNEJMが掲載した、転移性非小細胞肺がん患者に対する早期緩和ケアの論文が紹介された。この試験は、新たに転移性非小細胞肺がんと診断され化学療法を施行予定の患者を、標準治療に早期緩和ケア(3週以内に介入開始、1カ月毎の定期的な緩和医・専門看護師チームによる外来診療)を組み合わせて行う群と標準治療のみを行う群(希望時のみパリアティブケアチームが診療)に割り付け、12週間後に評価を行ったもので、評価項目はQOLと情動(うつ)である。NEJMアブストラクトによれば、早期緩和ケア群は標準治療群に比べ、QOLが良好であり(p=0.03)、抑うつ症状を有する患者が少なかった(16%対38%、p=0.01)。また生存期間の中央値も、終末期の積極治療を受けた患者は標準治療群の方が多かったにもかかわらず、11.6カ月対8.9カ月で早期緩和ケア群の方が長かった(p=0.02)。田村教授は「今のがんをターゲットとする薬が、数カ月の延長を有意差として承認されていく現実を考えると、決して少ない延長期間ではない」と評価し、診断早期からの介入はQOL、うつ症状の改善並びに生存期間の延長が得られると結論付けた。
支持・緩和医療の提供場所については、2015年にBMC Palliative Careに掲載された厚生連高岡病院の村上望医師らの研究を紹介した。これは190人のがん患者を対象に、ホスピスでケアを受ける群と、在宅でケアを受ける群で生存期間の差を見た研究である。結果は、在宅ケア群の生存期間はホスピスケア群の生存期間よりも有意に長いか、少なくとも短くはなっていないことを示すものだった。田村氏はこれらの研究結果から、「提供の場は病院(入院)ではなく、自宅(外来あるいは在宅診療)が望ましい」と結んだ。
■セミナー便り
7. 2型糖尿病患者、残薬ありが「33.1%」
-横浜市立大学分子内分泌・糖尿病内科学教室:寺内康夫教授-
横浜市立大学分子内分泌・糖尿病内科学教室の寺内康夫教授は11月14日、日本イーライリリー主催のメディアセミナーで「経口糖尿病治療薬を服用中の2型糖尿病患者の33.1%に残薬が生じていた」と報告した。服薬回数が1日に3回以上の患者や、軽症な楽観的タイプ、多忙な治療あきらめタイプに残薬が生じやすいという。
寺内教授は残薬解消に向けて「服薬回数を1回にまとめられないか、配合剤はどうかといった配慮が必要」と述べたほか、「処方日数を変えて処方せんを打ち出すのは余分に時間がかかる。日数の問題で解決できることは薬剤師などチーム医療を担うスタッフに任せてもいいという考え方もある。大きな病院では難しいところがあるかもしれないが、検討すべき課題である」と述べた。