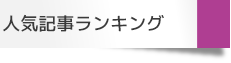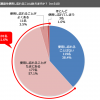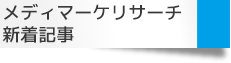■記者会見
1.がん領域に再参入「来年国内で開発に着手」
-グラクソ・スミスクライン:菊池加奈子社長-
グラクソ・スミスクライン(GSK)日本法人の菊池加奈子社長は12月5日の記者会見で多発性骨髄腫を対象とした抗体薬物複合体(ADC)GSK2857916について「来年国内で開発に着手する」と話し、国内におけるオンコロジー領域への再参入を発表した。開発本部長の高橋希人専務によると、国内は第1相から開始する見通し。社内の人的資源の確保が課題で、アウトソーシングの活用を視野に入れて開発を進める。
GSKは15年3月にノバルティスにオンコロジー事業を移管したが、創薬研究の一環としてエピジェネティクス、細胞治療・遺伝子治療、がん免疫療法の研究を続けていたという。再参入にあたり高橋専務は「もう一度やる気を出してしっかり準備しているところ」と話し、「競合が激しいことは重々承知しているが、現在出てきているアセットは新規のメカニズムであり高い奏効率があるだろうということで開発を進めている。生存の最大化で競合の中でも特徴を出していきたい」と述べた。
GSK2857916は抗BCMA(B細胞成熟抗原)抗体薬物複合体で、海外は18年から多発性骨髄腫の4thラインの単剤療法を評価するピボタル第2相試験を開始する。海外第1相試験の中間結果報告では難治性多発性骨髄腫に対する単剤療法で奏効率(ORR)66.7%であり、FDAのブレークスルーセラピー、EMAのPRIMEに指定された。
日本法人はグローバルの方針に沿い、呼吸器領域、HIV/感染症領域、免疫・炎症領域、オンコロジー領域を重点として事業を進める。なお、17年度国内業績は重症喘息治療薬ヌーカラが牽引し「順調に進んでいる」(菊池社長)。開発品は免疫・炎症領域で全身性エリテマトーデス治療薬ベンリスタが9月に国内承認を取得。呼吸器領域ではCOPDを予定適応症とし3剤併用療法トレレジー・エリプタが国内承認申請準備中だ。
デジタル・イノベーションでは、英国サイバイト社のセマンティック・テキストマイニング技術を活用したテキスト分析をこの秋から国内の安全性業務の一部に導入している。
■記者会見
2.中期経営計画発表「5年以内に2製品出す」
-GHITファンド:BTスリングスビーCEO-
公益社団法人グローバルヘルス技術振興基金(GHITファンド)は12月11日、18年度から22年度までの中期経営計画を発表し、会見でBTスリングスビーCEOは「次の5年間以内に2製品出す」と目標と語った。GHITファンドはHIV、マラリア、結核、顧みられない熱帯病など開発途上国の感染症に対する治療薬やワクチン、診断薬の開発を行っている。13年4月に設立され、以降、資金拠出パートナーやスポンサーを拡大する一方、開発プロジェクトへの投資を続けてきた。現在は40プロジェクトが進行している。規制当局の承認を取得した品目や上市製品はまだないが、今後の5年間でいよいよそれが誕生する見通しだ。臨床試験の結果次第なので2製品の内訳は明示していないが、18年に第3相を開始する小児用の住血吸虫症治療薬など臨床試験実施中の7品目が候補となっている。
後期開発品目が多くなるにつれ、開発費用の増加が見込まれるが、スリングスビーCEOによると新たなパートナーとの共同出資という形で資金を確保する。例えば、小児用の住血吸虫症治療薬は第3相開始にあたり、サハラ以南のアフリカにおける感染症治療薬の開発推進と臨床試験支援を行うオランダの機関EDCTPから出資を得た。
一方、中期経営計画では後期開発品目の推進だけでなく、リード化合物の特定や非臨床試験の実施など早期のパイプラインでも目標を定めている。スリングスビーCEOは「進行していないあるいはサイエンスがうまく進んでいない案件はなるべく早く抽出し終了する。その代わりに新たな案件を獲得する」という形で推進するとした。
また、今後の5年間では診断薬への投資にも注力する。スリングスビーCEOによるとグローバルヘルスにおけるニーズが高く、治療薬やワクチン開発に比べて、開発費用が安価で開発期間が短いといった特長がある。現在のパイプラインでは富士フイルムの結核診断薬といった革新的な候補品が進んでいるという。
■セミナー便り
1.ピロリ除菌は不利益も知ったうえで行うべき
-国立がん研究センター社会と健康研究センター:津金昌一郎センター長-
2017年12月5日、国立がん研究センター社会と健康研究センターの津金昌一郎センター長はブリストル・マイヤーズスクイブが主催した胃がん啓発セミナーで、「ピロリ菌の除菌には不利益もある。利益不利益を知ったうえで行うべき」との見解を述べた。
ヘリコバスター・ピロリの非感染者が胃がんになる確率は1%以下と極めて低く、胃がん患者の99%はピロリ菌に感染している。胃がんを発症するのは感染者の一部であるが、除菌することにより胃がんリスクを30〜40%低減できるというエビデンスも揃いつつあるという。
一方でIARC(国際がん研究機関)が14年に出した胃がん高率国への予防対策実施へ向けた勧告には、胃がん予防戦略としてのピロリ菌除菌の重要性とともに、「住民レベルの抗生物質投与による胃がん予防の実施可能性と及ぼす影響については未知の部分が残る」「胃がん高率国の公衆衛生当局は、ピロリ菌のスクリーニングと除菌による利益と不利益を総合的に評価できるプログラムの導入を考慮すべきである」との記載があることを紹介した。除菌により増える可能性のある負の影響として挙がったのは食道腺がん、食道胃逆流、喘息、湿疹、免疫系への影響などである。
津金氏はIARCのワーキンググループのレポート(14年)が除菌による耐性菌出現への影響について、「処方を厳格にしている国においても、高齢化の影響により抗生物質の使用が増えており、大量のピロリ菌除菌がこれらの負担をもたらすことは疑いがない」と指摘していることにも触れ、「高齢者にむやみやたらに除菌のために抗生物質を使って耐性菌が出てきたら大変なことになる。この辺りはもう少し吟味していかなければならないが、(不利益についてもあまり知られていないまま)保険適用されて皆が使い出した。不安が残る」と懸念を表した。
実は今年10月に発表されたがん対策推進基本計画(第3期)も、「感染が胃がんのリスクであることは、科学的に証明されている」と明記する一方、「除菌が胃がん発症予防に有効であるかどうかについては、まだ明らかではない」として「除菌の胃がん発症予防における有効性等について、(引き続き)国内外の知見を速やかに収集し、科学的根拠に基づいた対策について検討する」との表現に留めている。
近年は中高生への除菌を実施している自治体もある。これについて津金氏は、除菌は利益・不利益を知ったうえで、親や自治体ではなく本人の判断で行うものであり、「成人前に除菌によって胃がんを免れる人もいるかもしれないが、ものすごく確率は低い。それよりも子どもの時に抗生物質を使うことによって起こる不利益についてまだ分からない部分も残るなかで、むやみに抗生物質を使うのは反対だ」との立場を明らかにした。
■セミナー便り
2.「臨床研究モニタリング」と「再生医療臨床試験」の新展開
-第38回日本臨床薬理学会学術総会-
第38回日本臨床薬理学会学術総会が12月7日から3日間にわたりパシフィコ横浜で開催された。シンポジウム25「臨床研究法案成立後の臨床研究のモニタリング」では、日本製薬医学会の岩崎幸司氏が、ICH-E6で強調されている‘quality of design’の考えの下での試験体制にはシティマティックな対応による質の確保と透明性が求められるとした。さらにヒトとカネが少ない状況のアカデミアでは被験者保護とデータの信頼性確保のためには効率性も重視した‘Quality Management System’が必要であると述べた。
エイツーヘルスケアの林行和氏はこれまでの施設訪問と100%SDV(Source Data Verification)に代わるセントラルモニタリングの方法を提案した。同氏は、臨床研究におけるモニタリングの目的は是正から予防へ、SDVは100%から部分的へと変化し、データの完全性ではなく結果の信頼性を重視する方向にある。中央でモニタリングレビューすることによってデータ全体から問題の有無の可能性を確認することになるが、データの見方のポイントとして重要な課題となるのは不正チェック‘Fraud Detection’とエラーの閾値設定であることを強調した。
九州大学病院の稲田実枝子氏はAROではモニター専任者は少数であり、臨床研究の知識は不十分な現状を述べた上で、多くは院内の薬剤師や看護師であることから院内連携には大きな強みであるとした。また、モニター教育は急務であり九州地区で研修会を実施していること、いまだ経験不足であり時間が必要であるが、モニタリングを実施体制整備から病院間連携を統一化して一流のプロマネを確保していきたいと述べた。慶應義塾大学病院の松嶋由紀子氏は稲田氏と同様にアカデミアモニターの人材と能力不足の現状を紹介し、研究企画から成果報告まで品質マネジメント全体を把握できる人材育成の重要性を指摘した。
総合討論で、モニタリングは閾値を定めたクオリティ目標の事前宣言が必要なこととアカデミアとCROの連携が当面の対応策であることが議論された。
シンポジウム33「再生医療と臨床薬理の関わり〜適正な評価をめざして〜」では、国際医療センターの飯山達雄氏よりグローバルヘルスに関わる者の立場から、途上国や新興国から再生医療への要望が強いことが述べられ、再生医療は患者が少なく比較試験は困難であり原材料細胞の品質が問題となる特長があり、細胞治療的、医療機器的、サイトカイン的な側面を持つ特性があることが示された。
成育医療研究センターの梅澤明弘氏は、日本では現在4品目が承認されているが他国と比較して非常に少ない現状を考慮すると、試験実施においてはサロゲートエンドポイント選択と閾値設定が重要であり、多数の評価項目による情報の最大化を目的にして、限られた例数での一定のエビデンスに対して、第三者委員会におけるベネフィット・リスクの比較考量が必要であるとした。
医薬基盤・健康・栄養研究所の松山晃文氏は再生医療試験の特性である症例が少なくデータベース化が困難であることに対して、現在、生物統計の方法が開発されているとし、再生医療の試験にSMO等がとっつきにくいのは再生医療が移植から始まった歴史があり、将来は日本の再生医療を世界に発信していきたいとした。また条件付きで早期承認されることから市販後調査においてはCRCの活躍の場があるとした。再生医療治療にはES細胞やiPS細胞に代表される置換型治療とサイトカイン治療があり、前者は移植に近いのに対して、後者は徐放配合剤に類似しており臨床薬理的手法の応用が期待されるとした。
再生医療の評価に対しての総合討論で、飯山氏は臨床薬理の専門家との議論を常に模索しているとし、梅澤氏は是非、臨床薬理から再生医療に入ってきてほしいとするなど、いずれの演者も臨床薬理専門家との連携協力を求めていた。また松浦氏は再生医療の研究は疾患を理解することにつながることも強調した。
臨床研究法案と再生医療等製品のガイダンスにより、臨床研究のモニタリングと再生医療の臨床試験・研究はそれぞれ脚光を浴びており、二つのシンポジウムは時機を得たテーマであった。シンポジウムの各演者は異口同音にそれぞれの分野はまだ専門家が少なく、専門家による研修・教育と他領域との連携が必要であると訴えた。とりわけ再生医療の臨床試験においては臨床薬理に対して大きな期待が寄せられた。両シンポジウムのキーワードはいみじくも共通して‘教育と連携’、‘サロゲートと閾値’であった。